◎「やべー人」との出会い
このところ、「自由」をテーマにして記事を書くことが多いのですが、考えてみれば、私はずっと「自由」を求めて生きてきたような気がしないでもないです。
私が初めて「自由」というのを意識したのは、19歳の時でした。
その時、私はダンスの専門学校に通っていて、二年生に上がる前の進級制作展で踊る即興舞踊を準備していました。
その時の私の指導を担当していたのが、私にとっての恩師である桜井郁也さんという方でした。
貼ったリンク先のページをご覧になった方はわかると思いますが、「けっこう怪しい感じの人」です。
「暗黒舞踏」と言って通じる方はいますか?
昔、そういう呼び方で呼称された前衛的な舞踊のムーブメントがあったのです。
彼ら暗黒舞踏家たちは、しばしば身体を白く塗りたくって、ほとんど裸みたいな恰好をし、そのままひたすら動かずに居続けたり、時には壊れた人形のような「のたうつ動き」をしてパフォーマンスをしていたようです。
それは、綺麗できらびやかなバレエやジャズダンスの世界とは一線を画す世界観です。
私の恩師である桜井さんは、そんな暗黒舞踏の流れをくむ舞踏家でした。
それゆえ、桜井さんの踊りは独特で、他の誰とも違っていました。
学校のある先輩は、「あの人はやべーよ」とよく言っていました。
その先輩自身も、クラスから外れていつも一人で踊っていた「変わり者」だったんですが、その「変わり者の先輩」をして「やべー」と言わしめていたわけです。
何が「やばい」のか聞くと、その先輩はこう答えました。
「だって、『ヒュー…と来てグシャッ!』だぜ?あんなの他の誰にできるよ?」
この「ヒュー…と来てグシャ!」は、確かに桜井さんの「底の知れなさ」をよく表している表現だったと思います(まあ、当人を間近に見たことがないと想像しにくいかもしれませんが)。
確かに、暗黒舞踏の系譜に連なる人たちのダンスは、バレエやジャズダンスのようにきらびやかでは無いですし、ブレイクダンスやロックダンスのようにクールでカッコいいわけでもありません。
しかし、そこには踊る人の存在をかけたかのような「凄味」があり、当時の私は桜井さんにある種「畏怖の念」にも近い感情を持っていたのです。
そして、そんな桜井さんから、進級制作展が近づいてきたある日、私は急に話しかけられました。
ちなみに、その頃の私は、もうダンスにすっかり飽き飽きしてしまっていました。
私は高校時代にブレイクダンスを始め、それからロックダンス、ヒップホップ、ハウスなどのジャンルを遍歴しました。
そして、専門学校に入学してからは毎日朝から晩までクラシックバレエの稽古に明け暮れ、バレエのテクニックを応用して、モダンダンスやジャズダンスまで踊っていたのです。
しかし、私はどのジャンルも「人前に出しても恥ずかしくないレベル」まで習熟すると、そこで「これはだいたいわかったから、もういいや」と感じてしまい、稽古への熱意が冷めてしまうことを繰り返していました。
そもそも、そんな風に飽きやすかったからこそ、私は様々なジャンルを遍歴して、「自分の退屈」を誤魔化していたのでもあります。
しかし、ある時にとうとう「やりたいジャンル」がなくなってしまい、私は「退屈」と直面するしかなくなってしまいました。
当時の私は学校の授業をボイコットして、空いた教室を勝手に使っては、大音量で好きなダンスミュージックを流しながらゴロゴロして暇を潰していたものです。
◎「自由に動いて」という重い課題
そんな私を見かけて声をかけてきたのが桜井さんでした。
「湯浅は即興やらないのか?」
それが桜井さんの第一声でした。
私は「ドキッ」としました。
それまでの私は振り付けのある踊りはやったことがありましたけれど、「完全即興」というのはやったことがなかったのです。
もちろん、ブレイクダンスやロックダンスのようなストリートダンスには、「ダンスバトル」というものがあり、そういうものに出る時は、「その場の思い付きで踊る」ということをしてはいました。
しかしそれは、「ダンスバトル」という形式に守られ、「ブレイクダンスやロックダンスのテクニック」という文脈によって保証されているものでした。
それゆえ、いかなるダンスのテクニックにも依拠せず、「ただ自由に踊る」ということは、当時の私には想像もつかないことだったのです。
それで、桜井さんの問いかけに対して「さぁ、どうでしょうね…」と私は曖昧に答えてやり過ごそうとしました。
しかし、次の週、桜井さんの「舞台製作の授業」がやってきたら、作品を見せるグループリストの最後に「湯浅和海」と私の名前がしっかり書かれていたのです。
つまり、私は何の準備もないまま、桜井さんの前で「自由に」踊って見せねばならなくなってしまったわけです。
他のグループが順番に桜井さんに作品を見てもらっている間、私は「どうしよう…」と考えていました。
桜井さんの目を誤魔化せないことはわかり切っていました。
なにせ「ヒュー…と来てグシャ!」の人です。
私がいつものようにブレイクダンスやロックダンスの即興を適当にやってやり過ごそうとしたところで、必ず引き止められるはずです。
それに、私としても桜井さんの前で、「出来合いのテクニック」を披露することはしたくありませんでした。
何故かはわかりませんが、それは「マナー」に反することのように感じられたのです。
とうとう私の順番がやってきました。
私はジャージに裸足という格好で桜井さんの前に立ちました。
しかし、何をどうしたらいいのか、私にはさっぱりわかりませんでした。
すると、桜井さんはいきなり「じゃあ、自由に動いて」と言いました。
「自由に?それってどうすればいいんだ?」と私は思いました。
さっきも書いたように、私は多数のダンステクニックを既にモノにしていました。
学校の教師は私を見本として前で踊らせていましたし、他のクラスメイト達からも私は一目置かれていました。
それにもかかわらず、私は「自由に動く」ということを一切知らなかったのです。
私の心臓は急にドキドキと速く打ち始めました。
そして、その恐怖に衝き動かされるように、私は暴れるように動き始めたのです。
自分でも自分が何をしているか、よくわかりませんでした。
でも、恐怖が強くなって私が頭を抱え込み始めた時、それまでずっと黙って私を見ていた桜井さんは、「感情表現じゃないよ」と急に言いました。
「感情表現じゃない?なら、これはいったい何の時間なんだ?」
私の中には答えはなく、それにもかかわらず、私は動き続けねばなりませんでした。
私は内側の不安と恐怖に押しつぶされそうになりながら、同時にそれを振り払うように動き続けました。
すると、しばらく時間が経ったとき、「ここまでにしよう」と桜井さんに止められました。
しかし、桜井さんは特に感想を言うわけでもなく、「じゃあ、また来週見せて」と言ったのです。
「やっと終わった」と思って安堵していた私は、「また来週もこれをやらないといけないのか…?」と絶望的な気分になったものです。
その時の私にとって「自由」は重く、苦しいものでした。
私はそれを受け止められなかったのです。
だからといって、桜井さんの前で「出来合いのテクニック」に逃げたくはありませんでした。
それゆえ私は、葛藤を抱えながら動き続けていたのです。
◎「自由」を前にして逃げ出したかつての私
桜井さんの前で動いていた間、私の内側では無数の「なぜ?」が浮んでは消えていきました。
私の内側は迷いと疑いでいっぱいで、その心は深く束縛されていたのです。
その次の週も、またその次の週も、同じようなことが繰り返されました。
しかし、そうしているうちに、私の作品は他のクラスメイトたちの注目を集め始めました。
しかも、賛否両論が起こっていて、「いいと思う」という意見もあれば、「いや、これはやっぱり変じゃないか」という意見もありました。
その様子を見ていた桜井さんは、ある時に「賛否両論が起こるってことは、それが良い作品だということだよ」といったような意味のことを言いました。
たぶん、それは桜井さんなりの誉め言葉だったのではないかと思います。
でも私は、今までそんな仕方で誉められたことが一度もありませんでした。
今までは、「人から反対されてはいけない」と思っていましたし、むしろ「賛否両論」なんて巻き起こしてしまったら、場が荒れてしまうからもっての外だと思っていたのです。
でも、桜井さんは「賛否両論を巻き起こすことは良いことだ」と、私に初めて言った大人でした。
そして、とうとう本番の日になりました。
結局、毎週同じことを繰り返しましたが、私は「進歩」と呼べるようなものは何も感じられませんでした。
ただ、「内側の不安」と闘いながら、みっともなく暴れ回っていただけです。
そしてそれは、本番においてもそうでした。
私は簡素なスウェットのズボンを穿いて上は裸という格好で、大勢の観客を前に踊り続けました。
ただ、それを「踊り」だと認識した観客がどれだけいたかはわかりません。
そもそも私にだって、「これは踊りだ」という確信がなかったのです。
むしろ、「こんなのが踊りなのか?」と思っていたくらいです。
ですが私は、「これが最後だ!」と思い、何もかも出し尽くすつもりで、必死で動き続けたのでした。
曲が終わり、照明が落ちた時、私の目からは涙が流れてきました。
なぜかはよくわかりません。
というのも、そこには様々な感情が混ざり合っていたからです。
その時の私の中には達成感もあれば無力感もありました。
また、「いったい観客からどう思われただろう?」という不安もありましたし、羞恥心や喪失感もありました。
それら無数の感情がまぜこぜになって襲ってきて、私は泣いてしまったのです。
その後、全ての作品の上演が終わった時、回収された観客のアンケートを見ていた桜井さんが私に声をかけてきました。
そして、「『裸の男の子が踊っているのが良かった』というやつが一つあったよ」と教えてくれたのです。
その声は、当時の私の耳には、なんだかちょっと嬉しそうに聞こえました。
実際、桜井さんの表情は、いつもより柔らかかった気がします。
しかしその後、私はダンスを完全にやめてしまいました。
なぜなら、「もうあんな怖い想いはしたくない」と感じたからです。
その時の私は、もはや「特定のダンスのテクニック」をなぞることに何の意味も感じなくなっていました。
「どこかで習い覚えた技術をただ反復して、それが何になるというのだろう?」
当時の私には、そんな風に思えて仕方なかったのです。
だから、与えられた振り付けを踊ったり、覚えたテクニックを披露したりすることが、私には無意味に思えるようになっていました。
しかし、そうかといって「自由に踊る」ということの恐怖にも、私は勝てませんでした。
「これからは自由に踊りを追求しよう」なんていう風に、楽観的に考えることはできず、むしろ私は「自由」を前にして逃げ出していったのです。
◎恐怖から虚無感へと変わっていった「自由」
それから後、何年かダンスから完全に離れた生活を送りました。
ダンスで食っていくことを捨ててしまったので、卒業後は社会にもうまく居場所が見つけられず、家の中に閉じこもっていた時期もあったのを思い出します。
しかし、紆余曲折を経て合気道の道場に通うようになり、そこで呼吸法や瞑想法と出会いました。
なんとなく神秘的な雰囲気に惹かれた私は、道場の中で教えられていることだけで満足できなくなり、自分でいろいろリサーチするようになっていきました。
そうしてある時、「踊る瞑想」というものに私は出会ったのです。
これはOSHOという覚者が考案した「活動的瞑想法(アクティブ・メディテーション)」というもの内の一つでした。
かつて進級制作展の舞台で即興舞踊をしてから時間も経っていたため、私の中でかつての恐怖も多少薄れていたのでしょう。
「一つこれをやってみるか」という風に私は思いました。
また、そこには同時に「かつて自由を前にして逃げた敗北感」を克服したい気持ちもあったかもしれません。
また、この「踊る瞑想」に出会うまで、私は坐ってする瞑想の技法をいくつか実践していました。
そして、それらの実践によって、思考が静まり、感情にも飲まれにくくなっていました。
そういったこともあり、「今ならあの恐怖とも向き合えるんじゃないか」と、その時の私は思ったわけです。
そして、「踊る瞑想」の実践が始まりました。
瞑想用に作られた音楽をかけ、私は「自由」に動いていきました。
そこには、昔のような恐怖はなく、私はかつてよりずっとリラックスして「自由」を表現できました。
でも、「何かが足りない」とも感じていました。
身体を動かすことに集中することで、確かに思考は静まりましたし、私は恐怖に飲まれることもありませんでしたけれど、同時に、内側では何も感じていなかったのです。
それゆえ、踊れば踊るほど、かえって虚しさが感じられてきてしまいました。
私の身体は動いていましたが、私の心は何も感じていなかったのです。
それは、あたかも「味のない料理」を食べ続けているような感覚でした。
咀嚼はしているのだけれど、そこには何の味わいもありません。
噛めば噛むほど、身体に疲労感だけが残っていき、心は虚無感でいっぱいになってしまったのです。
学生だった時の私にとって「自由」というのは「恐怖」でした。
だからこそ、私はそこから逃げ出したのです。
しかし、それから数年経った後の私にとって、「自由」とは「無味乾燥な虚無」でした。
私はもう「自由」を恐れてはいませんでしたが、それを感じ取ることはできなかったのです。
同時に、私は自分の感受性がほとんど死んでいることにも気づきました。
私は普段料理を食べている時に味をほとんど感じていませんでしたし、何かに触っている時も、その感触を意識したことがありませんでした。
また、当時の私の呼吸は浅く、自分の息さえ、私は満足に感じられなかったのです。
「自分の感覚は死んでいる」と気づいた私は、それから意識的に感覚を味わうトレーニングをし始めました。
料理を味わって食べるようにし、触るものは意識的に触るようにし、呼吸法を実践することで自分の息への感受性を徐々に高めていったのです。
◎「心のままに踊る」ということ
そんな実践が数年続きました。
また、そういった「感覚の養成」と並行して瞑想の実践もしていた私は、「『感覚を育てること』と『瞑想的であること』は実は同じことなのではないか」と感じ始めました。
というのも、当時の私はまだ、何らかの感覚や対象に意識を向ける「集中する瞑想」しか知らなかったからです。
そのため、「感覚を意識的に味わうこと」と「特定の感覚に集中すること」は同じことであるように当時の私には思えたわけですね。
それゆえ、私の中で「味わうこと」と「静かに内側へ向かうこと」は一つに重なっていきました。
そして、そうした実践を積み重ねていく中で、私はある時、「大きな気づき」を体験したのです。
それは、合気道の道場で指導されている呼吸法を家で実践している時のことでした。
いつもその技法を実践する時と同じように、私は呼吸のリズムに合わせて手を上下させる動きをしていました。
すると、その手の上下運動をしている中に、自分がある種の「喜び」を感じていることに私は気づいたのです。
それは、今にして思えば「アーナンダ(至福)の芽吹き」だったのかもしれません。
ともあれ、私は「ただ呼吸に合わせて手を上げ下げする」というだけの動きの中に、「確かな幸福感」を感じることができたのでした。
それから、私はもう一度即興舞踊をおこなうようになりました。
なにせ、ただ手を上げ下げするだけでも、そこに「喜び」を見いだせるのです。
だったら、踊ることに「喜び」を見いだせないことがあるでしょうか?
実際に踊ってみると、私はそこが「感覚の宝庫」であることを発見しました。
ただ床の上で足を滑らせるだけで、足裏に何とも言えない「愉快な感覚」が生じます。
手をゆったりと回していると、腕や手の甲に当たる空気の粒子が感じられてきて、思わず鳥肌が立ったほどです。
そして、そのまま腕を回し続けていると、次第に身体全体がその動きに巻き込まれ、私は思わず転んでしまいました。
それで私は、床に寝っ転がったまま、自分の心臓の鼓動に耳を傾け、自分の呼吸が全身を波のように伝わっていくのを感じていたのです。
私は初めて「自分の自由」を表現できたように感じました。
「これが自由の本当の味だったんだ」と私は思いました。
「どう動けばいいか」は、心と身体が教えてくれました。
心が言います。
「今度はこっちに行ってみたい」
そうすると、身体はそれと一緒になって動き出します。
動きが動きを生み、心は文字通り踊り続けていました。
「これが『自由に踊る』ということだったんだ」と私はようやくわかったのです。
桜井さんから「自由」という宿題を突き付けられて、既にその時は十年近くが経っていました。
桜井さんは、かつての私に「自由」というものの厳しさを教えてくれた人です。
ですが同時に、そこに在った「可能性」もまた、私は彼から教わったように思っています。
◎「オリジナリティ」は「こうとしか在れない」という自由な表現である
私たちの心は、いつも何かで縛られています。
それは特定の思考や感情だったりしますが、その奥には当人の固定観念や思い込みが隠れていたりするものです。
また、自我は絶えず当人を追い立て続けており、人は自身の承認欲求やコントロール欲求によって、いつも振り回されています。
このため、世の中の多くの人たちは、自分の心臓の鼓動や呼吸の波を、立ち止まって味わうことさえできません。
仮にもし「そうしよう」と思っても、たぶんほとんどの人には、そのやり方がわからないと思います。
これほど身近に在るものなのに、私たちは心臓や呼吸を知らないのです。
そうして私たちは、「行く先」もわからないまま毎日走り続けています。
そうやって必死になって走り続けることで、「内側に既に在るもの」を見落としてしまいます。
でも思い切って走ることをやめて立ち止まってみると、そこには「深い味わい」が広がっているものなのです。
ほんの5分でも構いません。
たった5分の間であっても、立ち止まって自分の呼吸を感じてみると、そこには「深い味わい」があります。
実際、瞑想には「固有の味」があるものです。
それは「自由が持っている味」です。
その「味」の中に抱かれる時、当人は迷いと疑いを捨てて、「自分の表現」を始めます。
その人は、自分の心(ハート)の鼓動に耳を澄ませ、身体を浸す呼吸のリズムにゆったりと意識を沈めるのです。
そこに恐れはなく、不安もありません。
その時、当人は「自由」そのものです。
しかし、この時に当人は「何をしてもいい」はずなのに、なぜか「こうとしか在れない」と感じ始めます。
それは踊りと一緒です。
実際、「手がどうしてもこっちに行きたがる」ということは、即興で踊っていると、しばしば起こります。
なぜそういうことが起こるのかは私にもわかりません。
しかし、なぜか心と身体は「こうとしか在れない」という道を進んでいくのです。
そしてそれは、「その人自身の自由」を表現していきます。
この時、当人は「自分自身」に定まっており、誰の真似もしていない「オリジナル」です。
きっと誰もが、内側にそんな「オリジナル」を抱えて生きているのだと、私自身は思っています。
◎「自覚された無垢」を抱きしめて生きていく覚悟
瞑想は、その人の心と身体を「自由」にします。
そして、いつかその「自由」が当人の中で十分に大きく育った時、その人は「自分だけの表現」を始めるはずです。
それは、「丁寧に料理をすること」かもしれませんし、「心のままに詩を書くこと」かもしれません。
あるいは、山に登ってその空気と一体になろうとする人もいるかもしれませんし、過去の私のように踊り始める人もいるかもしれません。
もちろん、「サット・チット・アーナンダ」を完全に理解しない限り、その「自由」は失われやすいとは思います。
実際、過去の私も、「自由」を一度完全に失いました。
でも、道はずっと続いています。
たとえ一度「自由」を失っても、また歩いていけば必ず取り戻せるのです。
それも、「前よりもずっと大きくて伸び伸びとした自由」へと、当人は辿り着くでしょう。
なので、私は読者の皆さんに「悟ってほしい」とはあまり思いません。
ただ、「自由であってほしい」と思っています。
そういった「自由」は、別に「最終的な悟り」に至らなくても感じることができます。
そもそも「自由」がどんなものであるかは、子どもたちだって知っています。
たとえば、まだ学校にも上がっていない幼い子どもは、「自由に絵を描いていいよ」と言われると、目をキラキラさせて伸び伸びした絵を描くことがあります。
そうした絵の持っている生命力や迫力には、時に大人さえビックリするほどです。
しかし、やがて学校に上がるようになると、ほとんどの子どもたちが「自由の味」を忘れていきます。
なぜなら、「他のクラスメイトや教師からどう見られるか」ということを気にする「自意識」が育ち始めるからです。
探求の道とは、もう一度「無垢」を取り戻すことに他なりません。
しかしそれは、「幼い子どもの無垢」のように、弱くて壊れやすいものではなく、「丈夫でたくましい無垢」です。
実際、探求者は瞑想の実践の中で、自身の「自意識」と闘います。
それがどれほど多くの恐れに満ちているか、そして、どれほど多くの不安を抱えているかを探求者は真正面から見るのです。
すると、やがてそうした恐れや不安は溶けて消えていきます。
そうして後には、「冷徹なまでに覚めた無垢」が残るでしょう。
その時、当人は再び「無垢」になります。
しかし同時に「自分の無垢」をその人は自覚しています。
幼子は「自分の無垢」に気づくことがありませんが、探求者は自覚的に「無垢」に留まるのです。
だからこそ、探求者は「自分の無垢」が失われそうになると、すぐに気づきます。
内側に虚栄心や自己顕示欲が起こった時、コントロール欲求や快楽への依存が生じた時、探求者は「無垢が失われようとしている」と気づいて立ち止まることができるのです。
自分で自分を束縛した時、「無垢」は再び失われ、当人は「不自由」になっていきます。
それが、仏教で言うところの「無明」です。
その時、当人は「物事のありのままの姿」が見えなくなっています。
このような状態の中で当人に見えるのは、ただ「自分の苦しみ」だけなのです。
もう一度言います。
どうか「自由」であってください。
その「種」は既にあなたの中に在り、あなたから水を注いでもらえるのを待っています。
もしどうしたらいいかわからなくなったら、無理に何かをしようとしなくていいのです。
ただ立ち止まって、たった5分だけ、自分の心(ハート)の鼓動と呼吸のリズムに、静かに耳を傾けてください。
最後に、桜井さんからかつて言われた言葉を送ろうと思います。
「内側から動きが起こってくるまでは、無理に動こうとしなくていいんだよ」
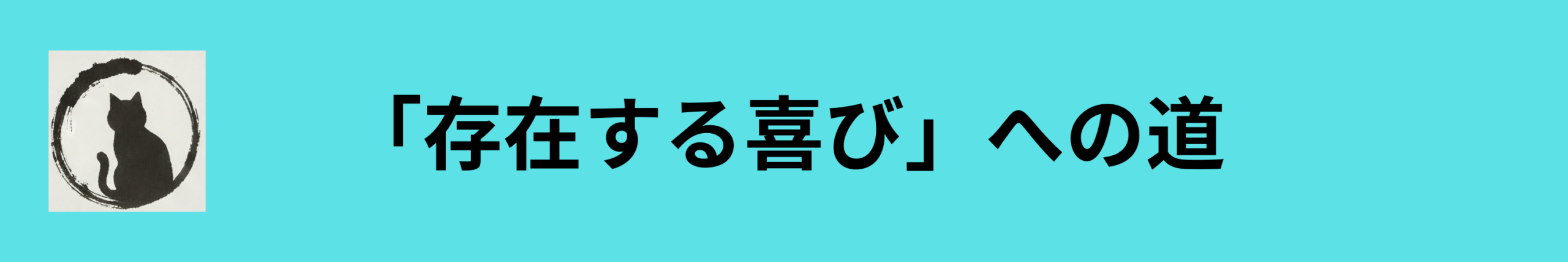

コメント