かつて、池田晶子さんという哲学者がいました。
もう亡くなられてしまったのですが、彼女は「哲学エッセイ」というジャンルを作った草分け的存在と言われています。
そんな池田さんは、ある著書の中で「道徳」と「倫理」という言葉について、自分の中で明確に使い分けをしていたことを明かしています。
池田さんにとって「道徳」とは、「あれをしなさい」とか「これをしてはいけません」とかいった形で教えられる「外なる規範」です。
それに対して、「倫理」というのは、「当人が『したい』と思ったことをして、『したくない』と思ったことをしない」という形で表現されるような、「内なる規範」であるとしています。
つまり、池田さんにとって「道徳」というのは「外なる規範」で、「倫理」というのは「内なる規範」であるということです。
道徳教育の先生だとか、倫理学の学者の人がどう言うかは知りませんが、少なくともこれが池田さんにとっての「道徳」と「倫理」の定義なわけです。
そして池田さんは「『道徳』ならいくらでも教えることができるが、『倫理』は教えることができない」と考えていました。
だからこそ、「もしも『倫理的』であろうと思ったら、教えられた『道徳』を守って思考停止するのではなく、自分自身で考えることが必要だ」と、池田さんは感じていたようです。
「善とは何か?」
「悪とは何か?」
「なぜ人を殺してはいけないのか?」
もちろん、池田さん自身も「答え」は知りません。
ですが、「答え」を知らないからこそ、池田さんは考え続けます。
そして、そんな風にして「ただどこまでも考え続ける」という姿勢を目の前で示して見せることによって、多くの読者が「自分も本当は『答え』を知らなかった」ということに気づき、自分自身で考え始めたわけなのです。
ただ、今回の記事で私は、池田さんとはちょっと違ったアプローチで「道徳」と「倫理」について考えてみたいと思います。
それは、「探求者にとって『倫理的』とはどういうことか?」というものです。
「道徳」が「外なる規範」で、「倫理」が「内なる規範」であるという池田さんの定義をお借りしつつ、私は私なりに仕方で、「道徳」と「倫理」について切り込んでみたいと思います。
ただし、先に言っておきますが、私も「答え」は知りません。
あくまでも、「池田さんとはアプローチの仕方が違う」というだけで、「こうすることこそが『倫理的』なのだ」と明確に示すことができるわけではないのです。
しかしそれでも、「善とはいったい何なのだろう?」と考えたことのある人や、「自分はいかに生きるべきなのか?」と思って悩んだ経験のある人には、何かしらの「考えるヒント」が提示できるかもしれません。
それに、探求者の中にも、「探求を進めていった結果、『反社会的な人格』になってしまったらどうしよう…」と思って心配している人がいるかもしれません。
実際には、探求が進んでいくことによって、当人は「社会的」でも「反社会的」でもなくなって、ただ「その人らしく」なっていくのですが、それは別にそんなに「危険」なことではなかったりします。
そのあたりの事情についても、今回の記事を読んでもらえればわかっていただけるのではないかと思います。
ということで、今回も前置きが長くなってしまいましたが、話に入っていきましょう。
では、始めます。
◎人の本性は「善」なのか?それとも、人はもともと「悪」なのか?
先ほども書きましたが、もう一度、今回の記事における「道徳」と「倫理」の定義を確認しておきましょう。
「道徳」とは「あれをしなさい」「これをしてはいけません」という形で教えられる「外なる規範」です。
対して、「当人が『したい』と思ったことをして、『したくない』と思ったことをしない」という形で表現されるような、「内なる規範」が「倫理」になります。
しかし、多くの人は、「『したいこと』をして、『したくないこと』をしないのでは、みんな好き放題に生きるようになって、社会は崩壊してしまう」と考えて、これを危惧するではないかと思います。
「それのいったいどこが『倫理的』なんだ?」と疑問に思うわけです。
確かに、もしも法律がなくなったら、犯罪を犯す人は増えるでしょう。
潜在的に「できれば犯罪を犯したい」と思っている人は世の中にかなりいるでしょうし、もし「刑罰」というストッパーがなくなったら、そういう人たちはためらうことなく他人を傷つけるかもしれません。
ですので、「現状の社会において、いきなり全ての人が『倫理的』に生きることは難しい」と私自身は思っています。
実際、もしも「外側からの強制」を全部なくしてしまったら、私たちの社会はたぶんそう長くは持たないでしょう。
そう考えると、「人間というのはもともと『悪い存在』なのだ」という風に感じる人もいるかもしれません。
でも、人によっては「いやいや、人間というのはそんなに『悪いもの』でもないんじゃないの?」と考えることもあります。
よく議論される「性善説」と「性悪説」の対立ですね。
実際、「性善説」と「性悪説」は、古来より併存してきました。
「人は生まれながらに『善』なのか?」
「それとも、人はもともと『悪』なのか?」
このことについては、未だに決着がついていません。
私自身の感覚でいうと、論者自身の経験から、「性善説」を取るか「性悪説」を取るかが変わってくるように思います。
たとえば、「幼い頃に誰かから親切にしてもらった」とか、「人が自ずから人格的な成長を遂げる過程を見た」とかいった経験を持っている人は、「性善説」を信じているように感じます。
反対に、「犯罪者とかかわることが多かった」とか、「人類が犯した残虐行為の歴史について深く学んだ」とかいった人は、「性悪説」を取る傾向が強まるでしょう。
ちなみに、私自身はどちらの説が正しいとも思っていません。
ただ、探求の過程で「道徳」と「不道徳」の両方から自由になった時、当人は「その人自身」になっていくだろうと私は思っています。
つまり、探求の果てに社会的に「善」とされることを為すのか、それとも社会的に「悪」とされていることを為すのかは、その人が本来的に「どういう人であったのか」にかかっていると思うのです。
【関連記事】
「善」と「悪」の鎖を断ち切る方法|「無分別」に至るために「事実」に留まることの意味
いずれにせよ、世の中の多くの人は、「道徳」によって縛られています。
実際、世の中のほとんどの人は、「これをしなければいけない」「あれをしてはいけない」という風に、個人個人が内側に「ルール」を持っていて、無意識にそれに従っているものです。
しかしそれは、「純粋な内的動機」に裏付けられた「倫理」とは違います。
それらの「ルール」の起源はあくまでも、当人の「外側」にあるものなのです。
◎人が自律的に考え始めるためには、一度「反抗」を通り抜けねばならない
たとえば、幼い頃から「女の子はおしとやかでないといけません」と絶えず言われて育った子どもは、だいたい二パターンの成長を遂げます。
一つは、「常におしとやかに振る舞わねばならない」という観念に縛られて、そこから外れる言動を取ることができなくなるパターンです。
彼女は「常におしとやかであること」という「ルール」を内面化しており、たとえば、友達と街で夜遊びしたり、漫画を読んで笑い転げたりすることはありません。
たとえ「そういうことを一度してみたい」と内心では思っていても、無意識にブレーキを踏んでしまってできないのです。
もう一つの成長パターンは、「教えられたこと」に思いきり反抗する場合です。
この場合、「上品さなんてクソっくらえだ!」と言わんばかりに、いわゆる「非行」に走ったりします。
親や教師から言われたことに反発し、場合によっては、犯罪すれすれのことをするかもしれません。
しかし、だからといって、当人はそういった「非行をしたい」と思っているわけではなかったりします。
当人はただ、「何かを押し付けられること」に対して「ノー」を突き付けたいだけであって、その際の表現方法が、たまたま「非行」だっただけに過ぎません。
つまり、「非行」そのものを欲求しているわけではなく、あくまで「非行」という表現方法によって、「嫌だ!」と主張しているだけなのです。
これは、多くの人に経験があるのではないかと思います。
私たちが何かに対して反抗する時、私たちは往々にして、別に「自分が本当にやりたいこと」がわかっているわけではありません。
私たちが親や社会に反抗する時というのは、「自分はどうしてもこれがやりたい。だからどうかそれを思う存分やらせてほしい」とは言うことは少なくて、「なんだかわからないけど、とにかく言われた通りにしたくない。だから自分は逆らうんだ!」と内心では思っているわけです。
こういう場合、当人にとっての「本当にやりたいこと」というのは、だいたいにおいて、そうやって「ノー」を突き付けた後でだんだんとわかってくるものです。
つまり、私たちが「自分が本当にやりたいこと」を自覚していく場合には、まず「やりたくないこと」を列挙するところから、探索を始めていくのです。
「あれも嫌!」「これも嫌!」と言って「したくないこと」を除去していった後になって、やっと私たちは落ち着いて「じゃあ、自分が本当にしたかったことって何だったのだろう?」と自問することができます。
自分自身で自律的に考えるためには、「盲目的に従うこと」からなんとかして抜け出さないといけません。
そして、そのためにこそ、「反抗すること」が一時的に必要となるのです。
このような「自律的思考」に至る前までは、「あれをしなさい」と言われて従うか、「そんなの嫌だ!」と言って逆らうか、二つに一つの状態です。
つまり、従うか逆らうかしか当人は選ぶことができません。
ですが、「反抗」を一度経ることによって、当人はやっと「本当のところ、自分は何がしたかったのだろう?」と落ち着いて自問することができるようになります。
そうして考えに考えた結果として、当人は最終的に「かつて言われたとおりしよう」と思うようになるかもしれません。
これは、「いろいろ考えてみたけれど、確かに親や教師から言われたことは正しかったな」と結論付けた場合ですね。
この場合、当人の表面的な振る舞いは、確かに「道徳的なもの」になりますが、実際のところ、その動機は「外側」ではなく「内側」にあります。
当人は、もう「誰かに言われたから」という理由でそのように振る舞っているわけではなく、あくまでも「自分でそうする」と決めた上で、あえてその振る舞いを選んでいるのです。
また、自分自身で考えてみた結果として、当人は「全く新しい方向性」に進んでいくようになるかもしれません。
それは外見上は親や教師に対して逆らっているかのように見えます。
なぜなら、決して「言われたこと」を守っているわけではないからです。
しかし、当人の中には、別に「反抗しよう」という意図はありません。
あえて逆らっているわけではなく、当人はあくまでも自分で「こうしたい」と思った道に進んでいっているだけなのです。
◎「自律的に考えること」に絶えず干渉してくる「自我」の機能
このように、私たちは最初、まず「道徳」を外から教え込まれます。
そして、成長する過程で徐々にそれが「内面化」していきます。
あたかも、それを自分自身で望んで守っているかのように、かつて教えられたことを、私たちは「重要なルール」として内に抱え込むようになっていくわけです。
しかし、それに従っているばかりだと、窮屈に感じる人もいます。
そういった人たちは、かつて押し付けられた「道徳」に反抗しようと試みます。
彼らは表面的には「不道徳」なように見えますが、実際のところ、「不道徳なこと」がしたいわけではありません。
彼らはただ、「外側」からあれこれ押し付けれらたくないだけだったりします。
そして、「外側」から押し付けられたものを拒否した後に、当人はじっくり考えます。
「自分は本当のところ、どう生きたいのだろう?」と自問して、納得するまで考えるのです。
そのようにして出した答えは、「外側から押し付けられたもの」ではなく、あくまで「自律的に導き出したもの」です。
それゆえ、当人はその「自分の答え」に従っていても「束縛されている」とは感じませんし、それに対して「反抗しよう」とも考えません。
つまり、この段階まで到達することで、人はやっと「道徳的」ではなく「倫理的」に生きることができるようになるということです。
ただ、これは「自分にとっての『善』とは何か?」ということの「答え」について、あくまでも「考えること」によって近づこうとするアプローチです。
確かに、多くの人はこのアプローチによって「自律的な人間」へと成長していきますが、それはけっこう難しいことだったりします。
なぜなら、どうしても途中で「自我(エゴ)」が当人の思考に介入してくるからです。
私の書いた文章をいくつか読まれた方は、私が「『自我』の言うことを真に受けないように」と口酸っぱく繰り返していることを、既にご存じかもしれません。
実際、「自我」の言うことに従っていると、私たちは自分を見失い、道に迷って消耗していきます。
「自我」はいつも「もっと成功を追い求めろ」とか、「金銭や名声を手に入れろ」とか言うことで私たちのことを追い立て続けますが、実は「道徳」によって私たちを縛っているものも「自我」だったりします。
たとえば、親や教師から「優しい人にならないといけません」と言われ続けた人が大人になると、「人には優しくしないといけない」という観念によって当人は縛られるようになっていくことが多いです。
こういった場合、当人の中には「自分は優しい人間でなければならない」という観念があり、「自我」がそれをいつも管理しています。
それゆえ、もしも当人の「心」に「残虐な思考」や「他者への憎悪」が現れそうになると、「自我」はそれを検閲して、「出てくるな!」と言って無意識の奥へと抑圧するのです。
その結果、当人の「心」の奥底には「残虐な思考」や「他者への憎悪」が存在し続けることになりますが、当人はそれらを自覚することができなくなります。
そして、もしもそれらの「抑圧された思考や感情」が表に現れそうになると、当人は「苦しみ」を感じて、まともに物を考えることができなくなってしまうのです。
このように、「自我」は絶えず「私たちが何を感じ何を考えるか」ということに対して干渉してきます。
それゆえ、私たちは往々にして「自由に考える」ということができず、「自我にとって都合のいいこと」だけを考えて、「自我にとって都合の悪いこと」はそもそも考えることができません。
その結果、「自分の本当にしたいことは何だろう?」と自問しようとする際にも、私たちの思考は「自我」によって絶えず阻害されることになってしまうのです。
◎「自我」が浄化され始めると、人は「葛藤」を感じるようになる
こういった事情があるため、探求者は「考える」ということをあまり重視しません。
そうではなくて、探求者はまず「自我を浄化すること」を優先します。
そもそも、思考や感情を歪めている元凶は「自我」なので、何かをじっくり考えようとする前に、まず「自我」が一人で暴走している状態のほうを先に終わらせようとするわけです。
実際、瞑想などの実践を重ねていくと、「自我」は徐々に大人しくなっていきます。
最初は「自我」が絶えず「心」に浮かぶ思考や感情を検閲していたところから、次第に抑圧が解けていって、それまで抑えつけられていた思考や感情が一つずつ解放され始めるのです。
もちろん、長いこと抑圧していた思考や感情は、「どうして自分を押し込めたんだ!」と言って大暴れするでしょう。
そういった場合の対処法については、過去にいくつか記事を書いたので、気になる人は読んでみてください。
【自分の呼吸を感じられない人へ】感覚を深め、感情を解放する二つのステップ
「怒り」は探求のための燃料になる|「怒り」を罪悪視せず、「自己理解の力」へと変える方法論
ともあれ、「自我」による支配が緩まることで、徐々に「心」は自由を獲得していきます。
そうして思考や感情が抑圧されることがなくなることで、「自我にとって都合の悪いこと」も感じたり考えたりできるようになっていくわけです。
ですが、そうなると探求者は一時的に「分離感」を感じるようになります。
それは、「自我」と「心」の間で生じる「分離感」です。
ここにおいて「自我」は、多少は力が弱まったと言っても、まだ主張を続けています。
そして、「心」に向かって「そんなことを考えるんじゃない」と注文をつけてくることがあります。
たとえば、さっき上で書いた例で言うと、「自我」は「常に優しく在らねばならない」と思っていて、「心」は「ムカつく上司を蹴り飛ばしたい」と思っていたりします。
すると、「お前はそんな人間ではないはずだ。そのようなことを考えてはいけない」と、「自我」は「心」に言ってくるわけです。
そうは言っても、「心」からしたら、思ってしまうものは仕方がありません。
「だって、自分としては本心からそう思うんだもの」と「心」の側は言うわけです。
ここにおいて、「自我」と「心」の間で対立が起こります。
「自我」による「独裁」は終わったものの、まだ「自我」と「心」が完全に足並みを合わせているわけではないのです。
この状態は、心理学や精神医学において「葛藤」と呼ばれているものです。
それは、「自我」で考える「こうすべき」という命令と、「心」で感じている「こうしたい」という欲求とか、お互いに矛盾している状態です。
ちなみに、心理学や精神医学においては、この「葛藤」を「健全な状態」であるとしているようです。
なぜなら、「自我」による抑圧が弱まって、「自由な思考と感情」が無意識から意識へと上がってこれるようになっているからです。
確かにそれは、思考や感情を無理やり抑圧している状態よりも、ずっと「健全」な在り方ではあります。
しかし、当人はまだ「微妙な分離感」を感じ続けています。
内側で「自我」と「心」の対立は続いており、全てがすっかり片付いたわけではないのです。
◎探求者は「葛藤」を超えていき、「ハートの感覚」へと至りつく
「自我」がいくらか大人しくなったとしても、「分離感」はまだ残っています。
それゆえ、探求者はここを「ゴール」とは考えません。
なぜなら、「分離感」が残っているということは、「まだ自分は束縛されている」ということだからです。
実際、探求者はさらに実践を続けていきます。
そして、探求がもっと進んでいくと、徐々に「自我」と「心」の足並みがそろってくるのです。
その鍵となるのは、探求の世界で「アーナンダ(至福)」と呼ばれている「無根拠な幸福感」の体験です。
たとえば、瞑想などの実践を続けていると、どこかの段階で探求者は「完全な静寂」に辿り着きます。
そこにはいかなる思考も感情もなく、いつもは口うるさい「自我」さえもが沈黙を守って消えています。
そして、そのような何もない「空(くう)」の中で、当人はなぜか「穏やかな心地よさ」を感じ始めます。
ずっと縛られていたものから解き放たれたかのような「解放感」が、そこにはあります。
それは胸のあたりに感じられるので「ハートの感覚」とも呼ばれるのですが、これを感じるようになると、徐々に「自我」と「心」の足並みがそろっていくことになります。
というのも、「ハートの感覚」の心地よさを「自我」が徐々に学習して受け入れるようになっていくからです。
最初、「自我」は「ハートの感覚」を認めようとしません。
なぜなら、「ハートの感覚」は何もしなくても無条件に感じることができるのに対して、「自我」は「何かをしたことの結果として感じることのできる喜び」しか知らないからです。
実際、「自我」は「ハードル競争」が大好きです。
自分で目の前に「達成困難な課題」を作り、それを実際に飛び越えることで「達成感」を得ようとします。
「自我」は絶えず進路上に「ハードル」を置き続け、そうして自分で置いた「ハードル」を、自分で超えることでしか「幸福」を感じることができないのです。
このように、「自我が知っている喜び」というのは、基本的に「達成感」だけです。
それは常に何かを成し遂げなければ手に入りません。
そして、「自我」はそのようにして「幸福」を感じるパターンに慣れ切っています。
それゆえ、「ハートの感覚」のように、「何もしなくても無条件に感じられる喜び」というものが、「自我」にはさっぱり理解できないのです。
しかし、もしも当人が自覚的に「ハートの感覚」に留まり続けるなら、月日が経つにしたがって、「自我」もその心地よさを学習していきます。
そうしてやがては、「何も達成しなくてもこんなに心地よいのであれば、別に何も成し遂げなくていいじゃないか」と、「自我」自身が考えるようになっていくのです。
ここに至った時、「自我」と「心」の足並みはほぼ一致します。
もちろん、その時々によって「自我」が優勢になることもあれば、「心」が優勢になることもあるでしょう。
ですが、両者の対立はほとんど解消されてしまいます。
この時、「心」が「したい」と思うことは、「自我」にとっても「すべきこと」となり、「心」が「したくない」と思うことは、「自我」にとっても「すべきでないこと」になっていくのです。
◎「倫理」を決めるのは、自分の胸に宿る「ハートの感覚」の生滅である
ちなみに、その際の判断基準は、「ハートの感覚を失うかどうか」です。
たとえば、もしもあることをした際に、それでも「ハートの感覚」に留まることができるのであれば、それは「心」にとって「したいこと」であると同時に、「自我」にとっても「すべきこと」です。
反対に、もしもそれをすることによって「ハートの感覚」が感じられなくなるようであれば、それは「心」にとって「したくないこと」であり、「自我」にとっても「すべきでないこと」になります。
つまり、「ハートの感覚が持続すること」が当人にとっては「善」となり、「ハートの感覚を失うこと」は当人にとって「悪」となるのです。
その判断基準は完全に「内側」にあり、当人は決して「外的な規範」に従っているわけではありません。
だからこそ当人は「外側の条件」から自由であり、「自我」と「心」の対立が解消しているからこそ、「葛藤」することもないのです。
また、私自身の経験からいうと、この状態に至った場合、人は自然と「利他的」になっていく傾向があるように思います。
なぜなら、当人は「ハートの感覚」に留まることによって、既に「自我」と「心」が満たされているからです。
世の中の人々がなかなか他人に優しくできないのは、実のところ、「自分自身」が十分に満たされていないからだったりします。
実際、自分のお腹が空いている時に、進んで他人に食べ物を譲ることは難しいでしょう。
もしも自分が満たされていないにもかかわらず、他人を満たそうとし始めると、それはどうしても「偽善的な形」を取りがちです。
そういう時、当人はあくまで「我慢」して「利他的行為」をおこなっており、「心」の底では見返りを期待してしまいます。
つまり、自分自身が現に満たされていないなら、当人は「見返りを期待せずに与える」ということができないのです。
それに対して、「ハートの感覚」を知っている人は、「何もしなくても自分は既に幸福だ」と知っています。
それゆえ、他人に何かを与える際も、見返りを期待せず、惜しげもなく与えることができます。
そして、自分自身がもはや「苦しみ」の中にいないがゆえに、「他人の苦しみ」がよく見えるようにもなるものです。
それゆえ、当人は「どうしたらこの人たちの苦しみを取り除けるだろう?」という風に、自然と考えるようにもなっていくのです。
それらの行為は確かに「利他的」なものではありますが、それを当人に強制する人は誰もいません。
つまり、「ハートの感覚」に根付いた人がおこなう「利他的な行為」というのは、あくまでも当人が自分で「そうしたい」と思ってしているだけなのです。
そういう意味で、「ハートの感覚」に根付いている人がおこなう「利他的な行為」は、あくまでも「自分自身が満たされていること」から生じる「副産物」です。
言い換えれば、「利他」は「自身の幸福」が溢れたことによって出来上がった、「余剰生産物」であるということです。
つまり、当人にとっては別に「利他的であること」が目的であるというわけではなくて、「自分をハートの感覚で満たすこと」を突き詰めていった結果として、「他人にも与えられるもの」が余ってできてしまっただけだということです。
◎「内側の無根拠な幸福感」が、人を真に「倫理的」にする
このような状態にある人のことを、「倫理的」と言うのではないかと私は思っています。
もちろん、「自分にとって倫理的とはどういうことか?」と考えることにも意味はあると思います。
ですが、先ほども言いましたように、「自我」による問題を解消する前に考えようとしても、当人はまともに考えることができません。
なぜなら、「自我」が絶えず当人の思考と感情を検閲し、それらを操作しようとするからです。
この状態に留まっている限り、「自律的に思考すること」は常に妨げられてしまいます。
そして、もし「自我」による支配が弱まってきても、「自我」と「心」の対立が解消していないと、「自我の声」と「心の声」との間で、当人は「分離感」に苦しみ続けます。
なので、もし「倫理的」であろうと思うなら、まず「自我」をどうにかするほうが優先事項であり、「倫理とは何か?」について考えるのは、その後のほうがいいのではないかと、私自身は思うのです。
そして、最終的に「利他」は「考えることでおこなうもの」ではなくなっていきます。
それはただ、当人の「自我」と「心」が「そうしたい」と感じることでおこなわれていきます。
しかし、そんな風に自分から望んで「利他」をおこなえる人は、「現に自分自身が深く満たされている人」だけです。
なぜなら、自分自身が満たされていないと、人は表面上は他者に与えているように見えたとしても、深いところでは相手から「与えた以上のお返し」を期待することをやめられないからです。
そして、自分自身を真に満たすためには、人は自分の胸に生じる「何の条件もいらない無根拠な幸福感」を知っている必要があると、私は思うのです。
◎「他人を救おう」と思うなら、まず自分自身を救うこと
いかがでしたでしょうか?
今回は「『哲学的な話』から入って、最終的には『探求の必要性』へと引っ張っていく」という、いささか「我田引水」な展開になってしまいましたが、私は本当にそう思っています。
実際、「哲学的な省察」だけでは、「自我」に干渉されてしまって、「心」にとっての「したいこと」がわからない人も多いと思います。
そして、そういう人は結局、探求の道を歩まないと「自分の答え」には辿り着けないのではないかとも思っています。
いずれにせよ、本当の意味で他人を助けることができるのは、「自分自身を既に救うことができた人」だけです。
つまり、自分で自分を救って初めて、「他人の支え」になることができるということです。
逆に、自分自身が救われていないと、私たちはどうしても他人に寄りかかることになってしまいがちです。
だからこそ、覚者は「世界を救おうとする前に、まず自分自身を救いなさい」と言うのでしょう。
それは、「そもそも『世界』というものは、あなたが創り出した幻だ」という意味もありますが、「自分を救っていないなら、他人を助けることはできない」という意味もまた、そこには含まれているのではないかと、私は思っています。
「人助けをしたい!」という想いに胸を焼かれている人には、冷や水を浴びせる形になってしまったかもしれません。
ですが、「他人を本当に救いたいなら、まず自分自身をどうにかするほうが先だと思うよ」と、私はやっぱり言いたくなってしまうのです。
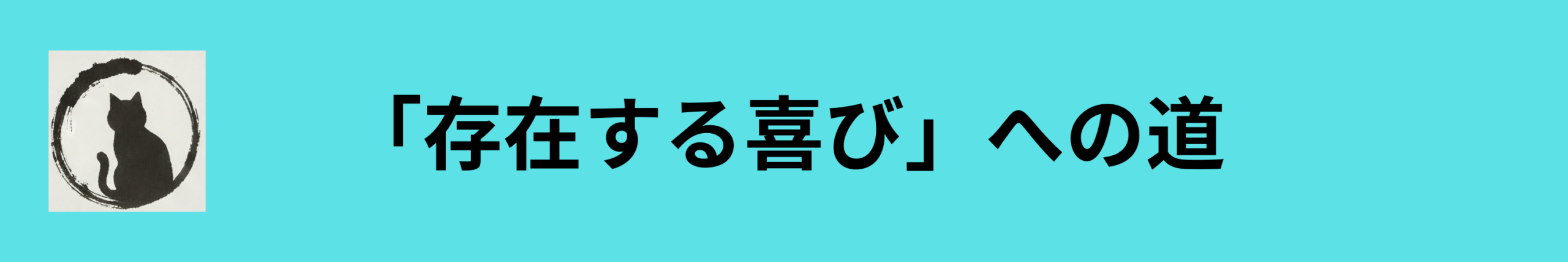

コメント