私は文章を書く時は、基本的に何も考えないことにしています。
多くの人は、文章を書くことを「考えること」だと思っているでしょうけれど、私にとっては違うのです。
言葉は「向こう」から勝手にやってきます。
それは私に意図してコントロールすることのできないものです。
だから、私にできることは、ただ浮かんでくる言葉を、消えないうちに書き写すことだけなんです。
私が初めて「向こう側」を知ったのは、中学二年の夏のことでした。
その時、時刻は朝の五時頃で、私は夏休みの宿題である作文の課題をしようとしていました。
書く題材についてだけは「部活の大会のことにしよう」と決めていたのですが、どう書き始めたらいいものかわからなかった私は、まっさらな原稿用紙を前にそのままジッとしていました。
すると、不思議な感覚がしてきました。
急に、頭蓋骨の内側に文字が彫り込まれるような感覚がしてきて、「書くべき言葉」が浮んできたのです。
私は驚きながらも、とにかくそれが消えてしまわないうちに、必死で手を動かして、「向こう側からきた言葉」を原稿用紙の上に書き留めていきました。
そして、私が一つ文章を書くごとに「次に書くべきこと」が浮んでくるので、私はまた、「これが消えないうちに書かないと!」と思って、なんとかそれを文字して残していったのでした。
そうこうするうちに、作文はどんどん長くなっていき、ある瞬間に「直観的なビジョン」のようなものが見えました。
突然、作文の結末のようなものが「観えた」のです。
そして、あれよあれよという間に「物語」は動いていき、さきほど観た「ビジョン」の通りに結末を迎えて、その作文は終わりました。
「言葉の湧出」が止まった時、私は不思議な静寂の中にいました。
そこには、「いいものが書けた」という手応えもなく、「苦労して書いた」という疲労感もありませんでした。
ただただ「透明」でした。
そして、私は夏休み明けにその作文を学校に提出したのですが、後日、私は担当の国語教師から呼び出しを受けました。
「いったい何の用事だろう?」と思っていたら、私の出した作文の出来が非常に良かったらしく、「コンクールに出そうと思うがいいか?」ということの確認でした。
私は自分の作文に何の手応えも感じていなかったので、それが「良い作品」なのかどうか、まるでわかりませんでした。
そもそも、私は「向こう」から勝手にやってくる言葉を必死で書き留めていただけであり、それゆえ、私はそれを「自分で書いた」ともうまく思えなかったのです。
だから、私はまるで「他人の作品」を提出するみたいでちょっと気が引けたのですけれど、コンクールへの出品を許可しました。
すると、私の書いたその作文は、東京都近県作文コンクールで一等一席を取ってしまったのです。
「一等一席」ということは、ただの一等ではありません。
これは、「一等として選ばれるような作品の中でも、特に優れていた」ということです。
教師は大喜びし、両親も鼻を高くして私を誉めました。
そして、国語教師からもらった冊子には、私の書いた作文のことをいろいろと論評している大学の教授たちの論考がたくさん載っていたのですが、私にはそこで書かれていることが難しすぎて、まるで理解できませんでした。
私はあたかも「台風の中心」にいるみたいに静かな心境でした。
周りは大騒ぎしているのに、当の私は「あれの何がそんなにすごかったんだ?」と不思議でならなかったのです。
しかし、そうやって周りに持ち上げられるうちに、私はだんだんと「勘違い」をしていきました。
「あの作文を書いたのは自分であり、その功績は自分のものだ」と考え始めたんですね。
そして、「自分には他の人にはない『特別な能力』が在る。きっと自分は『選ばれた人間』に違いない」とまで、私は考え出したのです。
もっとずっと後になってからわかったのですが、「向こう側」から言葉を受け取るのには条件があって、その条件とは「当人が『無私』の状態である」ということでした。
実際、「自分のことを認めさせよう」とか、「自分の能力を誇示しよう」とかいったことを考えていると、「向こう側」は言葉を送ってくれません。
それゆえ、当人は必然的に、自力で考えないと書けなくなります。
自分自身で「うんうん」唸って言葉を絞り出し、「こうかもしれない、ああかもしれない」という迷いに囚われ、「こんなこと書いたら笑われないかな?」と自意識にちょっかいを出されながら、当人は「頑張って」書かねばなりません。
だから、そこには「当人が力いっぱい思考した跡」は残るのですけれど、そうして力んで書いた文章には、「透明な感じ」はないものです。
そこに埋め込まれている「書き手のエゴ」が、「濁り」となって紙面に滲んでしまうからです。
もちろん、そういう「エゴ」にこそ「独特の味」を感じる人もいますから、それはそれでファンがつくこともあるでしょう。
でも、そのようなやり方を続けると、すぐ言葉が涸渇してしまいます。
なぜなら、毎回ゼロから自力で考えないといけないからです。
私は、書くという行為は基本的に「他力」だと思っています。
たとえば、道元禅師は『正法眼蔵』の中で、「自己を忘れるというのは、万法によって証せられることだ」と書いています。
この言葉の意味は、「人が『無私』になった時には、『全てのもの』がその人に『真理』を悟らせてくれる」ということです。
逆に、自分で「悟ろう」と思っていると、「エゴ」がつっかえてしまって、うまく「万法」とつながることができません。
しかし、もしも「悟ろう」という「エゴ」を落として「無私」になると、「悟り」は「向こう」からやってきて、勝手に私は「悟らされる」のです。
そして、道元禅師はその後に「万法によって証せられるというのは、自己と他己の心身を脱落させることだ」と書いています。
これは要するに、「もしも『全てによって悟らされる在り方』を体現するならば、その人は自分と他人を『自由』にするだろう」ということです。
そして、実際にその通りなのです。
「無私の人」が取る一挙手一投足は、瞬間ごとに「新しい悟り」を表現し、自分だけでなく、周りの人のことまで「自由」にします。
「向こう側からやって来る悟り」が、自分と他人に「自由の味」を思い出させるんです。
たぶん、過去の私の作文が一等になったのはそのためです。
私はそんなつもりもないまま、多くの読み手の心を「自由」にしたのでしょう。
それは、たまたまその時の私の心が「自由」だったことが原因です。
実際、その時の私の中には、何の力みもありませんでした。
「良いものを書こう」とも思っていませんでしたし、「バカにされないように書かないと」とも思っていませんでした。
当時の私は、そんなに成績が優秀なわけでもなかったですし、誰も私に期待していなければ、私も別に「見返してやろう」とは思っていなかったのです。
だからこそ、結果的に言葉は「向こう」からやってきてくれました。
私は「向こう側」によって悟らされ、自分と他人を「自由」にすることができたのです。
しかし、先ほども書きましたように、私は徐々に「勘違い」をしていきました。
つまり、「自分は『特別な力』を持った人間だ」と考え始めたのですね。
こうなるともう悲惨です。
翌年の夏休みも、同じように作文の宿題が出されましたが、もはや言葉は出てきませんでした。
でも、親も教師も私がまた「立派なもの」を書くだろうと期待してかかっていました。
そして、当の私自身も周りの期待がプレッシャーになり、「下手なものを書いてガッカリされたらどうしよう?」という恐怖が湧いてきて、書く手が震えてきてしまったのです。
一年前はまだ何も「持って」いなかったので、私は「手ぶら」で書くことができました。
しかし、その時の私は、もうすっかり「多くの荷物」を背負ってしまっていたわけです。
その時の私は、「守らないといけないもの」をたくさん抱え込み、悪戦苦闘しながら文章をひねり出しました。
要するに、自力で考えて書いたのです。
執筆は難航し、進んでは戻り、脇道に逸れては引き戻すことを繰り返しました。
書いていてもずっと苦しいばかりで、一年前に経験した、あの「『何かの流れ』が自分を通り抜けていく快さ」はまるでありませんでした。
それでも、私は苦心の末に、とりあえず一本の作文を書きあげました。
それは確かに「自分で書いたもの」でしたけれど、私はそれを「他人のもの」にしたいくらいでした。
その出来は、たぶんひどかったと思います。
なにせ、書いていた私自身が、息を詰めて、苦しみながら書いていたのです。
だから、きっと読んだ人たちの息も詰まったはずです。
国語の教師も、今回は手放しでは誉めませんでした。
かといって、前年の実績がある手前、酷評するわけにも行かず、奥歯に物が挟まったような曖昧な言い方で私のことを誉めました。
結果的に、その年の私の作文は、コンクールで二等になりました。
でも、私にはわかっていました。
あの作文に二等になるだけの価値はなかった、と。
おそらく、前年の私の作文を読んだ人たちの先入観が働いて、審査が甘くなったのでしょう。
「なんだかひどいものに見えるけど、去年のあの子が書いたものなら、何か意味があるに違いない」と考えたのかもしれません。
ともあれ、「自力で書く」ということが、どれだけ「不毛なこと」であるかを、私はその時に身をもって学んだのです。
このように、本当に心が透明になると、「書くべき言葉」というのは「向こう」から勝手にやってきます。
私にはそれを止めることさえできません。
それゆえ、私にできることは、その「湧出する言葉たち」を消えないうちに書き留めることだけです。
すると、文章というのは一気呵成に書きあがります。
先も見ず、後ろも振り返らず、ただひたすら「やってくる言葉」を書き記し続けるだけです。
もちろん、時折「ビジョン」のようなものは到来します。
自分が書きつつあるものの結末や全体像が、直観的に「観えて」しまうのです。
でも、だからと言って、やっぱりそれを統御することはできません。
私はただ、「導かれるままに」踊り続けるしかないのです。
私はブログや本の中において、しばしば「天を信じる」という言い方をしますけれど、それは別に観念的な話ではありません。
私は、「人というのは真に『無私』になった時、『天』によって導かれ、『しかるべきこと』をする」ということについての、「体験的な確信」が在るのです。
ただ、「天」の思惑は私にはさっぱりわかりません。
「天」は日々、「万法」を通して私を悟らせ続け、私のことを「どこか」へと導いていきます。
別に私が「ここに行きたい」と注文を付けたわけでもないのに、「天」は絶えず私に「道」を示し続け、私を「どこか」へと流し去って行ってしまうのです。
しかしそれは、社会の空気や他人の思惑に流される時とは違います。
人が社会や他人によって流されるのは、むしろ「無私」になれないからです。
「自分の行く先」をコントロールしたい。
社会から排斥されたり、他人から孤立したりしたくない。
そんな欲望に取り憑かれる時、その人は「自分」を捨てて、社会や他人に迎合していきます。
逆に、「社会や他人から守ってもらわなくても、自分は自分でやっていく」とはっきり覚悟を決めることができると、その人は周りに流されなくなり、「自分自身」を確立することができます。
そして最終的に、その「確立された自分」さえもが消えた時、当人は「天」によって導かれ始めるのです。
夏目漱石が晩年に「則天去私(天に則って私を去る)」と言ったのは、このことです。
そして、「天を信じる」ということは、「どんな未来も恐れない」ということと同義です。
たとえ社会から排除されても、他人から排斥されることになったとしても、「天」がそれを望むのならば従おう。
そのように覚悟が決まった時、その人の「エゴ」は溶解して消え去ります。
そして、その人は社会の流れも他人の顔色も見ることなく、「自分の道」だけを進んでいくようになるのです。
しかし、そのような「自分の道」は、決して一般的に言われるような「自己表現の道」ではありません。
なぜなら、もう「表現するべき自己」が溶けて消えてしまっているからです。
それゆえ、その人の言葉や振る舞いは、自然と「天からの啓示」のようなものになっていきます。
西洋的に言うと、「神の代弁者」です。
今から2000年前にイエスがやっていたことも、おそらくそういうことだったのでしょう。
彼は、どんな「結末」も恐れていなかったはずです。
そして、ただ「神の声」に従って、彼は「為すべきこと」を為したのです。
ということで、「書くこと」というのは「考えること」ではありません。
それは、もしも当人が「無私の状態」にある限り、「天からの声を人々に伝えること」を意味します。
そして、道元禅師の言っているように、そのような言葉だけが、「自己と他己との心身を脱落させ」て、自分と他人を「自由」にすることができます。
それゆえ、そのような「自由の響き」だけが、人々の心に「震え」をもたらし、「内側の光」を思い出させることができるのです。
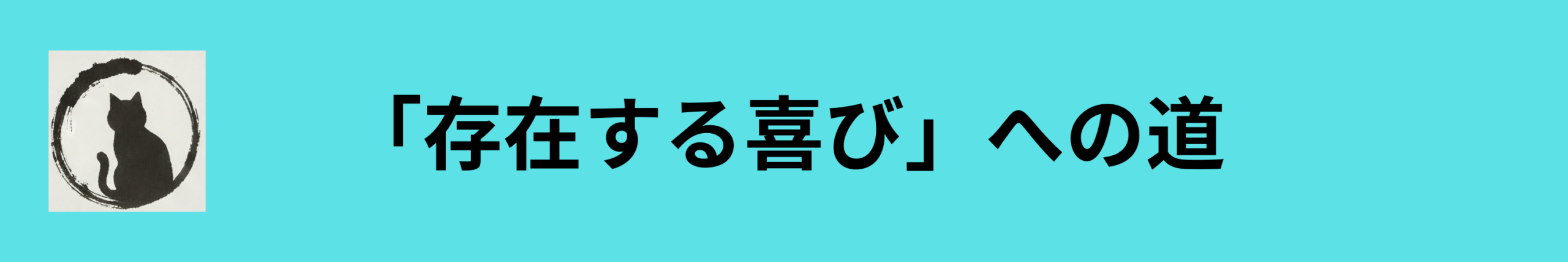

コメント