あなたは何らかの瞑想法を実践していますか?
呼吸や眉間に集中する瞑想をしている人もいれば、ヴィパッサナー瞑想やマントラ瞑想をしている人もいるかもしれません。
こういった瞑想の技法やメソッドを実践すると、当人は思考や感情が静かになったり、心身が安らぐのを感じることもあるでしょう。
ただ、往々にして、また日常生活の中に戻っていくと、再び思考や感情に巻き込まれてしまったり、リラックスした状態が失われてしまったりするものです。
それらの「理想的な状態」は決して日常生活では持続せず、簡単に消えてしまうわけです。
今回は、瞑想の技法やメソッドをおこなうことによって一時的に現れる「理想的な状態」について、「それを日常的に持続させることはできるのか?」ということを論じていこうと思います。
何らかの瞑想技法やメソッドを実践していて、「この状態が普段も持ってくれたらなぁ」と思っている人に対しては、何かしらヒントを提示できるかもしれません。
では、行ってみましょう。
◎「瞑想」とは「死んだかのように静かにしていること」
気づいている人がいるかどうかわかりませんが、私がいつも記事を書く時、「瞑想を実践する」と書くことはありますが、「瞑想『法』を実践する」と書くことはほとんどありません。
それは、「瞑想の実践」という言い方のほうが、「瞑想法の実践」よりも広い枠組みで瞑想について表現できるからです。
でも、そもそも「瞑想」というのは何なのでしょうか?
私の師である山家さんによると、「瞑想」とは「死んだ状態をシミュレーションすること」だそうです。
実際、「瞑」という字の語源をコトバンクで調べてみたところ、「死亡の意」という風に書かれていました。
つまり、「瞑想」というのは、字義通りに解釈すると「死んだ状態を想うこと」であるということになります。
じゃあ、「死んだ状態」ってどんなものでしょうか?
それは、思考も感情も消え去って、「自我」も沈黙している状態です。
仏教で言うところの「空(くう)」ですね。
もちろん、私も実際に死んだことがあるわけではないので、これは「シミュレーション」に過ぎません。
でも、限りなく「死んだ状態」に近いのではないかと思います。
そしてそれは、言い方を換えると「静寂」です。
つまり、「ただ静かに在ること」というのは、「死んだかのような状態でいること」でもあるわけです。
このように考えていくと、「瞑想状態」というのは「死んだかのように静かになっている状態」のことです。
そして、私にとって「瞑想の実践」とは、この「瞑想状態(死んだように静かな状態)」を維持しようとすることを意味しています。
それに対して、私が「瞑想『法』の実践」と言う場合には、「何らかの瞑想の技法をおこなうこと」を意味します。
さて、それらはいったい何が違うというのでしょうか?
以下、順番に説明していきます。
◎「瞑想『法』の実践」は、「自我」による独裁体制を強化する
まず、「瞑想『法』の実践」についての話から始めましょう。
何らかの「瞑想法」を実践する場合、人によっては呼吸に集中する瞑想技法を実践するかもしれませんし、他のある人はマントラ瞑想を実践するかもしれません。
そこには「明確な手順」があり、「意識を集中する対象」があります。
そして、「決められた手順」を守って、「決められた対象」に意識を集中するために、当人は「自我」を働かせることになります。
勘の良い方は既に気づいたかもしれません。
そうです、「瞑想『法』の実践」をしている限り、「自我」が何時まで経っても死なないのです。
もちろん、「瞑想法」を実践している場合であっても、どこかの段階で集中力が極限まで高まると、「自我」が一時的に溶けて消えることがあります。
アスリートで言う「ゾーンに入る」というやつです。
この瞬間だけは、「自我」が消えていなくなっているので、「瞑想状態(死んだかのような状態)」が出現してきます。
しかし、それはあくまでも一時的なものであり、瞑想法の実践が終わると、再び「自我」が息を吹き返してきます。
実際、どんなに優秀なプロスポーツ選手であっても、日常的に起きてから寝るまでずっと「ゾーン」に入り続けることはできません。
それはあくまでも「特殊な意識状態」であり、日常の中に根付かせることができないのです。
私が「瞑想の実践」という言い方を主に使い、「瞑想『法』の実践」という言い方をあえて使わないのはこのためです。
もしも「瞑想(死をシミュレーションすること)」が何らかの技法の実践によってしか不可能であるとするなら、それはどうしても「非日常的で限定的なもの」にならざるを得なくなります。
ここにおいて、当人は「静寂」を日常の中に広げていくことはできないため、もしもそれを求めるのであれば、ひたすら「瞑想『法』の実践」にのめり込んでいく他ありません。
そして時には、そういった人たちが「瞑想法のアスリート」のようになっていくことがあります。
彼らは社会生活を放棄して、毎日毎日、何時間も坐って瞑想をする生活を送り、「集中力」をどこまでも高め続けます。
なぜなら、「それこそが『静寂』を自分の中に根付かせる唯一の方法だ」と、彼らが信じているからです。
しかし、そうやって「集中力」を鍛えていくと、その分だけ「自我」が強化されていきます。
と言うのも、私たちが「集中力」を行使する時には、「自我」の働きに依存する他ないからです。
そもそも「自我」は、もともと何の方向性も持たない「意識(本来の自己)」に、何らかの方向性を与えることが仕事です。
「あれをしろ」「これを求めろ」と言うことで、「自我」は私たちに進むべき方向を示します。
だからこそ、私たちは日々家事や仕事をこなして生活することができているわけです。
そして、瞑想の技法をする際、「何らかの対象に集中する」ということは、「『意識』の方向性を特定の対象や行為に固定すること」に他なりません。
それゆえ、私たちが集中する時には、必ず「自我」も働くことになるのです。
そして、「自我」が強くなればなるほど、内側で思考や感情の圧が強まっていきます。
つまり、「自我」強くなるにしたがって、思考や感情もより一層激しく暴れ出すのです。
そもそも、「自我の働きが強くなる」ということは、言ってみれば、「自我による独裁体制が強化される」ということでもあります。
当人はそれによって「自己コントロール感覚」が強くなってきます。
つまり、「自分は、自分自身の意志で考えたり判断したりできている」という感覚が出てくるのです。
しかし、この「自己コントロール感覚」の裏側で、「市民(思考や感情)」は肩身の狭い想いをしていることがあります。
たとえば、心や身体は「もっとダラダラ休んでいたいなぁ」と思っていても、「自我」のほうが「まだまだ頑張って働かなければ!」と思っていると、両者の間で意見の不一致が発生します。
こういった場合、心や身体にも発言権が認められていれば、「自我」の側も「じゃあ、たまにはちょっとのんびりしようかね」と妥協することもあるでしょう。
しかし、「瞑想『法』の実践」によって「自我」が強化されていると、「自我」は心や身体の言い分を聞かなくなっていってしまいます。
そういう場合の「自我」は、無意識から湧き上がってくる思考や感情を、無理やり力ずくで黙らせるのです。
そうすると、確かに一時的に「静かな状態」が訪れるかもしれません。
その「一見静かな王国」では、「自我」が一人で威張っていて、「あれをしろ」「これをしろ」と命令を出し、心と身体を支配しています。
しかし、そういう状態は長くは続きません。
なぜなら、無理やり抑え込まれた思考や感情は、「自我」の気が緩んだタイミングで噴出してくることになるからです。
◎ストイックな「瞑想法のアスリートたち」が取り逃す「絶対的な幸福感」
これは、瞑想「法」をいくらか実践したことのある人は、経験があるかもしれません。
たとえば、瞑想法を実践している間だけは、思考や感情を静かにしておけるのですが、15分とか30分とか、決めていた実践の時間が過ぎて「よっこらしょ」と腰を持ち上げた途端、急に思考や感情が噴き出してくることがあります。
それは、「自我」によって思考や感情が無理やり押し込められていた反動で起こる現象です。
もしもこのような状態を収めようと思ったら、「自我」による独裁をやめて、共和制を敷くしかありません。
つまり、心や身体にも市民権を与えることで、発言を認めてあげるのです。
しかし、実践をしている当人は、往々にして逆方向に舵を切ります。
つまり、「きっとまだ修行が足りないんだ」と考えて、ますます「集中する瞑想」に時間をかけるようになり、「自我」による独裁を強化していってしまうのです。
「瞑想法のアスリートたち」はそんな風にして誕生します。
彼らの心と身体は「もう毎日何時間も瞑想法を実践するのは疲れたよ」と言っています。
しかし、当人は「集中する訓練をやめたら、自分の思考や感情に負けてしまう」と考えて、「瞑想『法』の実践」にしがみつきます。
そして、実践をすればするほど、「心や身体が発する声」は抑圧されて聞こえなくなり、「自我」だけが肥大化していくのです。
ただ、周りから見ると当人はとてもストイックに見えるので、「理想的な修行者」のように見なされがちです。
しかし、「本当の静寂」は「自我」を手放した後に起こります。
それはゴータマ(お釈迦様)が悟った時の逸話によく表れているのではないかと思います。
ゴータマは王子としての地位を捨て、修行者の道に入りました。
各地を巡って数人の師につき、そこで様々な瞑想の技法を学んだようです。
しかし、どの師もゴータマを満足させることができなかったため、最終的に彼は数人の修行仲間たちとともに、命を懸けた苦行を断行しました。
断食をし、肉体を痛めつけ、それによって精神を解放すれば、輪廻から抜け出して「安らぎ」が得られると彼らは思っていたようです。
ですが、約6年間も苦行を重ねたにもかかわらず、彼らはいっこうに「安らぎ」に到達できませんでした。
そして、ある時にゴータマはこう考え始めました。
「このやり方を続けても、解脱には至らないのではないか?」と。
そして、彼は一人だけ苦行をやめて、仲間たちの元から去っていきます。
仲間たちは「ゴータマは安逸な暮らしに逃げた脱落者だ」と言って軽蔑しましたが、ゴータマとしてはもうこれ以上、苦行を続けることに意味を感じられなかったようです。
その後、断食でやせ細っていたゴータマは、スジャータという娘から乳粥を与えられて一命をとりとめます。
それから、菩提樹の元で一人坐っている時に、彼は悟ったと伝わっています。
この物語は、様々な解釈が可能だと思います。
ただ、私が一つ思うのは、「本当に『安らぎ』を求めているのであれば、何もしないでただリラックスすればいいだけだ」ということです。
別に苦行をして自身を責め苛む必要はないのです。
もちろん、「そんなのはしょせん世俗的な快楽に過ぎない!」と「瞑想法のアスリートたち」は言うでしょうけれど、極度の集中や激しい苦行の最中にしか感じられない「一時的な幸福感」のほうが、よほど「虚ろなまやかし」ではないかと、私自身は思います。
「本当の安らぎ」は、そんな風に状況や条件によって左右されるものではなく、「絶対的なもの」であるはずです。
そしてそれは、当人が何もせずリラックスして、「死んだかのように静かになった状態」の時に、不意に内側から湧き出てきます。
菩提樹の元で一人坐っていたゴータマは、それを体験したのではないでしょうか?
実際、その時の彼は、もはや何も求めていなかったはずです。
王子としての地位も捨ててしまった。
何人もの師を訪ねたのに、満足する答えは見つからなかった。
そして、6年間も命懸けで苦行をしたけれど、それでも苦しみは消えませんでした。
当時の彼からすると、もう万策尽きていたのです。
「できること」はもう何もありません。
その時、きっと彼は初めて「手ぶら」になったのだと思います。
「もう何もするべきことはないし、目指していくべき場所もない」
「全てこれで良い」
ゴータマは菩提樹の元でそのように感じたのだと、私は想像しています。
そして、そのような「全面的な明け渡し」の中で、「絶対的な安らぎ」を彼は見出したのだと、私は思うのです。
◎「意識的な実践」から「無意識的な実践」へのシフト
先ほども書きましたが、「何らかの技法」を実践することの限界は、それを続けている限り、「自我」が死ねないということです。
むしろ、「技法」を実践すればするほど、「自我」による独裁体制が強化されていってしまいます。
そうならないためには、「自我」に頼らなくても「瞑想状態(死んだように静かな状態)」を再現できるようにしていく必要があります。
しかしその際のアプローチは、「技法を意識的に実践する」という形を取ることができません。
なぜなら、「意識的な実践」は「自我」の管轄する領域だからです。
なので、ここでは反対に「無意識的な実践」をおこなっていくことになります。
つまり、「自我」の代わりに「無意識」に働いてもらうことで、「瞑想状態」を維持するようにしていくわけです。
なお、このアプローチを取る際の詳しいやり方については、下記の記事を参照してください。
【第10.5回】「瞑想」の第二段階《実践編》|「無意識の力」を伸ばす「集中しない瞑想」
「無意識」に瞑想を任せる場合、当人はただ坐ったまま何もせず、そのまま過ごしてみたりします。
「思考や感情を静めよう」とも考えなければ、呼吸や眉間などの何らかの対象に意識を集中しようともしません。
本当に何もせず、ただ坐るのです。
そうしていると、きっと思考や感情が浮んできたり、「自我」が「退屈だー、何かしてくれー」と言ってきたりするでしょう。
でも、それを気にすることなく、ただ坐り続けます。
すると、思考や感情は消えていきますし、「自我」もそのうち諦めて、もはや何も言わなくなります。
そこには何も残っていません。
「空(くう)」です。
別に、「空」を意識的に作ろうとしたわけではないのに、気づいたら当人はその中に居ます。
そして、その「空っぽ」の中で、なぜか「穏やかな幸福感」が湧き上がってきます。
それは、「極度の集中」や「激しい苦行」によってもたらされたものではなく、むしろ「何もしないこと」の中から湧き出てきたものです。
そして、だからこそ、この「幸福感」は日常の中に持ち込んでいくことができます。
なぜなら、当人はその「幸福感」を感じるために、「特定の技法」を実践している必要がないからです。
この世のどこにも、マントラを四六時中唱えながら生活できる人はいません。
呼吸に意識を集中するのだって、毎日何時間も続けていたら疲れてしまいます。
それゆえ、「『技法の実践』と結びついている幸福感」は、日常生活に持ち込むことができないのです。
それに対して、「『何かをすること』と結びついていない幸福感」は、「手ぶら」で感じることができるので、日常生活に定着させることが可能です。
そして、私が「瞑想の実践」と言う場合、このような「行為と無関係な幸福感」を日常生活に定着させる試みのことを指しています。
それは決して「特定の技法の実践」ではありません。
しかし、確かに「瞑想(死のシミュレーション)の実践」ではあります。
そして、もしも「内なる静寂」と「穏やかな安らぎ」を日常の中に根付かせようと思うなら、このような「技法に頼らないアプローチ」を採用する必要があるのです。
◎瞑想の中で生じる「幸福感」が、「生」と「死」を超える助けとなる
また、このような形での「瞑想の実践」が進んでいくと、当人の中で「死の恐怖」が徐々に薄まっていきます。
なぜなら、「自我」さえもが消えた「死の静寂=瞑想状態」の中に、なぜか「幸福感」があることを当人は体験的に理解するようになっていくからです。
そもそも、多くの人は「自我」が消えることを恐れていると思います。
人は、自分の人格や記憶が消えて、この世界とかかわれなくなることを恐れるのです。
しかし、「瞑想の実践(瞑想『法』の実践ではなく)」を十分に積んだ人は、「自我」が消えることを恐れなくなります。
むしろ、「何もしないこと」の中で「自我」が消えていることによって、「本来の自己」が現れてくるということを、当人は知っています。
そして、その「本来の自己」の本質が「根拠のない幸福感」であることも、彼は知っているのです。
そのため、「瞑想の実践」が十分に進んだ人は、「生」と「死」の両方に執着しなくなります。
なぜなら、「生きているのであれ、死んでいるのであれ、『この幸福感』がなくなることはないだろう」と、当人は感じ始めるからです。
このため、当人は「何が何でも生き残らなければ」とも思いませんし、「一刻も早く死んでしまわなければ」とも思いません。
当人は、「『生』と『死』には大した違いがない」と思っています。
もちろん、生物の本能から身体の痛みは避けようしますが、「瞑想の実践」に伴って、「死の恐怖」それ自体は希薄になっていくのです。
私は「輪廻からの解脱」というのは、実のところ、このことなのではないかと思っています。
それは、「この世や人生に対する執着の消滅」です。
「生きよう」と思わず、「死のう」とも考えず、ただ、なぜか与えられた存在として「在る」だけの状態。
そこには「幸福を求める欲求」も、「苦しみから逃げようとする恐れ」もありません。
すべてが「あるがまま」です。
かつてのゴータマと苦行仲間たちは、苦行によって肉体を滅ぼせばそのような状態になれると思っていたのかもしれませんが、別に苦行は必要ありません。
ただ、「何もしないこと」の内で深くリラックスし、そこで溢れ出た「幸福感」を日々の生活の中に根付かせていけばいいだけなのです。
◎技法に頼って得た「幸福感」は、砂漠に生じる「蜃気楼」のようなもの
いかがでしたでしょうか?
今回は、「技法を実践する」ということの功罪について論じてみました。
人によっては「技法の実践を突き詰めていった果てに『悟り』があるに違いない」と思っているかもしれませんが、実はそんなことはありません。
むしろ、「技法の実践」のデッドエンドは割とすぐきます。
私としては、「何らかの対象や行為に集中することで、1分のあいだ無思考でいられたら、技法は卒業してOK」と考えています。
ちなみに、これについて詳しいことは、下記リンク先の記事で解説しています。
【第9回】「瞑想」の第一段階《理論編》|なぜいったん「自我」を強化するのか?
「たった1分なんて、ハードル低っ!」と思う人もいるかもしれませんけれど、私はあまり長く「技法の実践」には留まらないほうが良いと思っている人間です。
もちろん、「技法の実践」には「自我」が参加するので、当人は「意味のある事をやった感覚」を感じやすいです。
1時間の瞑想法の実践をしたりすると、たぶん「達成感」もあるでしょう。
でも、実際にはそれが「罠」だったりします。
と言うのも、そういった「充実感」や「達成感」というのは、「自我」を育てるエサみたいなものだからです。
そして、それらの「充実感」や「達成感」に依存すればするほど、当人は「何もしないでただくつろぐ」ということが、ますます難しくなってしまいます。
いずれにせよ、「自我」を働かせることでもたらされる「幸福感」は、砂漠に現れる「蜃気楼」のようなものです。
近づこうとすればするほど、それは遠ざかっていきます。
そして、「やっと着いた!」と思った時には、それはもう消えてなくなってしまっているのです。
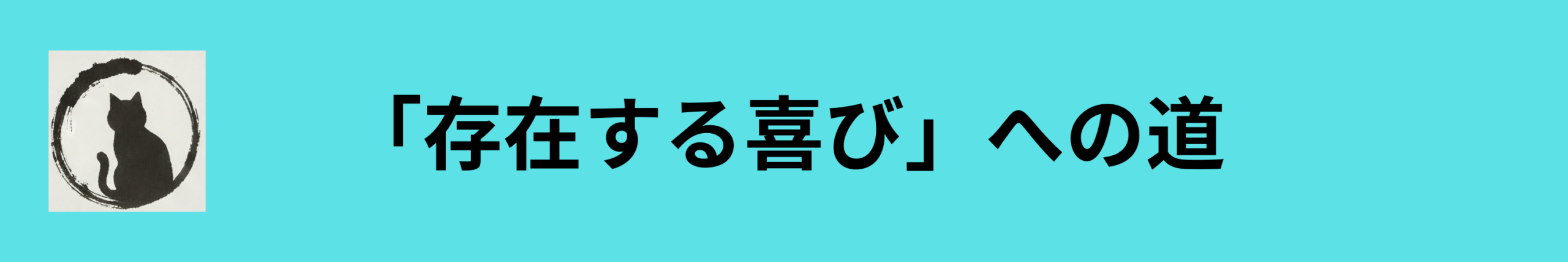

コメント