前回と前々回で、「覚者とはいったいどんな人間なのか?」ということを書いてきました。
「覚者」を見分ける二つの基準|「雄弁な無知者」と「口ごもる知者」のパラドクス
悟ることができるのは「傑出した人物」だけなのか?探求とは「究極の平凡さ」へ向かう旅である
今回は、この「覚者シリーズ」の第三段ということで、次のテーマで文章を書いてみたいと思います。
それは、「覚者というのは『独善的な人間』なのか?」というものです。
そもそも、「悟り」というのは免許制ではありません。
公的機関が合格証書を発行するわけではなく、覚者は自分自身で「悟った」と判断します。
そして、一度悟ると、たとえ世界中からそれを否定されても、覚者はそのことを意に介さなくなります。
誰がなんと言おうと、「自分は悟っている」と考えるわけです。
しかしそうなると、周りの人々の中には、当然次のような疑問が湧いてきます。
つまり、「それって『独りよがりな思い込み』なんじゃないの?」と思うわけです。
確かに、「真理」というものは客観的に証明することができません。
それゆえ、覚者の「悟り」も万人に納得できる形で示すことは不可能です。
しかし、だからといって覚者が「独善的な人間」であるわけではありません。
覚者は、決して他人の意見に対して耳を塞いだり、「自分だけが正しい」と言い張ったりしているわけではないのです。
では、覚者は内側で何を思っているのでしょうか?
今回は、そのことについて書いてみます。
◎探求者は自分の思考や感情を、「手足の存在」と同じように認識する
まず「独善」という言葉の定義を確認するところから始めましょう。
今、ネットでパッと調べてみたところによると、辞書にはこう書いてありました。
いわく、「自分だけが正しいと信じ込んで行動する態度。ひとりよがり」だそうです。
「自分だけが正しいと信じて行動する」ということは、つまり「独善」というものが一種の「個人的信念」であることを意味しているのではないかと思います。
つまり、他人がなんと言おうと、「自分こそが正しい」と信じているわけです。
それゆえに、その考えには客観性がなく、「ひとりよがり」になってしまうということでしょう。
しかし、別に覚者は「自分は正しい」と信じているわけではありません。
これについては、そもそも「真理」を理解するまでの探求の過程で、探求者が何をするのかを考えてみるとわかりやすいと思います。
たとえば、多くの探求者は瞑想などの実践によって、「自分の思考や感情を観察する」ということをおこないます。
最初のうちは、思考や感情に巻き込まれて我を失ってしまいますが、徐々に落ち着いてそれらを観察できるようになっていきます。
すると、探求者は自分の中にどんな思考や感情が在るのかを、正確に理解できるようになっていくのです。
たとえば、もしも内側で「上司が嫌いだ」という思考が湧くと、探求者は「今、『上司が嫌いだ』という思考が湧いた」と認識します。
また、なんとなくイライラしてきたら、「今、私の中に『イライラ』が在る」と認識します。
こんな風に、探求者は絶えず自分の内側を観察し、「そこに何が在るか」を淡々と認識し続けるのです。
すると、探求者は自分の思考や感情に対して、徐々にそれを「単純な事実」として認識するようになっていきます。
それは当人にとって、自分の身体に手足が在ることを確認するのと同じようなものです。
実際、手足が在る人は、そのことを証明不要な「単純な事実」として認識しているはずです。
もしそれを他人から否定されても、当人は「いや、そうは言っても手も足も在るんだってば」と思うのではないでしょうか?
それは当人にとって議論するようなことではなく、「当たり前の事実」であるわけです。
◎「自我」は絶えず「私」を作り続け、「知性」はその様子をただ映し出す
そして、さらに瞑想の実践が進むと、探求者は思考や感情だけでなく、「自我」についても分析できるようになっていきます。
ちなみに、「自我」というのはヨーガだと「アハンカーラ」と言います。
「アハン」というのが「私」を意味し、「カーラ」というのは「配役係」とか「製造者」を意味するのだそうです。
つなげると「『私』の配役をする係」とか「『私』を製造する者」ということですね。
それゆえ、「アハンカーラ」は英語だと「I-maker」とも訳されます。
つまり、「自我」とは「『私』を作る者」です。
実際、自我は絶えず「私は…」と語り続けます。
「私はこのように考える」
「私はこれが正しいと思う」
「私はこれをしなければならない」
「私は『真理』を悟りたい」
「自我」はこんな具合に、何にでも「私」というラベルを貼ろうとします。
そうすることで、「自我」は私たちの内側に生起するあらゆる思考や感情を管理しようとし、同時に、「その源は『私』である」と主張するわけです。
それゆえ、世の中の人のほとんどは、この「自我」のことを「自分自身」だと思い込んでいます。
なぜなら、「この『私』こそが『自分』なのだ」と「自我」が訴え続けるからです。
しかし、実際には「自我」と「自己」とは別のものです。
私たちの「自己」は「私は…」と言って何かを主張したりしません。
「自己」は「ただ一切を観ているだけの者」です。
それゆえ、「自己」は「観照者」とも呼ばれるのです。
【第7回】世界はなぜ「この自分」からしか見えないのか?「意識」の謎について
【第11回】「瞑想」の第三段階《理論と実践》|「自分は観察者だ」という錯覚に気づく方法
【第12回】「瞑想」の第四段階《理論と実践》|「自我」は「虚構」に過ぎないと理解する
瞑想の実践を続けていくと、探求者はどこかの段階で、「『自我』は『自己』ではない」ということに気づきます。
すると、かつて思考や感情を客体化して観察できるようになったのと同様に、「自我」についてもこれを対象化して分析できるようになっていくのです。
たとえば、「自我」が「私はこの考えこそが正しいと思う」と主張すると、「『自我』が『この考えこそが正しい』と主張している」と探求者は認識します。
また、「自我」が「私はもっと有名になってチヤホヤされたい」と主張すると、「『自我』が承認欲求に衝き動かされている」と認識するわけです。
こうした際に、「自我」のことをそのまま認識しているもののことを、ヨーガでは「知性(ブッディ)」と呼んでいるようです。
なお、「知性(ブッディ)」についても過去に一つ記事を書いているので、興味のある人は読んでみてください。
思考における「三つの層」|瞑想をすると、本当に考えることができなくなるのか?
ヨーガでは、「知性(ブッディ)」とは「鏡」のようなものであると言われます。
つまり、何であれ目の前にある対象をそのまま映し出すのです。
たとえば、「自我」の動きはもちろん、思考や感情や身体の感覚などまで含めて、あらゆるものを「知性(ブッディ)」はそのまま映し出します。
実際、瞑想の実践が進んでくると、自分の内側で起こっていることを「ありのまま」に認識することができるようになっていくものです。
つまり探求者は、自分が考えたり感じたりしていることを、歪曲化することなく、そのまま認めることができるようになっていくのです。
◎「自我」を守ろうとすることで、私たちの認知は絶えず歪む
しかし、世の中の多くの人は基本的にそういったことはできません。
なぜなら、どうしても「自分に都合のいいこと」だけを認めて、「自分にとって都合の悪いこと」は否認したくなってしまうからです。
この際に「自分の都合」をあれこれ気にしているのが「自我」です。
「自我」は明確なセルフイメージを持っています。
たとえば、「自分は決して間違いを犯さない完璧な人間だ」というセルフイメージを持っている人は、「自分の間違い」をなかなか認めようとしません。
仮に「自分のミス」を見つけても、無意識にそれを見なかったことにしようとします。
また、「自分は思いやりに溢れた優しい人間だ」というセルフイメージを持っている人は、自分の中に「残虐な思考」や「他者への憎悪」が湧いてきても、それを認めることができません。
そういった思考や感情は無意識に抑圧されることになり、当人には自覚できない形で存続することになっていきます。
しかし、それらの思考や感情は、抑圧されても別に消えるわけではありません。
ただ、当人の目からは見えなくなるだけです。
抑圧された思考や感情は、確かにまだその人の中に残っており、何かのタイミングで外に飛び出してくるのです。
どうしてこういったことが起こるかというと、もしも「事実」を認めてしまうと、「自我」が作り上げているセルフイメージが傷つくからです。
そして、世の中のほとんどの人は、「自我」のことを「自分自身」だと錯覚しています。
それゆえ、「自我」が傷つくと、「自分」まで傷つくかのように感じてしまい、「自我」を必死で守ろうとするのです。
こういった「自我」による「自己防衛反応」が、私たちの「自己認知」を絶えず歪めます。
現実に自分の中に存在する思考や感情を、多くの場合、私たちはそのまま認識することができません。
私たちの認知はいつもどこかが歪められており、「自我」にとって都合がいいように歪曲されているのです。
◎「認知」と「認識」の違いについて
ちなみに、私がこの記事で「認識」と言う場合、それは「客観的に対象について観察することで成立する理解」のことを意味しています。
なので、探求者が瞑想の中で思考や感情の存在を認める場合、それは思考や感情について探求者が「認識」しているということです。
また、「認知」という言葉については、「認識」よりも手前のプロセスをイメージしています。
つまり、まだ十分に対象を客観視できておらず、もっと直接的に知覚している段階です。
たとえば、思考や感情に巻き込まれている時、当人は頭がグルグルしたり、胸がザワザワしたりするのを知覚します。
そういう意味で当人は、思考や感情によって発生する「ある種の感覚」なら感じているわけです。
しかし、それらを客観的に「こういう思考」「こういう感情」と言って切り分けることはできていません。
つまり、思考や感情と同化してしまっていて、当人はそこから距離を取ることがまだできていないのです。
この段階において、当人が主観的な感覚から思考や感情の存在を感知することを、「認知」と呼び分けたいと思います。
ちょっと整理してみましょうか。
- 認識
対象を客観的に理解して把握すること。
対象との同化が解けており、当人は距離を取って対象を観察することができる。 - 認知
対象を感覚的に知覚すること。
対象とまだ同化しており、当人は距離を取って対象を観察することが難しい。
もちろん、これは私の個人的な定義なので、心理学者がどう言うかは知りません。
ただ、「認識」と「認知」という言葉を整理しないままこの記事を読んでいくと、人によっては混乱するかと思ったので、念のため説明をはさみました。
なので、「特に気にならないよ」という方は、両者を厳密に区別して読まなくても大丈夫です。
それでもメインテーマの意味はだいたい通るはずなので。
ということで、話を先に進めていきましょう。
◎「知性」が「自我」による認知の歪みを正す
話を戻すと、「私たちの認知は『自我』によって絶えず歪められている」ということでしたね。
「自我」は常に「『私』こそが『自分』という感覚の源だ」と主張し、私たちはそれを信じ込んでしまいます。
それゆえ、「自我」が作ったセルフイメージが傷つかないように、私たちは「自分の認知」を無意識に歪めてしまうわけです。
しかし、瞑想の実践が進むことで、「知性(ブッディ)」によって「自我」を客観的に分析できるようになっていきます。
すると、当人は「『自我』は『自分』ではない」と理解できるようになるため、結果的に、わざわざ「自我」を守る必要を感じなくなります。
つまり、「自我」にとって都合の悪い思考や感情も、抑圧することなくそのまま認識できるようになるのです。
それゆえ、もしも「自我」が「私は正しい。私以外の人間はみんな間違っている」という「独善的な思考」をしていても、探求者はすぐにそれに気づきます。
「自分の中に独善的な思考が在る」とだけ気づいて、それを特に気にかけません。
「そんなものが自分の中に在ってはいけない」とも思いませんし、「自分は決してひとりよがりな人間ではない」と言って反論しようともしません。
ただ、「独善的な考えが自分の中に浮かんでいる」とだけ認識し、それを「単なる事実」として受け入れるのです。
そして、そうやって自分の思考を認識していると、それはやがてどこかへ消えていってしまいます。
永遠に留まる思考というものはありません。
どんな思考もいつかは消えます。
もしも思考がなかなか去らないとしたら、それは「自我」が「これこそが『私』の思考だ」と言って執着しているからです。
そして、私たちは往々にして「自我」の言うことに支配されてしまい、「自分の考えの正しさ」に固執することになってしまうわけなのです。
このように、「自我」を分析できるようになると、「私は…である」と告げるあらゆる思考や感情から距離を取ることができるようになります。
そして、もしも「自我」が「『私』こそが正しいのだ」と言っていたとしても、探求者はその声に対してもう自己同一化することがありません。
あたかも自分の身体に手や足が在るのを「事実」として認識するのと同じように、「『自我』が独善的な思考をしている」とだけ認識することができるのです。
◎「自分をずっと惑わしていたのは、自分が作った幻だった」という気づき
しかし、こういったことは全て、探求者の内側で起こっていることです。
そして、私たちには「他人の思考や感情」を外から観察することはできません。
私たちに観察することができるのは、あくまでも「自分の思考と感情」だけです。
それゆえ、周囲の他人には、「その人がどれだけ客観的に自分の思考や感情を観察できているか」を外から判定することが不可能なのです。
しかし、それを逆からいうと、「もしも自己観察をどこまでも徹底していったら、当人は自分の思考や感情の観察に関しても、自分の手足を観察するのと同じレベルで正確におこなうことができるようになるはずだ」という話でもあります。
もちろん、ほとんどの人は最初からそこまで正確に自己観察をおこなうことはできないでしょう。
実際、実践を初めたばかりの探求者は、思考や感情に巻き込まれ続けてしまうことが多いため、観察どころではないと思います。
そして、仮に実践が進んでそうした思考や感情が静まってきても、「『自我』こそが『自分』なのだ」と思い込んでいたら、「自我」を守るために当人は「事実認知」を無意識に歪めてしまうはずです。
しかし、もしも実践をどこまでも徹底するなら、どこかの段階で探求者は「自我」を突き抜けて、「知性(ブッディ)」の層に到達します。
そこまで行くと、思考や感情の雲に目を塞がれることはなくなりますし、「自我」による主張によって「事実」を歪曲することもなくなるでしょう。
そして、「最終的な悟り」に到達した時、当人はただ理解します。
「結局全ての執着を作り出していたのは、自分自身だったのだ」ということをです。
その認識は、当人にとって身体に手や足が在るのを認めるのと同じくらい、「厳然たる事実」として存在しています。
もちろん、悟った直後は、この「事実」をすぐに飲み込めない人もいるでしょう(少なくとも、私の場合はそうでした)。
それゆえ、悟ってからしばらくの間、「自分が理解したことは本当だろうか?」と疑って、いろいろ検証したりします。
ですが、やっぱり認識は変わりません。
「自分を束縛していたものは、他でもない自分自身だったのだ」という認識は、揺るぎようもなく存在するのです。
悟った時に当人は、別に「世の中の人々はみんな間違っている(自分だけが正しい)」とは考えていません。
当人はただ、「これまで自分のことを惑わしていたのは、自分自身で作った幻だったのだ」と気づいただけです。
別に誰を否定する必要もありません。
むしろ、否定されたのは「これまでの自分自身」です。
だからといって、「これからの自分」が「正しい」と言うのとも違います。
当人はただ、「『自分は正しい』と思うことも、『相手が間違っている』と考えることも、どちらも自分を縛る囚われに過ぎなかったのだ」ということを、「動かしがたい事実」として認識しているだけなのです。
◎「『自我』を通さず見る者」には、多くの人々の苦しみが見える
このような理解に達した覚者は、自分自身の経験から、もしも他人が自身の思考や感情に囚われて苦しんでいれば、「まず思考や感情を静めたほうがいいですよ」とアドバイスするかもしれません。
また、「自我」と一体化して苦しんでいる人を見かけたら、「『自我』は『本当のあなた』ではありませんよ」と言って、気づきを促そうとするかもしれません。
ですが、それは別に「自分の正しさ」を主張しているわけではありません。
それはあくまでも「慈悲の心」ゆえに言っているだけに過ぎないのです。
たとえば、もしもあなたが薬の知識を持っていて、目の前に病で苦しむ人を見かけたら、「その病気にはこの薬が効きますから、どうか試しに飲んでみてください」と言うのではないでしょうか?
しかし、もしもそこで相手が「うるさい!自分のほうが正しいかのように考えやがって!どこかに行け!」と言ったとしたら、あなたはいったいどうするでしょう?
薬であれば物理的に無理やり飲ませることもできるでしょうが、思考や「自我」との同化については、当人が主体的に努力してそれと向き合わないと、解消することができません。
それゆえ、「どうせ自分だけが正しいと思ってるんだろ?引っ込んでいろ!」と言われてしまうと、覚者にはそれ以上、どうすることもできないのです。
もしそれでも覚者に何かできることがあるとすれば、「どうかこの人の苦しみに終わりが来ますように」と心の中で祈ることくらいでしょう。
いずれにせよ、覚者が独善的に見えてしまうのは、世の中の人のほとんどが、自分の思考や感情、さらには「自我」によって深く支配されているからです。
そういう状態にある人は、自分のことを冷静に観察することができませんし、現実を絶えず歪めて見ています。
実際、「自分がどれだけ事実認知を誤るか」ということを、人々は経験的によく知っているはずです。
同時に、社会的にもこのことは教育されます。
「自分の考えを信じすぎてはいけない。なぜなら、それは抑圧され歪んだものであるかもしれないから」と、様々な教育者や指導者が語り続けています。
しかし、「自分の考え」が信じるに値しないのは、それが「自我」という実体のない幻に由来するものだからです。
人々が「自分の考え」を信じて「事実認知」を歪めてしまうのは、「自我」を絶対だと信じるからです。
私たちは「自我」によって絶えず振り回されているというのに、その「自我」こそが「自分」であると思い込んでいます。
そして、そういった「自我の声」を、「自分の考え」だと私たちは誤認してしまうのです。
それに対して、覚者は「自我の声」を絶対のものとは信じていませんし、それと自己同一化もしていません。
しかし、そういった覚者の「内側の事情」は、外にいる他人の目からは見えません。
そもそも、多くの人の目には、「自分の自我」さえよく見えていないと思います。
むしろ、「自我」が「目そのもの」になってしまっていて、「『自我』を通さずに見る」ということが、ほとんどの人にはできないのではないかと私は感じています。
それゆえ、「覚者は決して独善的ではない」ということもまた、客観的に証明することはできません。
なぜなら、「覚者の独善性」について、「自我の声」に振り回されず落ち着いて判断できる人自体が、世の中にはほとんど存在していないからです。
ただ、覚者が「自分の正しさ」に固執しているわけではないことだけは、はっきりと言っておこうと思います。
◎次回予告|まだ覚者ではない、探求者の独善性について
ということで、今回は「覚者は独善的なのか?」というテーマで記事を書きました。
しかし、そうは言っても、探求者が決して独善的ではないということではありません。
むしろ、探求の過程において、探求者は「自身の独善性」を絶えず検証し、それに抗わねばなりません。
そして、この「独善性との闘い」に負けてしまって、まだ「最終的な悟り」に到達していないのに、「自分はもう悟った」と考え始める人もいます。
しかし、そういう人はまだ覚者ではありません。
実際、そうした人たちは、だいたいにおいて非常に「独善的な考え方」をします。
たとえば、「自分は『真理』を悟った特別な人間だ」と考えて、平気で他人を見下したりします。
こういった状態に陥ってしまうことは、探求の世界では「よくあること」です。
ですが、そういう時に、「自分はわき道にそれてピット・フォール(落とし穴)にハマっている」と気づかないと、その人の探求の旅はそこでストップしてしまいます。
そうならないように、次回の記事では、探求の過程で探求者が「自分はもう悟った」と思い込みやすいポイントをお伝えしたいと思います。
探求の過程で「大きなターニングポイント」を迎えると、しばしば当人は「ここがゴールに違いない」と思いがちなのですが、「実はそうではないんだよ」ということをお伝えできればと思っています。
というわけで、久しぶりに「続きもの」の記事ですね。
また次回お会いしましょう。
⇓⇓次回の記事です⇓⇓
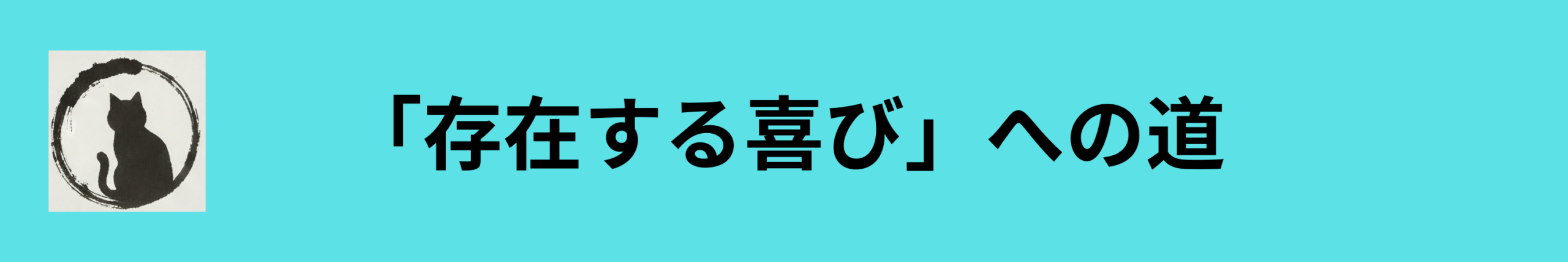


コメント