これまでの記事によって、私は「意識」と「純粋な喜び」について理解する道筋を示してきました。
連載の構成としては、第一部が導入として機能しており、「純粋な喜び」を第二部で扱い、「意識」については第三部で扱いました。
ただ、「純粋な喜び」に関する理解と、「意識」に関する理解は、どちらか一方だけで完成するものではありません。
むしろ、どちらか一方だけしか理解できていない状態には、時として危険性も潜んでいます。
そのため、最終的に私たちは「純粋な喜び」と「意識」の両方について理解する必要があります。
ということで、今回の記事では、「純粋な喜び」か「意識」か、どちらか一方を既に理解することができた人を主な読者の対象として、解説記事を書いていこうと思います。
記事の内容としては、「一方しか理解できていないと具体的にどんな危険性があるのか」ということを書いていくつもりです。
「『純粋な喜び』は理解できたけれど、どうも何かがおかしい気がする」という人や、「『意識』については理解したけど、なんだか何かが欠けている気がする」という人は、ぜひ最後まで読んでみてください。
では、いってみましょう。
◎今回の記事で使用する用語の整理
まず、説明を始める前に、用語と概念を整理しておきたいと思います。
そもそも、これまで私は「純粋な喜び」や「意識」といった言葉を使ってきましたが、これらの概念には正式な専門用語があるのです。
なぜ専門用語を避けていたかと言うと、あまり初めから専門用語を使って説明すると、初心者の人は取っつきにくく感じてしまうのではないかと思ったからです。
そういったわけで、私はあえてこれまで「純粋な喜び」や「意識」といった日常的な言葉を使ってきたのでした。
ですが、今回の記事はそもそも「中級者~上級者」向けの内容ですので、効率よく説明するために、専門用語で記述していきたいと思います。
まず、「純粋な喜び」について。
これはインドの不二一元論(アドヴァイタ)という学派において、「アーナンダ(至福)」と呼ばれているものです。
あらゆる感情が吹き消された「空(くう)」の中で、胸のあたりに感じられる「穏やかな解放感」を意味しています。
胸のあたりに感じられることから、「ハート」と呼ばれることもあります。
20世紀を代表する覚者であるラマナ・マハルシは、この「ハート」という表現を好んで使っていたようです。
それゆえ、ラマナ・マハルシの教えに触れたことのある人は、「ハート」という言い方のほうが、馴染みがあるかもしれません。
それに対して、私がこの連載の第三部で解説した「意識」は、不二一元論だと「チット」と呼ばれています。
これは、私たちが身体の五官を通じて受け取るあらゆる感覚や、思考や感情、さらには「自我」の働きなどまで含む、有形/無形の一切のものを観照している主体です。
ヨーガを学んだことのある人は、「プルシャ」という言葉でそれを教えられたことがあるかもしれません。
「チット」も「プルシャ」も、言葉としては違いますが、概念としては同じものを指します。
そして、この「チット=プルシャ」とは、私たちの存在そのものであり、深い瞑想の中で感じる「在る」という感覚の源泉です。
「何者でもない」けれども、確かに「在る」。
それが、「チット=プルシャ」というものなのです。
次の説明に行く前に、一度整理しておきましょう。
- 純粋な喜び
胸のあたりに感じられる「持続的で根拠のない幸福感」のこと。
不二一元論では「アーナンダ(至福)」と呼ばれ、探求の世界では「ハート」とも称される。 - 意識
有形/無形の一切のものを観照している主体であり、「私たちの存在の根源」そのもの。
不二一元論では「チット」と呼ばれ、古典的なヨーガ哲学では「プルシャ」と呼ばれている。
よろしいですか?
その他、もしもわからない用語が出てきたりした場合には、下記リンクから当ブログの用語集を調べてみてください。
このブログの中で使用している用語については、だいたい網羅できているはずです。
読んでいて道に迷った時は、ぜひ一度参照してみることを推奨します。
ということで、これ以降「純粋な喜び」については主に「アーナンダ(至福)」と表記するか、文脈によって感覚的に理解しやすそうであれば、「ハート」と表現するようにしていきます。
私が「アーナンダ」や「ハート」と言ったら、「『純粋な喜び』のことを言っているのだな」と理解するようにしてください。
また、「意識」についても、「チット」や「プルシャ」という表現を使っていきます。
こちらについては、基本的に「チット」で統一するつもりですが、「意識=チット=プルシャ」という関係性については、頭の片隅に置いておいてください。
それでは、本題に入っていきましょう。
◎「チット」と「アーナンダ」のどちらを先に悟るかは、人による
私たちが実践を続けていけば、どこかの段階で「チット(意識)」や「アーナンダ(至福)」についての理解が起こります。
しかし、「チット」と「アーナンダ」について理解する時、私たちは基本的に両方を同時には理解できないと思っておいたほうが良いでしょう。
というのも、人には適性というものがあり、このため、どちらを先に理解するかも人によって全く異なるからです。
ちなみに、私は「チット」の理解のほうが先行していました。
それは、私が真理の探求を始めた段階で、既に瞑想の実践を10年近く積んでいたためでもあったと思います。
当時は「『チット』について理解するため」というよりも、あくまで「メンタルケアの一環」として瞑想をしていたのですが、全くの経験ゼロの状態に比べると、やはりその違いは大きかったのではないかと思います。
結果的に私は「アーナンダ(至福)」よりも先に「チット(意識)」について理解することになりました。
なお、私にとって探求の道の師に当たる山家直生さんは、「自分は『アーナンダ(=ハート)』のほうを先に理解した」と言っていました。
山家さんはその当時、まだ探求などとはかかわりのない人生を送っていたそうなのですが、ある時、「なぜか訳もなく気分良く過ごせる」ということに気づかれたのだそうです。
その後、山家さんは紆余曲折を経てから瞑想の実践をするようになり、「チット」についても理解するようになりました。
このように、「チット(意識)」と「アーナンダ(至福)」の、どちらを先に理解するか人によります。
そこに「絶対的な優先順位」と言うようなものはありません。
ただ、はっきりしているのは、どちらか一方だけの理解では、全体として「危うさ」が残るということです。
では、それはいったいどんな「危うさ」なのか?
これから説明していこうと思います。
◎「私は在る」がもたらす無意味感から抜け出すためには、人はただ静かに在ればいい
まず、私の場合と同じように、「チット(意識)」について先に理解したケースを考えてみましょう。
以前の記事でも書きましたように、「チット」について理解すると、「『自我』というのは『虚構』である」という認識が生じるようになります。
【第12回】「瞑想」の第四段階《理論と実践》|「自我」は「虚構」に過ぎないと理解する
「自分」という存在の源は、あくまでも「チット」にあるのであり、「自我」は「チット」にくっついている付属物に過ぎないということがわかるようになるわけです。
同時に、「チット」について理解した人は、「私は在る」という感覚に留まることができるようになっていきます。
「私は在る」というのは、内側の思考や感情が静まり、「自我」さえもが沈黙する中で感じられる、純粋な「存在」の感覚です。
それは、内的な静けさの中で、無言のまま「在る」という感覚に留まっている状態とも言えるかもしれません。
そして、この「私は在る」という感覚に留まることが自然なものとなった時、「チット」の理解は達成されます。
しかし、まだ「アーナンダ(至福)」について理解していない場合、当人はここでひどい虚無感を覚える可能性があります。
というのも、「私は在る」という感覚そのものには、特に意味があるように思えないからです。
もちろん、「私は在る」の中に留まることができるようになったばかりの頃は、新鮮な感覚がするかもしれません。
「これが、あの『私は在る』なのか!」と興奮を覚える人もいるでしょう。
ですが、その感覚が自然なものになっていくにしたがって、当人はだんだんうんざりしてきてしまいます。
「『私は在る』ということはわかったけど、だから何なんだ?」と思ってしまうわけですね。
しかし探求の道について深く理解している師は、基本的にこういった疑問を持っている弟子に対して、「ただ『私は在る』ということの中に留まり続けなさい」と言うものです。
たとえば、覚者の一人であるニサルガダッタ・マハラジは、弟子たちに「『私は在る』という感覚にしがみつきなさい」という風に言っていたそうです。
でも、理解の途上にある実践者は、そこにどんな意味があるのか理解できません。
どうしても、「『私は在る』に留まって、いったいどんな意味があるんだ?」と思ってしまうわけです。
これは、探求の世界で「ドライ・ナレッジ(渇いた知識)」と呼ばれているものと関係があります。
たとえば、私たちが実践をおこなっていると、「知的な認識」が先行し、「感覚的な体験」がまだ訪れていない段階に差し掛かることが良くあります。
特に、瞑想の実践は、認識が「感覚的なもの」よりも「知的なもの」に偏る傾向があるため、なおさらそういうことになりやすいです。
そして、だからこそ、実践者は瞑想を続ける中で、自分の実践が無意味に感じられてしまうことがあるのです。
つまり、「~ということはわかったけれど、だから何?」と感じてしまうわけですね。
つまり、自分が獲得した知的認識が、「無味乾燥で渇いたもの(ドライ・ナレッジ)」のように当人には感じられるわけです。
私自身も、「チット」について理解した直後は、深い「無意味感」に囚われました。
と言うのも、「私は在る」ということを知的には理解していても、それが本当のところ何を意味しているのかまでは、理解することができなかったからです。
それゆえ、私は一時的に実践を続けることがひどく無意味に感じられてしまいました。
さらに悪いことには、「チット」を理解する過程で、「この世のこと」にも私は興味を失っていました。
たとえば、瞑想の実践を続けていくと、思考や感情というものは一時的な現象に過ぎないと理解されるようになっていきます。
「永遠に続く思考」も、「終わりのない感情」もありません。
どんな思考も感情も、時とともに変化して消えていきます。
それゆえ、瞑想を長く実践していると、好ましい思考や感情を追いかけることが虚しく感じられてきやすいです。
なぜなら、「そんなものを追い求めても、どうせ全ては失われるのだ」という認識が、実践者自身の内に芽生え始めるからです。
しかし、そうして世の中のあらゆることが「無意味」に感じられている時、それに代わるポジティブな「意味」のようなものを、実践者は見出すことができません。
「私は在る」ということを理解しても、それはあくまでも「知的な認識」でしかなく、自分を満たしてはくれないのです。
過去の私は、「私は在る」について初めて理解してからしばらくの間、生きていることが心底虚しくなってしまいました。
何年も瞑想の実践を真剣に続けてきた果てに、私は「生きていることの意味」が分からなくなってしまったのです。
これが「チット」についてだけ理解している時の「危うさ」です。
そこにおいては「知的な認識」がどうしても先行してしまうため、自分自身を満たしてくれるような「感覚的な体験」が欠けています。
それゆえ、実践者本人は「『私は在る』ということはわかったけど、何かが足りない」と感じるようになっていくのです。
そういう時、いったいどうしたらいいかと言うと、答えは非常にシンプルです。
「ただ静かに在りなさい」
あらゆる覚者が口をそろえて言うことはこれです。
つまり、ニサルガダッタ・マハラジが言うように、「黙って『私は在る』にしがみつき続けろ」ということです。
そう言われても、言われた当人は「そんなことしていったい何の意味があるんだよ」と、つい言い返したくなるのですが、この「無意味感」から抜け出す道はここにしかありません。
なぜなら、もしも当人が「私は在る」の中に留まり続けるならば、自然と「アーナンダ(至福)」が生じるようになっていくからです。
以前の記事でも書いたように、「沈黙」の中にずっと留まり続けていると、徐々に「自我」による束縛が破壊されていきます。
なぜなら、「自我」は「常に何かをしよう」とし続けるのに、当人は「無為」の中で沈黙し続けているからです。
もしも「沈黙」の中に留まるのなら、「自我」は次第にその力を失っていきます。
そうして当人は「もっと何かを成し遂げなければ!」という焦燥感や、「特別な個人として認められなければ!」という欲求から解放され、「自由」になっていくのです。
「別に何もする必要はないし、何者かになる必要もない」
このことが理解される時、自然と当人の中で「アーナンダ(至福)」が花開き始めます。
それは「自我」からの解放であり、当人はその「自由」の中で、「根拠のない至福感(アーナンダ)」を感じ始めます。
ここまで行くと、当人はもう「無意味感」に苛まれることはなくなります。
なぜなら、「私は在る」という感覚の中に留まることが、それ自体「至福」であると理解されるようになるからです。
このように、もしも「アーナンダ(至福)」より先に「チット」を悟ると、当人は一時的に「無意味感」を抱いて苦しむことがあります。
生きていることに「肯定的な意味」を見出すことができなくなり、時には「死への衝動」が起こる可能性さえあるでしょう。
ですが、もしもそのまま「私は在る」の中に留まり続けるならば、そのうち自然と「アーナンダ(至福)」に到達するようになります。
それは結局のところ「時間の問題」に過ぎません。
そして、このことが覚者には十分わかっているからこそ、彼らは一様に「ただ静かに在りなさい」とだけ弟子たちに伝え続けるのです。
◎「アーナンダ」について理解した後、「自我」の暴走を静める方法
次に、「アーナンダ(至福)」を先に理解した場合について書いていきます。
ただ、こっちのルートについて、私は自分で経験したわけではありません。
なので、ある程度は想像で書いていくことになることを、ご了承いただきたいと思います。
まず、「アーナンダ」について理解すると、「人は無条件に幸福を感じることができるのだ」ということを、当人は理解するようになっていきます。
「別に何も特別なことをしなくても、たとえ何者にもならなくても、自分は在るがままで幸福を感じることができる」
このような理解が起こるのが、「アーナンダ」の悟りです。
ですが、「チット(意識)」についてまだ理解していない場合、一つ大きな問題があります。
それは、「自我」による支配体制がまだ崩壊していないということです。
これがもしも「チット」を先に悟っていた場合、「『自我』はしょせん『虚構』に過ぎない」という理解が既に起こっているはずなので、当人は「自我」に振り回されなくて済みます。
つまり、「自我」を満足させるために社会的な成功をどこまでも追い求めたり、他人からの承認で心を埋めようとしたりしなくなっているはずなのです。
ですが、「チット(意識)」について理解する前に、「アーナンダ(至福)」についてだけ理解すると、「自我」はまだ大いに活動しています。
当人は、「もっと成功して名声を得たい」という想いに取り憑かれているかもしれませんし、「自分の存在を多くの人に認めさせたい」という欲求に衝き動かされているかもしれません。
こういった状態にある時に、もしも「無根拠な幸福感(アーナンダ)」を経験してしまうと、いったいどうなるでしょうか?
ひょっとすると当人は、「この『良い気分』を利用して、もっとこの社会でのし上がってやろう!」と思うかもしれません。
つまり、余計に野心へと火がついてしまうわけです。
さらに、人によっては、「こんな幸福感を感じられる自分は、『選ばれた人間』に違いない!」と考えて、人々を導こうとし始めるかもしれません。
しかしそれはあくまでも「自我(エゴ)」の肥大化であり、本当の意味での利他的な行為とは言い難いです。
なぜなら、そんな風に「自我」に操られたまま人を導けば、遠からずその人は、自分についてくる人たちのことをも支配しようとし始める可能性があるからです。
「自分の教えだけを信じろ」
「もっと自分を崇拝しろ」
「金銭や敬意をもっと寄越せ」
当人はいつか、そんな風に弟子や生徒たちに要求するようになってしまうかもしれません。
そのため、「自我による支配」から自由になっているかどうかということは、人を導く際の極めて重要な基準です。
もしも当人が己の「自我」を満足させることを優先する生き方にまだ留まっているならば、「利他的行為」は不可能です。
それはどうしても、「利他」を装った「微妙な搾取」のような構造を取ることになりがちです。
それゆえ、誰かを教え導く者は、まず己の「自我」をどうにかする必要があるのです。
このように、「チット(意識)」について悟る前に、「アーナンダ(至福)」について理解すると、「自我」が暴走してしまう可能性があります。
結果的に、当人はよりいっそう「自我」によって束縛されていくことになり、いつかは「アーナンダ」を感じることができなくなっていくでしょう。
と言うのも、そもそも「アーナンダ(至福)」というのは、「自我」から解放されることによって感じられるものだからです。
「自我」が「あれを目指せ」「こんな人間になれ」と命令し続けることをやめ、私たちがただ「在るがまま」の状態に留まる時、そのような「自我」からの解放感が、胸のあたりに「アーナンダ=ハート」として感じられるわけです。
それゆえ、もしも「自我」による支配が残ったまま「アーナンダ」を先に理解すると、その「至福感」はひどく脆く崩れやすいものとなってしまうのです。
これが、「チット(意識)」より先に「アーナンダ(至福)」を理解した場合の「危うさ」です。
しかし、そこから抜け出すための方法も、やはり「チット」を先に悟った場合と同じです。
「ただ静かに在りなさい」
本当に、この一言に尽きます。
きっと「アーナンダ」を理解したばかりの頃は、「自我」が様々な形で誘惑してくるでしょう。
「そんな風に『何もしないこと』の中で満足していないで、もっと多くのものを求めるべきだ」と「自我」は言ってくるはずです。
「あれを成せ」
「これを達成しろ」
「もっと優れた人間を目指せ」
「他者を押しのけ、勝利を求め続けろ」
「自我」はそう言って、当人を「無為」の中から引きずり出そうとします。
しかし、もしも当人が「アーナンダ(至福)」に留まることを大事にするなら、「『自我』の言うことを聞く限り、必ず最終的に苦しみがもたらされることになる」と、やがてその人は理解するようになります。
と言うのも、「自我」の欲求には限りがないからです。
どれだけ得ても「自我」は満足せず、どこまでも求め続けます。
そして、努力に努力を重ねた果てに、「これ以上はもう求めても得られそうにない」ということに気づいてしまうと、当人は深く絶望して苦しむのです。
確かに、「自我」を満足させようと必死になるなら、一時的な満足を感じることはできるかもしれません。
「ずっと目指していた目標」を達成できれば、その達成感から喜びを感じることもあるでしょう。
ですが、そういった喜びは全て一時的なものに過ぎません。
どんなに高い目標も、一度達成してしまえば過去のものとなります。
すると、当人はもうその「過去の目標」に満足することができなくなり、「さらに高い目標」を設定して、終わりなく走り続けることになってしまうのです。
「アーナンダ(至福)」に留まるということは、こういった「終わりのない円環」からの離脱を意味します。
何もすることなく、何者かになることもなく、ただ「在るがままの幸福感」の中に留まること。
それが、「アーナンダ」を理解した人にとっての、「ただ静かに在ること」です。
これによって、「自我」による支配は徐々に弱まっていきます。
「自我」の言葉に従って走り続けることよりも、「アーナンダ(根拠のない幸福感)」の中に留まることを優先していくことによって、「自我」による束縛が破壊されていくのです。
もしもこのルートで進んだ場合、私が第三部で述べた「瞑想の実践」を完全にスキップできる人もいるかもしれません。
実際、覚者の中には瞑想の実践を一切せずに悟りに到達してしまった人もいます(ラマナ・マハルシはそのうちの代表的な一人です)。
いずれにせよ、「アーナンダ(至福)」についての理解を深めていけば、「自我からの自由」も自然と実現するようになるということは、確かなことだと思います。
◎【終わりに】「チット」と「アーナンダ」の理解は、二つで一つ
以上のように、「チット(意識)」と「アーナンダ(至福)」のどちらか一方だけの理解では、まだどこか「危うさ」が残っています。
とはいえ、これら両方を同時に悟ることは、不可能とまでは言いませんが、おそらくそうとう難しいです。
なので、それぞれの人の適性に応じて、向いているほうの道から進んでいくのが良いのではないかと思っています。
そして、もしもどちらか一方だけでも悟ることができたなら、実践を続けていくことで、もう一方の理解も自然と訪れることになるでしょう。
ということで、今回は「チット」か「アーナンダ」のどちらか一方を既に理解できている「中級者~上級者」に向けて、「チット」と「アーナンダ」の関係性を説明しました。
「チット」だけを先に理解した人は、今はまだ「無意味感」に苦しんでいるかもしれません。
ですが、そのまま実践を続けることで、「アーナンダ(至福)」という「深い味わい」を感じられるようになっていくはずです。
また、「アーナンダ」だけを先に理解した人は、ひょっとすると「自我」の働きが一時的に強化されてしまって、自分の思考や感情に振り回されるようになってしまっているかもしれません。
しかし、そうして「自我にとっての喜び」を追求することに虚しさを感じ始めたら、当人は自分から「アーナンダ(根拠のない幸福感)」の中に留まることを選ぶようになっていくでしょう。
そして、その「アーナンダ」がもたらす心地よい満足感が、「自我」による束縛を破壊して、当人を「自由」にしてくれるはずです。
いずれにせよ、「チット」と「アーナンダ」は車の両輪のようなものであり、どちらが欠けても全体として完成しません。
「チット」がわかった。
「アーナンダ」を感じられるようになった。
そのように感じたとしても、「これで自分は『ゴール』に到達したのだ」と思うことなく、実践を続けていってほしいと思います。
「チット」と「アーナンダ」の両方が理解できて初めて、ようやく「一区切り」と言えます。
このことを、どうか忘れないようにしてください。
以上で、今回の記事は終わりです。
次回は、おそらくこの連載の最終回となるのではないかと思います。
何を書くかと言うと、「チット」と「アーナンダ」の両方を理解した後のことについてです。
たとえ「チット」と「アーナンダ」を理解しても、それだけでは探求の旅は終わりません。
まだ「最後の一歩」が残っているのです。
次回は、この探求における「最後の一歩」についての記事を書きていきたいと思っています。
では、また次回。
⇓⇓次回の記事です⇓⇓
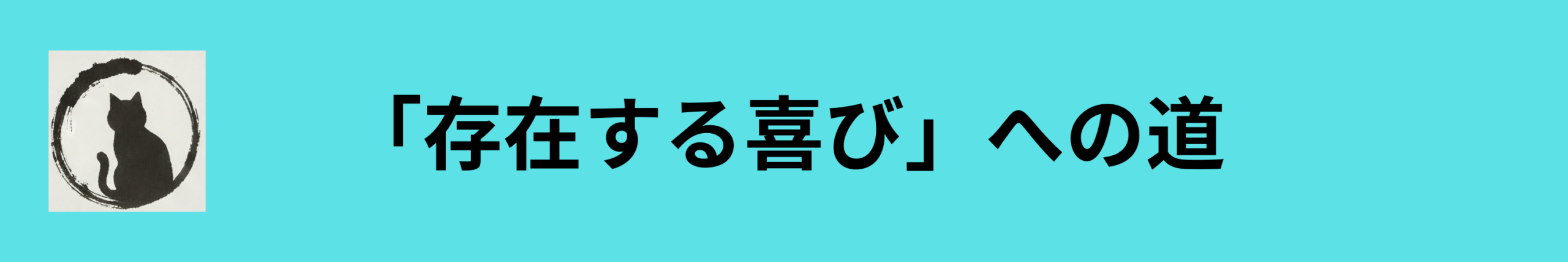

コメント