私は時々、「世界は実在しない」と言いますが、人によっては「それなら、どうしてお前はこんな風に世の中の他人に向かって文章を書いているのだ」と言いたくなるかもしれません。
これについて私は、「半分遊び」で、「半分本気」です。
まず、私の言う「世界は実在しない」の意味ですが、これは別にこの世の全てを否定しているわけではありません。
たとえば、私は今、自宅の部屋の中にいますが、私は自分がこの瞬間にパタパタとキーボードを叩いているノートパソコンの存在を否定はしません。
それは確かに「存在の一部」です。
ただし、私の家から歩いて十五分ほどのところに在るであろう、近所のスーパーの存在については、私に確かなことは言えません。
なぜなら、そのスーパーは、実際に歩いて行ってみたら消えてなくなっている可能性があるからです。
そのスーパーは局所的な天変地異で地底に没し去っているかもしれませんし、急な閉店が決まって取り壊されているかもしれません。
でも、ほとんど全ての人は、「スーパーは今この瞬間も存在している」と無根拠に信じているはずです。
もちろん、そのように考えることが、この社会で生きていくためには必要です。
それゆえ、私も他人と話す機会がある時は、あたかも「世界が実在している」と信じているかのように話を合わせます。
このブログを読みに来るような「踏み込んだ関係の人」ならいざ知らず、特にそこまで言う必要のない人に、わざわざ「いや、世界は実在していないよ」と言って聞かせたりはしません。
ただ、もしも私がスーパー(が在るであろう場所)に向かって歩いていくなら、自宅のノートパソコンは私にとって存在しなくなり、スーパーが存在し始めます。
これはいったいどういうことでしょうか?
覚者が普通の人と違うのは、「自分の心に映っているもの以外を信じていない」というところです。
普通の人は、「たとえ自分が見ていなくても、世界は存在し続けている」と信じています。
もちろん、さっきも言いましたように、その信念は社会生活上、必要なものです。
でも、覚者はそれを「生きるための方便」として演じはしますが、深いところでは信じていません。
覚者にとって存在するものは、「五官によって感じられるもの」と、「思考や感情などの内的な感覚」だけです。
そして、「それらの外側」に属するものについては、「在るのか無いのか確認できない」と思っています。
たとえば、今この瞬間の私には、目の前にノートパソコンが在るかのように見えています。
であるならば、「目の前にノートパソコンがあるかのように見えている」ということは、私にとって確認可能な事実であり、「それを見ている自分」の存在は絶対に否定できません。
そして、「そこ」にしか「足場」を持たないのが覚者です。
当人にとって、世界は「目に入る範囲」にしか生起しておらず、「目の届かない範囲」のことは知りません。
多くの人は、「自分が見ていようといまいと、世界はずっと存在しており、その中に自分という人間がいるのだ」と思っていますが、実のところは、順序が逆です。
本当は、「自分という『存在の根源』が何故か在り、その『意識』が照らし出した範囲にだけ『世界』が生起している」のです。
なんのこっちゃかわからんと思いますが、「世界が先に在って自分が後」というわけではないという話です。
実際、「自分(意識)」こそが「全ての始まり」です。
それゆえ、もしも「自分」が存在しないなら、「世界」はどこにも存在しません。
夢のない深い眠りの中では、「自分(意識)が存在している」という自覚が消失するため、「その間、世界は存在していない」と覚者は見ます。
でも、世の中の人たちは、「たとえ自分が熟睡していたって、地球も宇宙も存在しているよ」と言うはずです。
実のところ、この「思い込み」が壊れてしまった人間こそが、覚者です。
実際、生まれたばかりの赤ん坊の中には、「世界」という観念がありません。
当人の中では、「目に映るもの」だけが「全世界」です。
そこに「外側」は在りません。
でも、成長し、社会化していく過程で、「自分が見ていなくても世界は存在している」という「常識」を、私たちは刷り込まれていきます。
そして、この刷り込みが「魂のレベル」まで達した時、私たちは「世界が先に存在していて、自分はその中を動き回っている一人の人間に過ぎない」と信じ込むに至るのです。
とはいえ、たぶんいくら説明したとしても、あなたは納得できないと思います。
そもそも、もしも納得できるようなら、あなたは既に「自由」なはずです。
なぜなら、私たちの心を最後の最後まで束縛するのが、「世界」という観念だからです。
実際、「世界が自分の外側に実在する」と思うからこそ、人は苦しみます。
「世界」を変えようとし、変えられなくて苦悩するのです。
でも、もしも「世界とは自分の心の反映に過ぎない」とわかれば、「世界」を変えることをやめることができます。
その時は、ただ自分の心が「自由」であればいいだけです。
そうすれば、「世界」は私を「不自由」にすることはなくなります。
なぜなら、その人自身の「自由な心」が、常に「自由な世界」を創造し続けるようになるからです。
実際、「喜びに満ちた心」を持つ人は、日々を「幸せな世界」の中で暮らしています。
逆に、「苦しみに満ちた心」を持つ人は、たとえどれほど多くの物を所有していても、「不幸な世界」の住人です。
「幸福」も「不幸」も、「自分自身の創造物」です。
私たちは、「自分自身で創り出した世界」にしか住むことができません。
だからこそ、もしも心が「自由」なら、その人の世界に「苦しみ」が生じる余地はなくなるのです。
ただ、そうなると、「他人の存在」が問題になるかもしれません。
たとえば、「私の世界」の中には、時折「他人」が現象してくることがあります。
買い物に行くと、スーパーの店員さんが「私の世界」に現れてきますし、散歩して道を歩いていると近所の隣人が現れます。
でも、スーパーや散歩から帰ってくると、そういった「他人」はみんな消えてしまいます。
その時、「他人」は存在しません。
そういう意味で、「他人」というのは、「私」自身とは全く違う在り方をしているのです。
念のために言っておきますけれど、ここで言う「私」というのは、「湯浅和海」のことじゃありませんからね?
「私」が今の時点で「湯浅和海」であるのは、あくまでも「たまたま」のことです。
もしも「私」が記憶喪失にでもなった場合、「私」は「湯浅和海」として生きていくことがきっと難しくなることでしょう。
でも、その時もやっぱり「私」は「自分」です。
たとえ何者になろうとも、「自分」でなくなることだけはあり得ません。
「私」には「自分」でなくなることが絶対にできないのです。
しかし、「他人」の中にも同じような「自分(=意識)」が在るのかどうかは、私には確認しようがありません。
なぜなら、もしも私に特殊な能力があって、その「他人」の中に乗り移ることができたとしても、そうやって乗り移った時点で、今度はその「他人だった人」が「新たな自分」になってしまうからです。
言っていることはわかりますか?
私には「自分」であることしかできません。
これは「絶対」です。
そして、そうであるがゆえに、私には「絶対」に、「他人」が「自分」を生きているのかどうかを確かめることができないのです。
これについては、哲学的には「語り得ないこと」に属する問題なので、ウィトゲンシュタインという哲学者は「最終的には沈黙するしかない」と言っていました。
なので、たぶん私は今、「意味の無いこと」を言っています。
しかし、だからこそ私はそれを「半分遊び」だと言うのです。
私にとって「他人」に何かを伝えることは、最初から「意味の無いこと」です。
でも、私の中には「伝えずにいられない想い」が在ります。
だから、「無意味だ」とわかってはいながらも、私はそれを言うのです。
しかし、同時に「半分本気」でもあります。
なぜなら、私は「他人の意識」が視覚的に見えるようにも感じられるからです。
私は過去に呼吸法や瞑想法の実践によって、「他人の意識状態」が見える(ような気がする)ようになりました。
私の目には、「意識的に生きている人」は、頭のあたりがなんとなく光っているように見えます。
逆に、「眠り込んだまま機械的に生きている人」は、頭のまわりがなんとなく暗くなっていて、雲みたいなものが取り巻いているように見えます。
なので、ひょっとしたら、「『意識』というものの本質は『光』なんじゃないか?」という感覚が、私にはあるのです。
そうであるならば、「他人の意識」について、その存在を論理的には証明できないけれど、「光って見える」以上、「それは実在する」と前提してみるのも面白いと思うのです。
私には確認しようがないですが、他人も「意識」を持っていて、「自分自身」を生きているのだと、とりあえず前提してみるわけです。
そうなると、「いっちょ本気で『他人の意識』を覚醒させるために言葉を紡いでみるか」という気分にもなります。
これが、私の残り半分に当たる「本気成分」です。
いずれにせよ、私は「他人の意識」について「在るかもしれないし無いかもしれない」と思っています。
だから、「他人に伝える」ということについて、「半分本気」ではありますが、残り半分は「遊び」です。
私の文章を読んで、「どこにも力が入っていない」と言ってくれた人がいましたけれど、それはたぶんこのためです。
私は「100%本気」じゃないんです。
半分は「遊び気分」で書いています。
それは、自分がもともと「無意味」なことをしているという自覚があるからであり、その上で、「でも、せっかくやるならとことん楽しもうじゃないか」という風に軽く捉えているからだと思います。
また、これはおそらく、私が「世界の実在性」を信じていないためでもあるでしょう。
多くの思想家や革命家は、「世界が実在する」と深く信じ込んでいます。
だからこそ、その「世界」を変えようとして躍起になるのです。
でも、私にとっては「世界」は実在しないので、「世界を何が何でも変えないといけない!」というような「力み」が生じる余地ありません。
私からすると、最初から全部、「どっちでもいい」のです。
「起こるべきこと」は起こるでしょうし、「起こる必要のないこと」は起こりません。
私はただ、そんな「天地の移り行き」をボケーっとしながら見ているだけです。
それを「変えよう」だとか、「自分の生きた証を残そう」だとかいったことは、本当に「どうでもいいこと」です。
私はただ、何が起ころうが起こるまいが、「深い呼吸」を保って生きていくだけです。
私はそんな風に踊り続けています。
「踊ること」に別に意味なんてありません。
意味なんて考えず、「与えられた命」が続く限りは、ただ踊り続ければいいだけです。
実際、村上春樹もこう書いています。
「踊るんだよ」羊男は言った。「音楽の鳴っている間はとにかく踊り続けるんだ。おいらの言っていることはわかるかい?踊るんだ。踊り続けるんだ。何故踊るかなんて考えちゃいけない。意味なんてことは考えちゃいけない。意味なんてもともとないんだ」
村上春樹、『ダンス・ダンス・ダンス』、講談社文庫
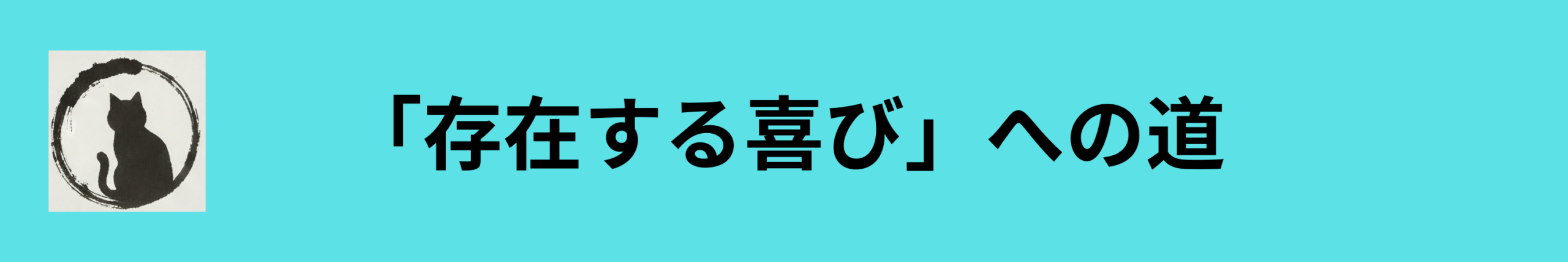
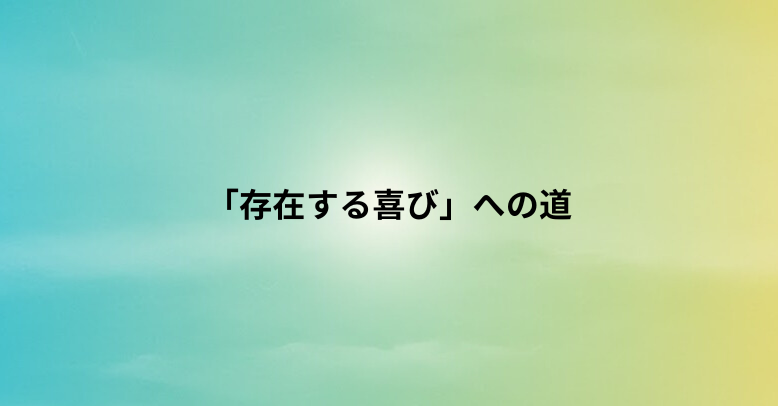
コメント