「数字にならないもの」というのは、ほとんどの人には理解できないのではないかと思うことがあります。
たとえば、私は昔、まだ十代の若者だった頃にダンスを稽古していたのですが、当時の私は「数字にできること」しか理解できませんでした。
その頃の私はブレイクダンスからクラシックバレエまで幅広く稽古していたのですが、「ブレイクダンスの難しい回転技を『何回転』継続できるか?」とか、「バレエのレッスンでおこなうターンを最高で『何回転』回れるか?」とかいったことしか眼中にありませんでした。
そう言えば、あるプロのバレエダンサーが言っていたのですが、世界中、どこのバレエスタジオに行っても、「必ず見る光景」があるそうです。
それは、「レッスン生全員が一斉に黙々とターンの練習をし始める光景」です。
このターンをバレエ用語では「ピルエット」と言うのですが、そのバレエダンサーはこういった光景を見ていると、「ピルエット教信者」という言葉が浮んできたそうでした。
かく言う私自身も、過去は「ピルエット教」の信者でした。
なぜなら、自分や他人のダンスの価値を「ピルエットを何回転できるか」で判定していたからです。
ちなみに、当時の私の最高回転数は五回転でしたが、プロのトップクラスは安定して九回転とか十回転することが可能でした。
そして、当然私自身もそういう方向性を目指して、時間さえあるとスタジオにこもってひたすら「ピルエットだけ」を練習していたものです。
でも、私のそんな「閉鎖的な価値観」をぶち壊した人がいます。
それが、私のダンスの恩師である桜井郁也さんでした。
私は本を書く度に、毎回この桜井さんの名前を出しているのですが、それだけ絶大な影響を受けた人であるということです。
実際、桜井さんのダンスは不思議でした。
決して何回転も回ったりしないし、脚を高く上げるわけでもなく、華麗にジャンプするわけでもありません。
そこには「わかりやすい技巧」は一切存在しなかったのです。
彼はユラユラと舞台上に現れて、そのままジッと佇んでいたかと思うと、突然「グシャ!」と体勢を崩して転んだりしていました。
私はそれを初めて観た時、「なんじゃこりゃ?」と思いました。
正直言って、当時の私はそれを「ダンス」だと思わなかったのです。
また、桜井さんの公演は決して広い劇場では行われず、彼はいつも地下にある小さな部屋を借りて、そこで二十人にも満たない観客を前に踊っていました。
そして、薄暗い地下の小部屋で、彼は一人きりで一時間以上踊り続けていたのです。
普通のダンスの作品が、何人ものグループで数分だけ踊って一区切りつけるのに対して、彼はたった一人で一時間以上も舞台の上に立ち続けていたわけです。
並大抵の集中力と精神力では、こんなことは不可能です。
しかし、彼のダンスの価値をまだ理解できなかった当時の私は、それを退屈に感じてよく眠くなっていました。
なぜなら、そこには「きらびやかなライトによる演出」もなければ、「目を見張るような超絶技巧」もなかったからです。
彼はただ、「自分の身体の存在感」だけで、一時間以上ものあいだ、観客の視線を一手に引き受けていたのです。
桜井さんに出会ったばかりの頃、私は自分のダンステクニックに自信を持っていて、いささか天狗になっていました。
それで、特にこれといって「技巧的なこと」をしようとしない桜井さんのことを内心で見下していて、「この人に自分のテクニックを認めさせて、上限関係をわからせてやる」と思っていました。
今思えば、実に浅はかで狭い了見でしたが、私にはその時、桜井さんが「何の技巧も身に着けていないのに人前に立っている勘違いおじさん」に見えていたのです。
しかし、私がいくらダンスを見せても、桜井さんはビクともしませんでした。
当時の私は自分の技巧の限りを尽くし、「桜井さんをうならせてやろう」と思っていたのに、桜井さんはどこ吹く風で、ちっとも心が動かされている様子がなかったのです。
桜井さん以外のダンス教師は違いました。
私が踊れば決まって誉めてくれましたし、人によっては、私を見本として他の生徒の前で踊らせることもあったほどです。
でも、桜井さんだけは、私がいくら必死に踊っても、眉一つ動かさなかったのです。
そしてある時、「ダンスが説明臭い」と桜井さんは私に言いました。
そんなことを言われたのは、生まれて初めてでした。
でも、今にして思えば、確かにそうだったのです。
当時の私のダンスは、決して「表現」ではありませんでした。
私はしょせん、「自分に何ができるか」について、ダンスを通して「説明」しているだけだったのです。
当時の私は、「自分のスペック」をカタログにして見せるように踊っていました。
そして、それを見て多くの人は「感心」して称賛しましたが、「感動」した人がいたかどうかは、はなはだ疑問です。
世の中の多くの人は「感心」と「感動」を混同していますが、両者は全く違うものです。
実際、超絶技巧を誇るピアニストは、観客を「感心」はさせるでしょうが、だからといって「感動」させることができるわけではありません。
むしろ、技巧自体は未完成でも、懸命に演奏している人の姿は、それを目の当たりにした人の心を強く動かすことがあります。
つまり、人の心を動かす際には、「技巧的な完成度」は必須事項ではないのです。
そもそも、「感心」している時、その人は「今までの価値観」の中に安住しています。
でも、「感動」している時、その人は「今までの価値観」を強く揺さぶられ、一種の「目眩」を感じているものです。
それまで「当たり前」だと思っていた物事がひっくり返され、「自分自身」がリアルタイムで新しくなっていくような衝撃を受けた時、私たちは本当の意味で「感動」するのです。
かつて、バレエのスタジオで「ピルエットターン」を機械的に練習していた私は、「必死」ではありましたが、心の中では何も感じていませんでした。
その時の私は、ただ「より多くの回転数」という「数字」だけを追い求めており、その過程は「単なるコスト」としてしか見ていなかったのです。
私は「回ること」を楽しんだこともなければ味わったこともなく、人前で踊る時は、「他のダンサーより多い回転数」という「数字」に寄りかかって、そこに「自分の存在」を賭けませんでした。
それゆえ、踊れば踊るほど、私の心は渇いていきました。
なぜなら、当時の私は「もっと多くの回転数」という「未来の結果」だけ求め続け、「今の練習」はいつも「それ自体はつまらないもの」としてひたすら消費され続けていたからです。
私にとって「ダンス」は、「他人を感心させるための説明道具」に成り下がり、「日々の稽古」は「自分のスペックを磨くための必要経費」に過ぎなくなっていました。
しかし、いったいここのどこに「表現」があったでしょうか?
私は「虚しさ」を内に抱えたまま、「よく回る機械仕掛けのロボット」になることを、必死で目指していただけだったのです。
ある時、桜井さんはこんな風に言っていました。
「何かをとても深く感じている人がいたとしたら、その姿は、きっと美しいと思う」と。
今なら、その意味がわかります。
「何をしているか」が大事なわけではなかったんです。
「何を感じているか」が大切だったんです。
でも、当時の私は頭でっかちで、「数値化して説明できる物事」しか理解できませんでした。
だから、「内側で主観的に感じているだけなんて、そんなの単なる『個人的な思い込み』に過ぎないじゃないか」と思いました。
「そんなものが『凄いもの』なわけがない」と思っていたんです。
でも、本当は話が逆でした。
たとえどれほど「技巧的に素晴らしいダンス」を踊れたとしても、当人の内側が「空虚」なら、観客は無意識にその「空虚さ」を感じ取ります。
そこにおいて、パフォーマーの「空虚さ」や「心の渇き」は「技巧というヴェール」の向こう側に「お行儀よく」隠されるわけですが、それでも、ちゃんと観客には伝わるのです。
もちろん、観客の側が頭でっかちになっていれば、「凄いパフォーマンスだった」と「感心」するでしょうけれど、心を強く揺り動かされることはありません。
パフォーマー自体も心が動いておらず、観客側も心が動いていない。
つまり、そこには「死んだ者」しかいないのです。
ある時、桜井さんはこうも言っていました。
「僕の目標の一つはさ、指先の動きだけで空間を歪ませることなんだよ」と。
私はその頃には、徐々に桜井さんの「凄味」を理解しつつありました。
「指先の動きだけで空間を歪ませる」ということは、もはや「テクニックの次元」では不可能です。
それは当人の「存在」そのものの峻烈さや深さ、当人がそこに賭けている「魂の重さ」無しには、成し遂げることが不可能なのです。
「踊る」ということを「自分の身体的スペックを説明することだ」と、いつの間にか勘違いしていた過去の私は、桜井さんのおかげで救われました。
「表面的なテクニック」だけを追い求めて渇き続けていた私の心に、「感じること」という潤いをもたらしてくれたのは、他でもない桜井さんだったからです。
たとえば、ある日の桜井さんの舞踏のクラスでは、「回ること」がテーマになりました。
そして、「回りながら身体にどんな感覚がするか」を味わうことが、そこでは実践されていたのです。
私は、形を整えてバレエの「ピルエット」をしたりせず、まるで幼い子どものようにグルグル回ってみました。
すると、そこには「目眩」の感覚があり、身体が風を切る感覚がありました。
そうして、必死になって回っているうちに段々バランスを崩して転んでしまいました。
でも、それは「失敗」じゃなかったんです。
転んだ先には「床の感触」が私のことを待っていて、「自分の身体の重さ」を地球に向かって預けていると、私はどこか安心した気持ちになることができました。
「成功も失敗もない。全てはダンスなんだ」
その時に私は、漠然とそう感じ始めたのです。
「数字で理解できるもの」を追いかけるのは簡単です。
より多くの年収や、より多くのフォロワー数を追い求め、年収の高い人やフォロワーの多い人に「感心」するのは簡単です。
難しいのは「感じること」です。
「自分の魂の重さ」を量り、「他人の感情の揺らぎ」に心を震わせることは難しいのです。
でも、私たちのことを本当に満たすのは、決して「数字」ではありません。
むしろ、「数字」は私たちの内側にある「渇き」を助長します。
そうして人は、どこまでも「より大きな数字」を追いかけ続けるレースに夢中になって、自分を擦り減らし続けるのです。
言葉を書く時、「自分の知っている知識」をずらずら並べて、「自分のスペック」を説明するだけの書き手がこの世には居ます。
そして、そういう文章を読むと、多くの頭でっかちな読者たちは、「この人はとてつもない知識の持ち主だ!」と「感心」して、その人の言葉についていきます。
でも、実際にはそういう書き手の内側は「空っぽ」で、「自分の感じたこと」を書いているわけではなく、ただ「本で読んだ他人の考え」を口真似しているだけだったりします。
口真似ではない「自分の言葉」を獲得した時、人は初めて読み手の心に向かって語ることができます。
それは、知識人たちの言葉のように整ったものではないかもしれませんし、文献的な裏付けだって、ろくに存在しないかもしれません。
でも、その言葉には、紛れもなくその人自身の「血肉」が通っています。
それゆえ、たとえ数千人の「頭でっかちの人々」がそこに価値を見出さずに素通りして行ったとしても、目には見えない「魂の重さ」を感知できる少数の人々は、その人の言葉の前で足を止めるでしょう。
「大事なもの」というのは、いつも「目には見えない」のです。
それは、「心を通して感じるしかないもの」です。
そして、多くの人々が心を失っているこんな時代だからこそ、私は「目に見えないもの」をこそ大事にして生きていきたいと思っています。
かつて桜井さんが私に「目に見えないもの」の大切さを思い出させてくれたように、誰かの心を開きたいのです。
そしてそれがたぶん、私が過去に桜井さんから託された、「私の仕事」だと思うのです。
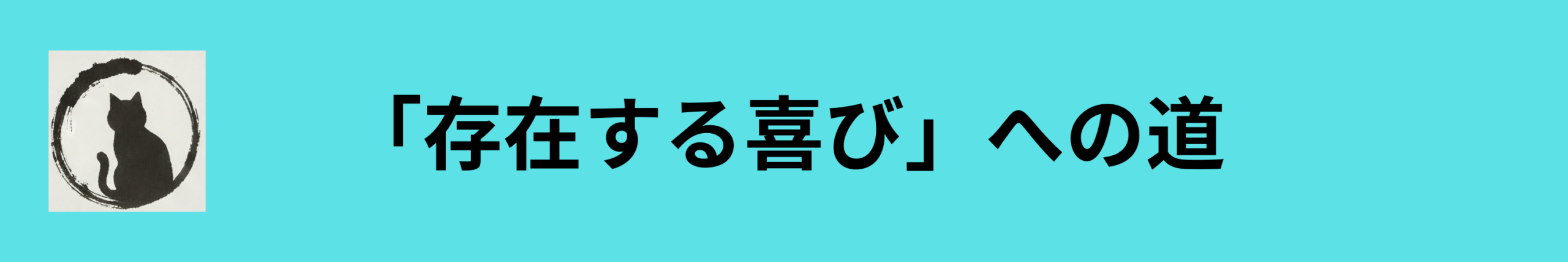
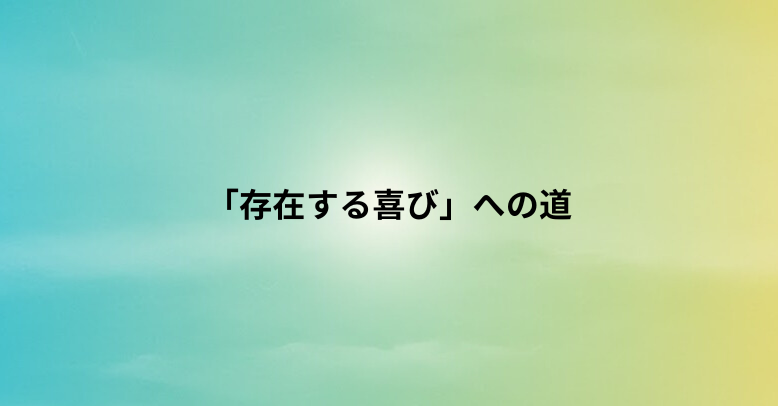
コメント