現在、道元の「現成公案」のフレーズを個人的に解説する本を書いているのですけれど、後年の道元は、「現成公案」で書いていたことと反することをしていたように私は感じています。
そもそも「現成公案」というのは、「目の前に現れている真理」という意味です。
「現成」というのが、「目の前に現に現れている世界」のことであり、つまりは私たち自身の「日常生活」です。
そして、「公案」というのは、「証明不要な動かせない真理」のことであり、これは数学や論理学の「公理」をイメージするとわかりやすいかもしれません。
たとえば、ユークリッド幾何学では、「重なる図形は合同である」とか、「全体は部分より大きい」とかいった「公理」がありますが、これらは「正しいか否か」を証明することができません。
むしろ、こういった「公理」を前提にして、全ての証明がなされます。
つまり、「公理」というのは、それ以上さかのぼれない「絶対的な前提」であり、「全ての出発点」なのです。
つまり、「現成公案」という言葉は、「日々の生活の中に『絶対的な真理』は現れているのだ」という意味になります。
そのような「日常の中の真理」こそが、私たちにとって「全ての出発点」であり、「動かすことのできない前提」でもあるわけです。
普通、「修行」というと、日常生活を離れて「どこか遠く」を目指すもののように思いますけれど、道元からすると「それは違う」ということになります。
実際、「仏性」は日常の中で表現されており、行住坐臥、一挙手一投足の中で活き活きと飛び跳ねています。
だからこそ、道元は「修行は本来必要ではない」という立場を取っています。
むしろ、「『悟った』という意識を捨てて、『現成=日々の生活』の中で、『自身の真理』を生きていけ」と語っているのが、「現成公案」という文献なのです。
しかし、それにもかかわらず、後年の彼は「坐禅の実践」を重視していきました。
あらゆる「作為」を落とし、「悟ろう」という思慮も捨てて、「ただ坐ること」を重んじたわけです。
これを道元の曹洞宗では「只管打坐」と言っています。
「只管」というのは、もともと中国語で、これを日本語に訳すと「ひたすら」という意味になります。
「打坐」というのは、「坐る」という語を強調したものです。
「打」という漢字は、「坐」という字を強める役割を果たしており、いわば「ぶん殴る」の「ぶん」みたいなものです。
つまり、「只管打坐」というのは、「ひたすらどん坐る」みたいな意味です。
そして、「そのように徹底的に『坐る』という在り方自体が、『仏性』の表現なのだ」と道元は言います。
ちなみに、私自身は、これに半分だけ賛成です。
実際、作為や思慮を落として坐っていると、「内側の仏性」を自覚することができるようになります。
この「内側の仏性」は、インドのヴェーダ聖典が「チット(意識)」と呼んだものであり、ヨーガの経典が「プルシャ」と呼ぶものです。
現代風に言えば、それは「観照者」のことですが、「『本当の自分』は『観照者』だったんだ」と自覚することをもって、禅宗では「見性成仏」と言っています。
これは、「『自分の本性』は自我とか身体ではなくて、『仏性』だったんだ」ということを、初めて理解する瞬間を指しています。
つまり、「見性」というのは「知的な理解」ではなく、あくまで「体験的な理解」なのです。
これは、それまで「自分」だと思っていたもの(自我とか身体とか)が、実は「自分の本体」ではなかったと、「感覚的に」気づく体験です。
逆に、もしこの「見性」を得る前に、頭の中で「『自分の本性』は『仏性』なのだ」と繰り返し唱えたとしても、何の意味もありません。
それは意識の表層なら変えることができるかもしれませんが、当人は心の奥底で、その言葉を信じていないでしょう。
それゆえ、当人は何かの拍子に「でも、本当に『自分の本性』って『仏性』なんだろうか?」という疑いに囚われてしまうはずです。
そういった迷いや疑いから「自由」になるためには、自分自身の目で確かめるしかありません。
つまり、頭の中で「自分はもともと『仏』なのだ」という思考を繰り返すのではなく、そういった思考そのものが完全に静まった時、そこに「何」が残るのかを確かめるのです。
そのためには、確かに「只管打坐」は有効な「方便」です。
他にも「役に立つ方便」はいろいろありますが、「只管打坐」はその中でもかなり有効なほうだと思います。
実際、いかなる瞑想のテクニックも使わずに、「ただ坐る」というシンプルな行を実践することによって、人によって「見性」を得ることができるでしょう。
でも、「見性」を得ることができたのなら、もうそれ以上坐っている必要はまるでありません。
むしろ、そこから先は「坐ること」を捨ててしまって、「日々の生活=現成」の中でこそ、瞑想を実践すべきです。
なぜなら、「坐る」ということに固執していると、それによって心身が束縛されてしまうからです。
もちろん、「悟り」を開いた直後のゴータマ・ブッダのように、しばらくの間、その「法悦」を味わいたくてひたすら坐ったりするのは、「個人の自由」だと思います。
内側に止められない衝動があって、「坐りたくて仕方ない」という人を止めるつもりは私にはありません。
ただ私は、「『坐りたい』という内的な動機を持っていない人にまで、『ひたすら坐ること』と求めることは、かえって相手の中に『余計な束縛』を生むことになる」と言いたいだけです。
「見性」を一度でも得たならば、その人はもう「仏性の味」を「自分の舌」で知っています。
だったら、後はその「味」を、その人自身の「日常=現成」の中で表現していけばいいだけです。
歌いたい人は歌ったらいいし、踊りたい人は踊ることによって「自分の仏性」を表現することができるでしょう。
もちろん、道元自身が「坐りたい」と言うなら、私はそれを止めませんけれど、だからと言って、万人に「坐ること」を勧めようとすることには、私は反対です。
なぜなら、全ての人が、「坐禅」によって「仏性」を表現するようには創られていないからです。
だからこそ、料理をすることで「仏性」を表現するほうが合っている人だっているし、絵を描くことで「仏性」を表現するべく生まれてきた人だっています。
「見性」を得た後は、もう「坐ること」になんてこだわらず、各人がそれぞれの仕方で「仏性」を表現したらいいのです。
ただ、晩年の道元はさらにここから、永平寺に集まった数百人の弟子たちを統率するために、「永平清規」というものを書いています。
「清規」というのは、修行者たちが守るべき「規則」のことです。
ここには、実に事細かく「こういう場合にはこうすべし」という決まりごとが書き込まれています。
「食事の場面で鉢を持つ手の形はこう」とか、「僧堂に入る時は左足から入る」とか、さらには、「トイレの後の手洗いの仕方」まで手順が全部決まっています。
そうしないと集団生活を維持できなかったのかもしれませんが、ここまで「ガチガチ」に固められてしまうと、「規則」によって心身が束縛されてしまいます。
もちろん、そうやって「日々の全て」の振る舞いを意識的に統御することで、「マインドフルネス」の実践にはなるかもしれません。
でも、それが意味を持つのは、あくまで「見性」を得るまでです。
「仏性の味」がわかったら、むしろ「決まった形」を守ることは、その人を縛る制約になっていしまいます。
道元がかつて「現成公案」の中で書いていた「日々の生活の中で『真理=公案』を生きること」は、そんな「窮屈なこと」ではなかったはずです。
とはいえ、数百人規模の集団を維持するためには、こういった「仕掛け」も必要だったのかもしれません。
「規則」をきっちり設けていないと、集団がバラバラになってしまうと道元は思ったのかもしれません。
でも、私はこういう「規則」を目にするたびに、いつもOSHOのコミューンの話を思い出します。
インド人の覚者であるOSHOのコミューンでは、実に様々な人たちが共同生活を営んでいたようです。
私はOSHOが講話をおこなう様子をDVDで観たことがありますが、彼が講話をおこなっているホールには何百人もの人たちが集まっていました。
つまり、OSHOのコミューンは、永平寺と同等以上の規模を持っていたわけです。
しかし、OSHOは規則について口うるさく言ったりしていなかったようです。
コミューンの中では、自然とそれぞれの人たちが役割分担をして、日々の生活を営んでいたらしく、そこで多種多様な瞑想の技法が実践されていました。
OSHOは、道元のように「坐禅だけが絶対なのだ」と主張したりせず、「役に立つと思うものは何でもやりなさい」という方針だったため、ボディワークや精神療法、占いや自然農法など、それぞれの弟子たちが自分の知識や技術を持ち寄って、互いにそれらを共有し合っていたのです。
それだけ「カオスな状態」だったにもかかわらず、OSHOコミューンは別に崩壊しませんでした。
きっとそこには、「自分の自由」と同じだけ「他者の自由」を尊重する気風があったのでしょう。
しかも、その共同体は、OSHOという「中心人物」がこの世を去った後も、インドのプネーで「メディテーション・リゾート」として存続しているようです。
私は実際に現地に行ったことがないのであくまで想像ですけれど、そこには「混沌とした秩序」が存在しているのではないかと思います。
でも、私たちは「秩序」を作ろうとする時に、いつも「混沌」をすべて排除してしまおうとします。
あかたも、「正しいもの」だけを残して、「悪しきもの」を排除するように、です。
しかし、実際には「陰」と「陽」とは一つです。
私たちの存在は、「善」だけで創られているわけでも、「悪」だけで創られているわけでもありません。
私たちはいつも「その両方」です。
道元にだって、それはわかっていたはずです。
でも、私は「現成公案」を書いた時代より後の道元の中に、そういった「トータルな視点」を見出すことができません。
彼は「悪しきもの」を切って捨ててしまい、「正しきもの」だけを囲い込んでしまったように、私の目には見えます。
私は今、道元の「現成公案」についての解説本を書いていますけれど、「現成公案」を書いている時の道元と、それ以降の著述をしている道元が、私の中では、いまいち一致しません。
「いったい彼に何があったのだろう?」と思ってしまいます。
あるいは彼も、「現成=人生」というものの「途方もなさ」に圧倒されてしまったのかもしれません。
その「理解不能性」に手を焼いて、「正しさ」という檻に中に、「生のダイナミズム」を閉じ込めようとしたのではないかと、私には思えます。
いずれにせよ、どんな賢者も、どんな哲人も、「理解できない」という状態に踏みとどまり続けるのは容易なことではありません。
それゆえ、誰もが「自分で作った砂上の楼閣」の中に立てこもり、必死で自分を守ろうとします。
ただ、私自身はできるだけ、そういったことはしないでいたいと思っています。
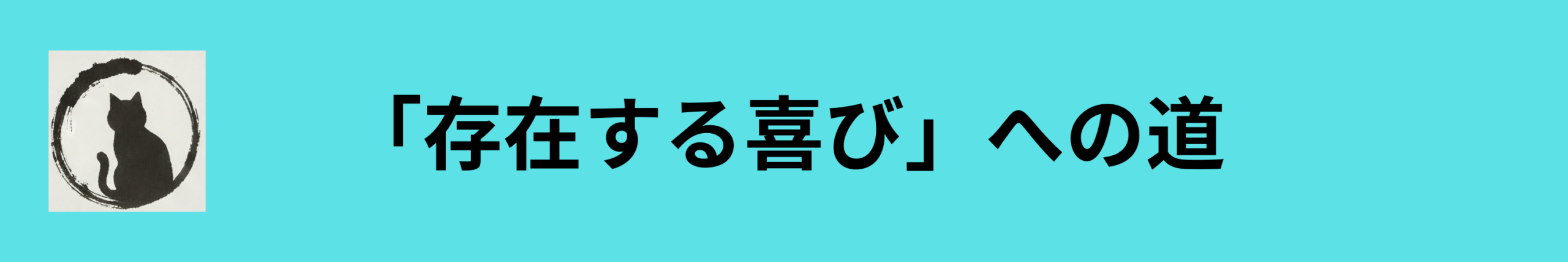
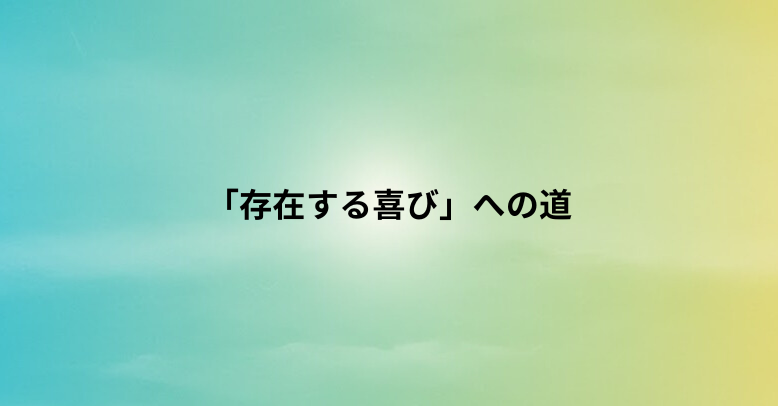
コメント