「真理」を悟るということを、「賢くなること」だと思っている人はいませんか?
つまり、「『真理』を悟ると、常人には計り知れない叡智をその身に宿すようになるに違いない」とイメージするわけです。
でも、本当のところはどうなんでしょうか?
実のところ、「知的である」ということは「真理」を悟る上で必須の項目ではありません。
たとえ「無学」な人であっても「真理」を悟ることは可能です。
逆に、多くの「知識」を蓄えながら、「真理」について「無知」であるということも大いにあり得ます。
今回は、探求の世界において、本当の意味で「知っている」ということがどういうことなのかについて説明してみたいと思います。
「自分がついていくべき師」が誰かわからなくて途方に暮れてしまっている人は、「真理」を理解している人としていない人を見分ける仕方が、わかるようになるかもしれません。
ぜひ、参考にしてみてください。
では、始めます。
◎一つ目の「知識」は「頭に取り入れた情報」である
まず、一般に「知識」と呼ばれるものには二種類のものがあるということを理解してください。
そのうちの一つは、「頭に情報が入っている」というものです。
「記憶している」と言い換えてもいいかもしれません。
たとえば、「日本の首都は東京である」とか、「徳川家康が死んだのは何年である」とか、そういったことを聞かれて答えられるのであれば、それは一般に「知っている」と言われるのではないかと思います。
この方向で「知識」を蓄えようとする人は、たくさん本を読んだり、偉い学者の先生に弟子入りして勉強したりするのではないかと思います。
そうやって「知識」を蓄えることで、学術用語や難解な概念を使いこなすようになる人もいるでしょうし、論理学をマスターすることで弁論の術を身に着ける人もいるかもしれません。
そういった人の話というのは、多くの人の耳には「説得力がある」かのように響きます。
そもそも、こういった人々はまず見た目にも頭がよさそうな人であることが多いですし、「知識人」という肩書を持っていることもあります。
それゆえ、世間の人は「この人の言うことは間違いない!」と信じて耳を傾けます。
つまり、「この人の話を聞けば、自分も『頭のいい人間』になれるかもしれない!」と期待するわけです。
このような形で世間に影響を与えるタイプの人たちが身に着けているものが、まず一つ目の種類の「知識」です。
多くの人は、この手の「知識」をたくさん身に着けることによって、「賢くなれる」と信じています。
そして、誰もが他人から「賢い」と思われたがっているがゆえに、人々はこうした「知識」を追い求め続け、それを提供してくれる「知識人」たちのことを重宝することになるわけです。
◎二つ目の「知識」は「自分の体験を通した理解」である
次に、二つ目の「知識」について説明します。
それは「自分自身の体験を通した理解」です。
たとえば、お味噌汁の出汁を取る時は、既製品の粉末出汁を使うより、かつお節や昆布を使って取ったほうが、香りも風味も深みが出ます。
でも、それを「単に情報としてだけ知っている」のと、「実際に自分で試して知っている」のとでは、当人の語り口は微妙に違ってきます。
「情報としてだけ知っている人」というのは、それを誰かから聞いただけの人です。
自分自身では試しておらず、「本当にそうなのか」を知りません。
それゆえ、他人から「詳しく説明して」と言われても、うまく答えることができなかったりします。
「聞いたところによると、どうもそうらしいよ」というくらいのことしか言えないわけです。
それに対して、自分自身で実際に試した人は、「本当のところどうなのか?」ということを我が身をもって知っています。
そして、自分で試す過程において、試行錯誤をした経験を持っているので、「実際に試す時にどういうことに注意したらいいか」についても、わかっている場合が多いです。
だから、他人から質問された場合も、相手の知りたいことに合わせて柔軟に答えることが可能です。
なぜならその人には、「相手がどこでつまづいているのか」ということを理解することができるだけでなく、「そこからどう抜け出したらいいか」もわかるからです。
◎いわゆる「賢者」や「聖者」たちは、「情報」で「無知」を覆い隠す
今度は探求の世界の話に置き換えて説明してみましょう。
たとえば、世の中には、いわゆる「賢者」や「聖者」という人々がいます。
そうした人々はとても博識で、多くの経典や聖典に通じています。
それゆえ、彼らは様々な言葉を経典や聖典から引用し、人々に「真理」について語ることができるのです。
そして、多くの聴衆はそういった言葉を聞いていると、「真理」について理解できたような気になってきます。
あるいは、「自分は今、何か聖なるものに触れている」という感じがしてきます。
そして、こうした感覚を聴衆に味わわせてくれるがゆえに、これらの「賢者」や「聖者」たちは人々から大いに尊敬されるのです。
ですが、実際には彼らは必ずしも「真理」を理解しているわけではありません。
彼らはただ、経典や聖典に載っている「情報」を頭に詰め込んでいるだけだったりするのです。
こうした「賢者」や「聖者」たちは、それらの「情報」を的確に組み合わせることで、もっともらしく論述する訓練を積んでいたりもします。
ですが、それは「真理」を理解するということとは関係がありません。
どれほど「情報」を頭の中に組み込んでも、それによって「真理」がわかるようになるわけではないのです。
そして、そのことをこういった「賢者」や「聖者」たちは、うすうす自覚しています。
「自分はまだ悟っているわけではない」と、彼ら自身もわかっているのです。
でも、彼らは人々からの尊敬を失いたくはありません。
だから、化けの皮がはがれないように、ますます経典や聖典から「情報」を取り入れることに注力し、自分の説教をそれらしく磨き上げていくのです。
彼らの頭の中の「情報」は、日に日に増えていくでしょう。
結果的に、人々からは「博識だ」と思われるでしょうし、「まさにこの人こそ賢者だ!」とさえ思われるかもしれません。
ですが、実際のところ、彼らは「真理」について全くの「無知」だったりします。
経典や聖典に書かれていることを自分自身で体験的に理解しているわけではなく、ただ「情報」として取り入れて、そのまま繰り返しているだけなのです。
◎探求者は経典や聖典の元を離れ、「自分の体験」を深めていく
これに対して、「外から仕入れた情報」よりも、「自分自身の体験」を重視する人々がいます。
こういった人々こそ、本当の意味での探求者です。
彼らは経典や聖典に書かれていることを読むことで満足することができません。
なぜなら、こういった人々は、「経典や聖典に書かれていることは本当だろうか?」と疑うことをやめられないからです。
彼らは「深い疑念」に取り憑かれます。
その「疑念」は、学べば学ぶほど、かえって大きくなっていきます。
そして、どこかの段階でこうした人は決意します。
「経典や聖典に書かれていることが本当かどうか、自分で確かめるより他にない」と。
彼らは経典や聖典が与えてくれる言葉だけでは、安心することができません。
それらは確かに、「頭の中の情報」を増やしてはくれますが、そういった「情報」は、当人の苦悩を解決してはくれないのです。
「本当のことが知りたい」
そのように思い定めて、彼らは探求者となります。
そうして、経典や聖典を拠り所とするのではなく、技法の実践を通した「自身の体験」を重視するようになっていくのです。
そういう意味で、「探求者の旅」というのは、「自分自身への確信」を育てていくプロセスであるとも言えるかもしれません。
実際、実践を積み重ねることによって、当人の中で「自己への信」は徐々に大きくなっていきます。
もちろん、最初は不安で仕方ありません。
と言うのも、もはや経典も聖典も拠り所として使えなくなっており、当人は自分の足だけで歩いていかねばならないからです。
「自分のやろうとしていることは、本当に正しいのだろうか?」と考えることもあるはずです。
ですが、実践を積み重ねていく中で、徐々に「自身の体験」が多くなっていきます。
そうして、「自分自身で確かめた事実」が多くなっていくことによって、「このことだけは確かに言える」と確信できる物事が増えていきます。
ゆくゆくは、「たとえ経典や聖典にどう書いてあろうとも、自分の体験ではこうだった」と言えるようにさえなります。
ここまで来ると、経典や聖典の言葉によって縛られることも徐々に少なくなっていきます。
逆に、経典や聖典に書いてあったことの意味が、自分の体験を通して理解できるようにもなっていきます。
そういう時に当人は、「この言葉の意味はこういうことだったのか」と深く納得し、経典や聖典に書かれた教えをただ頭に入れるのではなく、文字通り「自身の血肉」とするのです。
◎「自己への信」が最大化した時、「世界」は幻となって消える
そうやって、「自分自身に対する確信」がどこまでも大きく育っていくと、どこかの段階で「最終的な悟り」が訪れます。
それは「世界は実在しない」という理解です。
【最終回】「世界の実在性」が崩壊する時|「世界」という最後の束縛からの自由について
なぜ「自己への確信」が最大まで深まった時に、「世界の実在性」が崩壊するのかを、私は万人に納得できる仕方で説明することができません。
上記のリンク先の記事で、一応「理屈」は書いていますが、それらは全て「後付け」のものです。
なぜかわからないのですが、「自己への確信」が深まると、「世界というのは幻だ」と感じるようになるのです。
この理解が起こる前まで、探求者自身は「世界が存在するからこそ、その中に自分は存在できるのだ」と思っていたはずです。
ですが、「最終的な悟り」に至ると、この考え方が逆転します。
つまり、「自分が存在するからこそ、世界は存在できるのだ」と当人は感じ始めるのです。
「何を馬鹿なことを言っているのだ!」と思うでしょうけれど、このことを理解するのが「悟り」です。
「そんなのは狂人の妄想だ!」と言われるかもしれません。
確かに、私も「世界は実在しない」ということを客観的に証明することはできません。
しかし、ひたすら「自分自身の体験」を重視して「自己の中心」に定まっていくと、どこかの段階で、「世界」から「自己」のほうへと、当人の軸足が移ってしまいます。
つまり、「世界の実在性」に対する確信を、「自己の実在性」に対する確信が上回ってしまうのです。
言い換えれば、「自分が存在する」ということへの確信が強すぎて、「世界が存在する」ということがうまく信じられなくなるわけです。
そして、そのことによって、当人は真の意味で自由になります。
なぜなら、その時当人にとって「世界」とは、「自分の心が生み出した幻」だと、理解できるようになっているからです。
この時、「世界が自分を作ったのではなく、自分が世界を創っていたのだ」と、当人は悟ります。
もしも「世界が自分を作っている」のであれば、人間にできることはありません。
世界を変えるために革命を起こすことならできるかもしれませんが、それに完全に成功した人はいないでしょう。
言い換えれば、「世界が自分を作ったのだ」と思っている限り、その「世界」によって当人は絶えず束縛されてしまうということです。
「世界を変えたい」と願いながら、その「世界」を変えられなくて苦しむ。
私たちの人生は、そんなことの繰り返しです。
ですが、もしも「自分のほうが世界を創り出したのだ」ということが理解できると、当人はもう「世界」によって束縛されることがなくなります。
なぜなら、「世界とは自分の心の反映である」と、当人には既にわかっているからです。
だとしたら、「自分の心」が自由でさえあれば、もはや誰もその人を束縛することはできなくなります。
身体なら縛ることができるかもしれませんが、当人が身体を束縛だと思っていなければ、相変わらずその人は自由なままです。
私は何も、「世界を創ったのは自分なのだから、やろうと思えば山をも動かせる」というようなことを言っているわけではありません。
実際、たとえ「真理」を悟っても、山を動かせるようになったりしません。
ただ、「真理」を悟ると、「山を動かそうと思って動かせない」ということに関して、当人はもはや執着しなくなります。
言い換えれば、当人はもう「世界を理想の通りに変えよう」とは思わなくなるということです。
もはやその人は山を動かそうともしませんし、社会を変えようともしなくなります。
また、他人を思い通りに操ろうともしませんし、金銭や名声にしがみつこうともしなくなります。
なぜなら、覚者は「自分の中の理想」こそが束縛を生み出す源であるということを、深く理解しているからです。
それは言い換えると、「世界はこのように在らねばならない」という私たちの内なる願望こそが、私たち自身を束縛するのだということなのです。
◎「悟り」とは「感覚的な体験」である
私は今回、かなり論理的な説明を省いて文章を書いています。
そのあたりの細かいプロセスについては、連載記事に書いているので、「どうしても気になる!」という方だけ読んでみてください。
いずれにせよ、私が今回の記事でわかってほしかったのは、「情報をいくら頭に詰め込んでも『真理』は悟れない」ということです。
実際、上記のような「最終的な悟り」が訪れる時、当人はそれを知的に理解するわけではありません。
人が「悟り」に到達する時、決して頭の中に「新たな情報」が入ってくるわけではないのです。
ただ、ある時にふと気づいてみたら、「世界」よりも「自己」に対する確信のほうが強くなっていたことを、当人は発見することになります。
それは決して「知的な理解」ではなく、あくまでも「感覚的な理解」です。
その時、当人は「自分の中に世界が在る」と「感じ」ます。
決して、「自分の中に世界が在る」と「考えた」わけではありません。
理屈はよくわかりませんけれど、なぜか「自分の中に世界が在る」かのごとく、当人は感じるようになってしまうのです。
それゆえ、「知的な訓練」を積んでいない人であっても、「真理」を悟ることは可能です。
むしろ、下手に「情報」を頭に入れていない「純粋な人」のほうが、「悟り」は得やすいかもしれません。
そして、そのように「知的な訓練」を積んでいなくても悟ることが可能であるからこそ、「悟ったけれど、その体験をうまく言語化することができない」という人も現実に存在すると思います。
こういった人々は、悟った後に他の人たちを導く時にも、うまく語ることができません。
それゆえ、世間の多くの人々は、「この人はちっとも学がない」とか、「言っていることに説得力がない」とかいった風に感じて、覚者の言葉を無視してしまうはずです。
むしろ、「世界は実在しないのだ」とまで言い出すわけですから、「狂人なのではないか?」とさえ思われるかもしれません。
つまり、「真理」について理解していない世の中の多くの人々の目には、「学のない覚者」は「無知な狂人」のように映ってしまうわけなのです。
◎「言う者」は知らず、「知る者」は言わず
ここで最初の話を思い出してください。
「多くの情報」を頭に入れた、いわゆる「賢者」や「聖者」たちは、自分では「真理」をまだ悟ることができていない場合があります。
しかし、彼らは「見せかけ」を整えることなら、いくらでも可能です。
彼らはいかにも学があるかのように語ることができますし、聴衆を魅了することさえあるでしょう。
ですが、その内側に「真理についての理解」はなく、ただ「蓄えた情報」があるだけなのかもしれないわけです。
それに対して、覚者は時に「知的な訓練」を積んでいません。
「真理」について感覚的には理解していても、それを言語化して伝えることが得意な人ばかりではないのです。
すると、往々にしてそのような覚者が語る言葉は、あちこち矛盾して見えたり、説得力に欠けるように聴衆からは感じられます。
場合によって、「ただの狂人だ」と思われてしまうかもしれません。
ここに逆説があります。
「真理」を知らない人たちは、もっともらしく語ることができます。
あたかもそれを熟知しているかのように語りますし、時には、覚者よりも説得力のある語り方をするでしょう。
反対に、「真理」を知っている人は、時につっかえながら語ります。
なぜなら、全ての覚者が「知的な訓練」を積んでいるわけではないからです。
そして、本当に深く人間の心理というものを理解している覚者というのは、「ほとんどの人は自分の言葉を誤解するだろう」ということも、よく知っています。
実際、たとえどれほど言葉を尽くして語ったとしても、それはしょせん「言葉による説明」に過ぎません。
結局のところ、それらの言葉は、探求の最後に覚者自身が到達した「悟りの体験」そのものを表すことができないのです。
だからこそ、覚者は時にためらいがちに語ります。
なぜなら、「自分の言っていることは、本当のところ正確ではない」と彼らは自覚しているからです。
逆に、「真理」を体験したのことのない「賢者」や「聖者」は、迷うことなく断言することができます。
なぜなら、全て経典や聖典にしっかり書いてあるからです。
それらの経典や聖典を拠り所にして、彼らはスラスラと淀みなく語ることができます。
そのため、多くの人たちは覚者の言っていることよりも、こうした「賢者」や「聖者」の言っていることのほうを好む傾向があると、私自身は感じています。
むしろ聴衆は、「そうやってスラスラと経典や聖典を引用できる人のほうが、『真理』について詳しく知っているのだろう」とさえ思うかもしれません。
ですが、いくらそういう人たちの説教を聞いて「情報」を内側に蓄えても、「真理」を悟ることはできません。
むしろ、頭に入れた「情報」が邪魔になって、当人はますます道に迷うことになるでしょう。
実際、「外側の経典や聖典」を拠り所とすることで、「自分自身」を拠り所とすることはますます難しくなっていくはずです。
「蓄えた情報」の重さに引っ張られ、「自己への信」が築けなくなるのです。
これが、「真理について語る者」のパラドクスです。
◎「師」を見つける際の二つの基準について
こういった事情があるので、もしもあなたが真に「探求の道を歩もう」と望んでいるならば、耳を傾ける相手にはよくよく注意してください。
先入観から「この人が覚者のはずがない」などと言って、決めつけないほうがよいと思います。
実際、今の日本社会において、ある覚者の女性がスーパーでレジ打ちのアルバイトをしていたとしても、私はちっとも不思議に思いません。
そういうことは、いくらでもあり得ることです。
逆に、「有名な学派のトップに君臨する偉大な学者でありながら、『真理』について何も知らない」ということも、大いにあり得ます(もちろん、「大学者でありつつ覚者でもある」という可能性もあり得ますが、必ずそうだとは言えません)。
なので、「見た目」だけで師事する相手を選ぶと、間違う可能性があります。
両者を見分けるコツはいくつかありますが、次の二つを覚えておいてください。
まず一つ目は、語ることに「ためらい」があるかどうかです。
覚者は基本的に「自分の言葉はきっと誤解されるだろう」と思って語っています。
それゆえ、「自分の体験」に対する確信はありますが、「自分の言葉」についての確信はあまりありません。
逆に、「言葉」だけは確信に満ちて語られるけれど、「当人の体験的な裏付け」があまりないような語り手は、「嘘つき」である可能性が高いです。
両者を見分けるもう一つの基準は、その人の言葉を聞いている時、あるいは、その人のそばで一緒に沈黙している時に、「穏やかな感覚」になるかどうかです。
ひょっとすると、これが最も重要な基準かもしれません。
もしもあなたが本当に「真理」を悟りたいのであれば、ある人の話を聞いていて「知的な興奮」を覚えた場合、その人の話にはあまり耳を傾けないほうがいいです。
ちなみに、これは私が語る話についても当てはまります。
なぜなら、誰かの話を聞いて「知的な興奮」を覚えるということは、あなたがただ自分の頭に「新しい情報」を取り入れたがっているだけだということを意味するからです。
つまり、その時あなたは、頭の中に「情報」が増えていくことに対して、「喜び」を感じているということです。
そして、そのようにして外から頭に「情報」を入れ続けると、「自己への確信」は相対的に弱まってしまいます。
結果的に、それらの「情報」に依存するようになっていってしまい、「自分の体験」を軽視するようになっていくでしょう。
逆に、話を聞いていて「穏やかな気持ち」になれるのであれば、その人についていくことを検討してもいいかもしれません。
話を聞くだけではなく、実際に会って一緒に近くに居られるなら、そばにいるだけで「静けさ」が自分の内側に生じるかを、必ず確認してください。
そばにいるだけで心が静まって、「穏やかな心地」がしてくるのであれば、その人はあなたにとって師となる可能性が非常に高いです。
なぜなら、あなたに「静けさ」を伝染させられる人は、そもそも自分自身の中に深い「静寂」を携えているものだからです。
実際、「静けさ」というのは伝染します。
また、何ものにも束縛されていないことからくる「穏やかな解放感」も伝染します。
ですので、そばにいるだけで、内側が「静か」になり、「安らかな解放感」を感じることができる相手は、あなたにとって師となる人です。
こういった人のそばにいる時、あなたは相手の言っていることがうまく理解できなかったとしても、不思議とその人のことを信頼することができます。
逆に、そばにいるだけで「熱狂的な想い」がたぎってくるという場合、その人のそばにいると、おそらくあなたの「自我(エゴ)」はますます強化されるでしょう。
なぜなら、そういう時には「この人の言っていることは正しい!」という狂信があなたの中には生まれてきてしまっているからです。
そうなると、あなたはゆくゆくは「師の言葉の正しさ」を「自分の正しさ」のように考えて、それを他人に押し付け始めるかもしれません。
つまり、「師こそが正しいのだ!」と誰かに向かって主張することによって、間接的に「その師に従う自分こそが正しいのだ!」と相手に認めさせようとするわけです。
それによって、「自我(エゴ)」は満足するかもしれませんが、束縛はますます強まります。
そして、「師の教えへの依存」が強化され、「自己への信」は弱まっていってしまうでしょう。
◎終わりに
以上の二つが、師を見分ける際の基準です。
まず、言葉の中に「ためらい」があるかどうか。
そして、言葉を聞いたり、そばにいたりする時に、内側で「穏やかな解放感」を感じるかどうか。
師を探す時には、このことをよくよく確認してください。
もちろん、今あなたが読んでいるこの文章に対しても、その基準を適用してください。
あなたはこの文章を読むことで、「穏やかな気持ち」になりましたか?
それともあなたは、何らかの「情報」を求めていただけだったのでしょうか?
もしも私の文章を読むことで「知的な高揚感」を覚えたとしたら、あなたは「賢く」はなったかもしれませんが、「真理に対する無知」はかえって強化されてしまったかもしれません。
いずれにせよ、この世の誰も、当人に代わって「真理」を悟ることはできません。
経典や聖典も、参考にこそなりますが、ただそれを読み続けるだけだと、むしろ迷いが増えていってしまいます。
人を本当に変えるのは、「頭に入れた情報」ではなく、「自分自身の体験」です。
その「自分の体験」を徹底的に深めることが、探求の道であると言ってもいいと思います。
それは、ある意味において「頭に入れた情報」を徐々に忘れていくことでもあります。
「頭に入れた情報」が無価値になり、「自分自身の体験」への確信が定まった時、あなたはもはや自由です。
結局のところ、あなたを真に束縛しているものは、「頭の入れた情報こそが真実である」という、あなた自身の想念なのです。
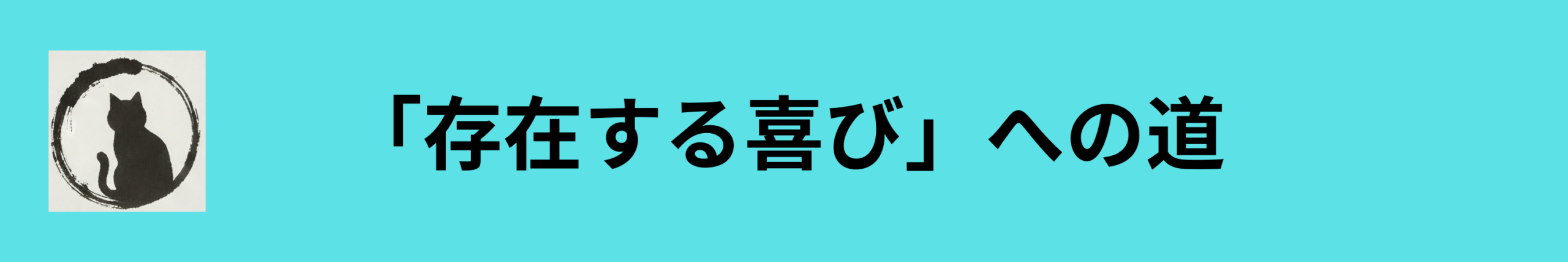
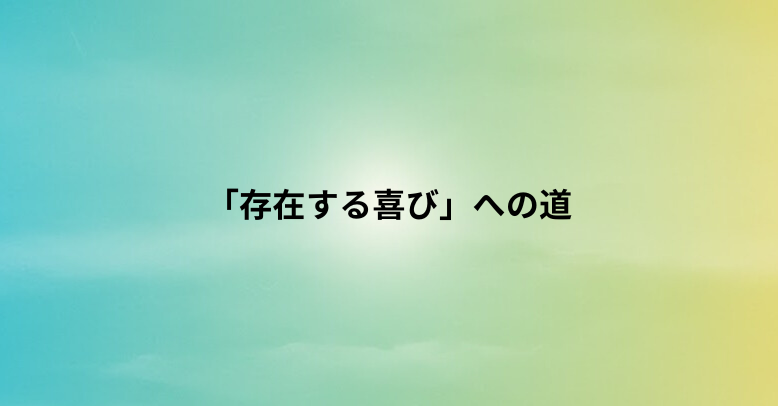
コメント