少し思い出したことがあるので、文章を書きます。
私は数年前、ひどい抑うつ状態に陥っていました。
当時は、毎日「死ぬこと」ばかりを考えていて、人生は完全に「真っ暗闇」でした。
そして、頭の中ではずっと「早く死んでしまえ!」とか、「お前が生きているせいでみんな迷惑している!」とかいった声が鳴り響いていました。
「幻聴」というほどはっきり聞こえるわけではなかったのですが、そうした声は、ほとんど「物理的な力」を持って、私のことを責め苛んでいました。
それで、当時の私はそれらの声が聞こえるたびに、「あぁ、そうだ、自分なんて早く死んでしまうべきなんだ…」と思ったり、「自分が生きているせいで他人に迷惑が掛かっているんだ…」と思ったりしました。
要するに、当時の私は、これらの声が言うことを「正しいこと」だと思っていたのです。
逆に、ある時にはこれらの声に抵抗しました。
「うるさい!お前たちの言うことなんて聞くものか!自分は間違ってなんかいない!」と、私はそういった「内なる声」に反論し、これらと闘っていたわけです。
しかし、そうやって私が反抗すればするほど、かえって声は大きくなっていきました。
まるで反抗する私のことを嘲笑うかのように、それらの声は「早く死ね!」と言い続け、私は無力感を感じながらも、必死で抵抗を続けたのです。
ただ、ある時を境に、そういった声に私は構わなくなっていきました。
たぶん、何千回、何万回と同じことを言われ続けたことで、私はその言葉にすっかり慣れ切ってしまったのです。
それゆえ私は、「お前なんか死んでしまえ!」という声が内側で聞こえても、「あぁ、またいつもものアレか」とだけ思って、気にしなくなっていきました。
かつては「この声があるから生きにくいのだ」と思って、それを必死でなくそうと思っていたのですが、その時の私はもう、「声をなくそう」とは思わなくなっていました。
私はその声を「いつも茶々を入れてくる隣人」くらいに考えて、「そういうヤツが内側にいても、まぁいいか」と思うようになっていったのです。
しかし、そうしているうちに、気づいたらその声が聞こえなくなっていました。
「あれ?そういやアイツ、最近見ないな」と思った時には、私はすっかり元気になっていて、もはや「早く死ね!」という声を聞くことができなくなっていたのです。
今では、「アイツ」がいなくなったことが、なんだかちょっと寂しいような気もしています。
なんだかんだで、「賑やかなヤツ」ではありましたから。
過去の私が体験したように、私たちの内側には、いろんな「声」が起こることがあります。
それらの声は、時として私たちのことを否定してくることもあるでしょう。
でも、もしもその「否定的な声」に対して、「言っている通りだ。この声は正しい」と思うなら、その人は自己否定の泥沼にハマっていくことになります。
かといって、逆に「お前の言うことは間違っている!」と言って反論すると、その人は自分の内側に存在する「実体のない影」と闘うことになってしまいます。
「影」には実体がありませんから、取っ組み合って闘うことができません。
それゆえ、「倒そう」と思って力めば力むほど、当人は一人で疲弊していってしまい、反対に「影」は大きくなっていくのです。
ただ、そういった全ては「必要なプロセス」と言えば、そうなのかもしれません。
「この声は正しい」と思うことも、「この声は間違っている」と思うことも、ずっと繰り返していると、どちらにもそのうちうんざりしまいます。
要するに、自分のやっていることが、段々バカバカしく感じられてくるのです。
その時、当人は「内なる声」に対して、「正しい」とも「間違っている」ともラベルを貼らずに、「ただの声」として接するでしょう。
「声」というのは、結局のところ、「ただの音」に過ぎません。
そこに意味を付与して解釈し、「正しい」とか「間違っている」とかいったラベルを貼るのは、私たち自身です。
だから、もしも解釈を差し控えることができるなら、「全ての声」は「物理現象」に過ぎなくなります。
その時、当人はあたかも「道端に咲いている花」を見ている時のように、「お前なんか死んでしまえ!」という声を聞くようになります。
そこには、「あなたはそう思うんですね」という返答だけが存在しています。
つまり、自分の内側の「早く死ね!」という声に対して、「私はそのように聞きました」とだけ返事をし、「相手が正しい」と寄りかかるのでもなく、「自分のほうが正しい」と意地を張るのでもなく、そうした声とそのまま向き合うことができるようになるのです。
結局のところ、「他者」というのは一つの「謎」です。
私たちに確認できることは、自分のことだけです。
自分が存在するということ。
その自分から、世界はこのように見えているということ。
それだけが、「確認可能なこと」です。
「他者」の目から世界がどう見えているのかについては、私たちには確認しようがありません。
でも、私たちはそういう「確認できない状態」にどうしても耐えられなくなってしまいます。
なぜなら、「わかったつもり」になりたいからです。
それゆえ、私たちは自分や他人に「正しい」「間違っている」というラベルを貼り、自分を納得させようとします。
時には、他者に「正しい」というラベルを貼って相手に寄りかかり、時には、自分に「正しい」というラベルを貼ってどこまでも戦おうとします。
難しいのは、「わからない」という事実に留まることです。
「答えがない」ということを事実として受け入れて、その状態の中で深く息をすることこそが難しいのです。
人は、「答えの無さ」に長く耐えることができません。
それゆえ、私たちは「確認できないこと」について、「真実がわかった」かのように考え始め、時に「思想や価値観の城塞」を作り上げます。
確かに、その中に入っている限り、当人は「自分は正しい」と思うことができるでしょう。
でも、その「城塞」は外からの空気も遮断するので、当人はだんだん息苦しくなってきてしまいます。
そして、「こんな風に息苦しいのは、きっとどこかにいる『悪者』のせいに違いない!」と考えて、「加害者」を探し始めるのです。
しかし、実際のところ、当人を息苦しくしているのは、自分自身だったりします。
自分で自分を束縛し、自分の呼吸を押し殺してしまっているのです。
当人がそうせずにいられないのは、私たちが「答えの無さ」に耐えられないからです。
「あなたはそう思うんですね」とだけ言えないんです。
どうしても、そこから「あなたは正しい」と言って寄りかかるか、「いや、あなたの言うことは間違っている」と一歩踏み出して戦うかしてしまいます。
「余計な一言」を足すことなく、一歩も出ず、一歩も退かず、「わからない」という原点に居続けること。
それが、本当の意味での「他者に対する誠実さ」なのではないでしょうか?
かつて、ユダヤ人哲学者のエマニュエル・レヴィナスは、「哲学の本務は、難しい問いに答えを出すことではなく、答えの出せない問いの下に繰り返しアンダーラインを引くことだ」と言いました。
世の中のほとんどの哲学者は、「答え」を出そうと躍起になりますけれど、「答え」を出した段階で、その人は「自分で作った城塞」に閉じこもり始めてしまいます。
そうして、「自分が正しくて他者は間違っている」という二元論的な価値観で、裁きを下すようになっていくのです。
重要なのは、「答えを出すこと」ではないと思います。
大事なことは「答えの無さ」を生きることです。
あなたがご飯を食べる時、もし「美味しい」という感覚が発生したなら、そこには「正しい味」も「間違っている味」も存在しません。
私たちはただ生きています。
「答え」なんてわからないまま、その「わからない謎」を日々呼吸しています。
でも、もしも「生」というものについて、「答え」を出してしまったら、そこにある「神秘」はバラバラに切り刻まれてしまって、もはや生きることができなくなってしまうでしょう。
「答えの無さを生きる」と言うと、なんだか「暗い諦念」みたいに感じるかもしれませんけれど、それはある意味で、「生」というものに対する徹底的な肯定です。
実際、「他者」と同様、「生」というものもまた「謎」です。
私たちはそれを完全に解明することができないでしょう。
でも、それで別にいいのです。
なぜなら、もしも「生」について何もわからなかったとしても、ご飯は美味しいし、空気は旨いからです。
私たちは生きています。
そのことの中に、「最も深い謎」は在り、私たちは何もわからないまま、日々それを飲み干して生きています。
「答え」なんてなくても人は笑えるし、深く息をすることができるのです。
苦しみに「正しい」も「間違っている」もありません。
喜びに「正しい」も「間違っている」もありません。
私たちはただ、それを生きるだけです。
「答えの無さ」に留まったまま、「自分の踊り」を踊るだけです。
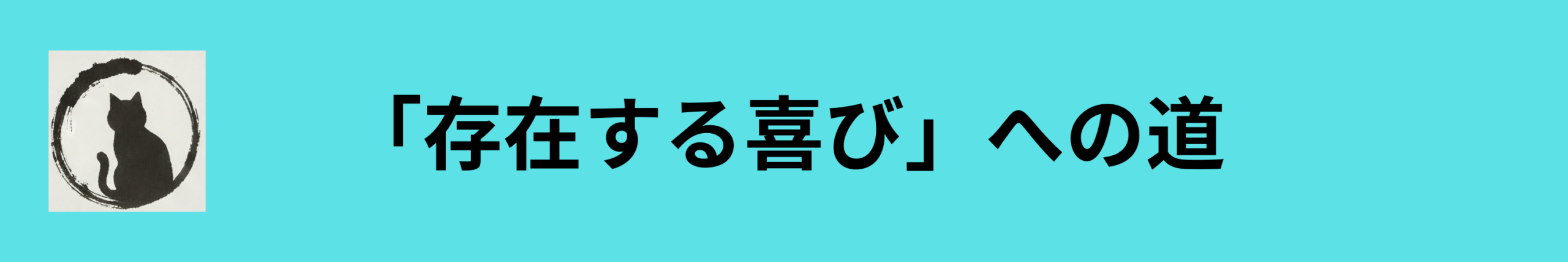
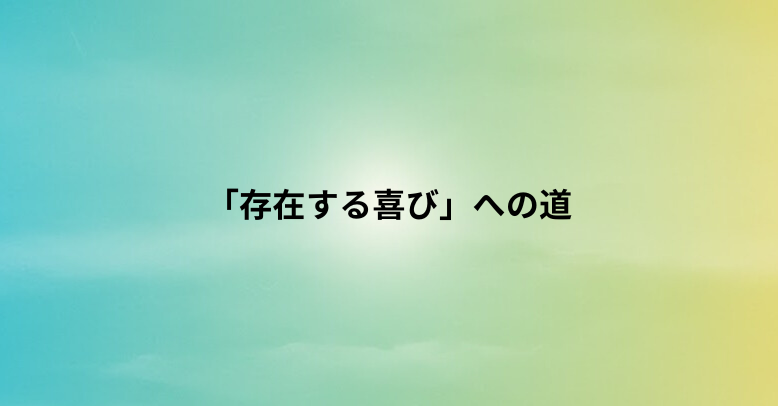
コメント