「現成公案」の解説本、第二章が書き終わりました。
この章は、「現成公案」の中の有名なフレーズである「仏道をならふといふは、自己をならふ也」を解説する章です。
道元は「仏道」と言っていますが、これは彼が仏教徒だからであって、現代風に解釈するなら、別に仏教の修行に限定して考える必要はないと思います。
人によってはヨーガを実践するかもしれませんし、自己啓発書を読み漁って、そこに書いてあることを実践する人もいるでしょう。
いずれにせよ、そうやって何らかの「道」を学んでいくと、その人は徐々に「自己をならふ」ことになっていきます。
私が思うに、道元が言う「自己をならふ」は、二つの段階から構成されています。
それは、「自分軸の確立」と「本当の自己(意識)の発見」です。
まず、なんらかの「道」を学び始めると、人は「教師」から言われたことを真面目に守って実践するようになります。
教わったことを勝手にアレンジしたりせず、これを「真理」として受け入れて実践を重ねていくのです。
しかし、もしも当人が「真摯な探求者」であった場合、どこかの段階で「深い疑念」に取り憑かれるようになるはずです。
なぜなら、実践すればするほど、当人はかえって自分が「ゴール」から遠ざかっていくように感じ始めるからです。
実際、経典や聖典を研究していくと、人はしばしばその教え同士の中に「矛盾点」を見つけてしまいます。
実際には「真理は一つ」なので、深いところでは矛盾していないのですが、この段階の探求者には、そのことがわかりません。
それゆえ、「いったいどっちの言っていることが正しいんだ?」と思って、道に迷ってしまうわけです。
それで、自分の習っている「教師」に質問して、「どっちが正しいんですか?」と確認します。
でも、その質問された人が「真理を自分で知っている師(マスター)」ではなく、「単に経典や聖典をおうむ返しにしているだけの教師(ティーチャー)」に過ぎなかった場合、納得のいく答えはもらえません。
もし、その「教師」に「誠実さ」が残っていれば、「自分にもわからない」と正直に告白するかもしれません。
ですが、おそらく十中八九、「教師」は「自分の無知」が暴かれそうになって狼狽し、「そんな質問をするお前は間違っている!」と言って叱責するはずです。
そうして「教師」は、時として「自分の体面」を保つために、「不躾な質問をした生徒」を道場や学校から追放するのです。
私自身も過去に「追放」されたことがあるのでわかるのですが、こういう時、その人は「自分の足」で立つしかなくなります。
もはや「教え」も「教師」も「組織」も自分のことを守ってはくれません。
それでも、当人の中には迷いと疑いが残っていて、その人は「苦しみ」にもだえ続けています。
それゆえ、「本当に真摯な探求者」であれば、ここで諦めずに前に進もうとします。
つまり、「経典や聖典をおうむ返しにするだけの教師(ティーチャー)」ではなく、「真理を自分で呼吸している師(マスター)」を自力で探し出そうとするのです。
その過程で、当人は自然と「自立」するようになります。
自分の選択の責任を「教え」や「教師」や「組織」に負わせようとしなくなり、当人は「自分の人生」を自分で背負い始めるのです。
そして、この「自分自身への責任感」が、当人の意識を徐々に「覚醒」させていきます。
そもそも、世の中の多くの人が「自分の人生」に対して無責任なのは、「覚醒したくないから」です。
なぜなら、もしも「覚醒」してしまったら、「全ては自分の責任である」と自覚するしかなくなるからです。
実際、私たちのことを束縛するのは、いつだって私たち自身です。
他人に縛ることができるのは、あくまでも当人の身体だけです。
私たちが苦しむのは、「他人に苦しめられているから」ではなく、私たち自身が何かを「理想化」して握りしめているからです。
そして、「理想」の通りにならない「現実」を前にした時、当人は「苦しみ」にもだえることになるのです。
それゆえ、もしもいかなる「理想」も握りしめなければ、当人はもう苦しむことがなくなります。
「理想」が全て放棄されることで、「苦しみが発生する根っこ」がそこには存在しなくなるため、「苦しみ」が生じる余地がなくなるのです。
逆に言うと、もしも「苦しみ」が発生するなら、その「苦しみ」を育てたのは自分自身であるということでもあります。
もちろん、それは無自覚だったかもしれませんし、最初に「理想」を握りしめた時は、まだ幼く無力な子どもの頃で、「理想化された愛や承認」にしがみつかないと生き残れなかったのかもしれません。
でも、大人になった後もなお苦しみ続けているのであれば、その「苦しみ」の責任は当人にあります。
というのも、親や教師から独立することのできる「大人」ならば、「自分の苦しみ」を「自分自身の責任」によって終わらせることが可能だからです。
しかし、この「事実」を自覚することは、人によっては「激痛」を伴います。
特に、なんでもかんでも「他人のせい」にすることに慣れている人は、絶対にこれを認めないでしょう。
当人は「自分の苦しみ」について、常に「社会が悪い」「他人が悪い」と言い続け、幼少期に自分の内側に埋め込まれた「地獄」から目を逸らそうとし続けます。
そして、そうやって「何でも他人のせいにしている人」は、「自分の選択」にも責任を持ちません。
なぜなら、たとえ「間違った選択」をして自分や他人が損なわれても、「それは自分のせいではない」というエクスキューズを、当人は「いつでも切れるカード」として保持することができるからです。
このため、「他責的な人」というのは「覚醒」することがありません。
というのも、もしも「覚醒」してしまうと、「実は自分に責任があった」ということをその人は自覚してしまうからです。
彼/彼女は「真実」を知りたくありません。
それゆえ、もしもうっかり「覚醒」しそうになると、当人は一目散で逃げ出すのです。
逆に、「自分軸」を確立した人は、「責任は自分にある」と自覚しています。
だから、当人はいつも注意深く選択します。
「自分の選択が、自分や他人の人生を左右しうる」ということに、彼は明確に気づいています。
そして、この「主体的な注意深さ」が当人の「覚醒」を育て、「次の気づき」をもたらします。
それが、道元の言う「自己をならふ」の第二段階である、「真の自己(意識)の発見」です。
もしも「覚醒」が深まって日常の中に広がり始めると、どこかの段階で、当人は不思議な体験をします。
それは、「これまでずっと自分だと思っていたもの(自我)」のことを、「客観的に観ている者」の存在に気づいてしまう体験です。
この時、当人は「『自我』は『本当の自分』ではなかったのだ」と気づきます。
私たちは普段、人格や個性、性格や記憶などを、「自分自身」と同一視しています。
つまり、自分が「どういう人間」であるかということに、「アイデンティティの軸足」が置かれているのです。
しかし、「覚醒」が一定以上に深まると、この「アイデンティティ」は崩壊します。
実際のところ、「私たちの本質」は人格や記憶とは関係ありません。
たとえどんな人格になろうとも、仮に記憶喪失になろうとも、私たちはあいかわらず、「自分自身」で在り続けるのです。
このことを理解するのは、おそらくかなり難しいと思います。
でも、ここを越えないと、道元の言う「自己をならふ」という言葉の意味は理解できません。
そして、もしも「『自我』は『本当の自分』ではない」ということが理解できたなら、ようやくその人の探求は「折り返し地点」に到達します。
ここからは、「来た道を戻るプロセス」が残っています。
それがすなわち、道元の「現成公案」に出てくる次のフレーズである「自己をならふといふは、自己をわするるなり」の意味です。
「自分軸の確立」と「真の自己(意識)の発見」という二つの段階を経ることによって、人は「自己をならふ」わけですが、そこから先は、そうしてやっとつかんだ「自己」を忘れていくプロセスが残っているというわけです。
ということで、今書いている「現成公案解説本」の第二章では、「自己をならふ」について書きました。
次の第三章では、「自己をわするる」ということについて書く予定です。
書いていて思いましたけど、こんな「真実」をいったいどれだけの人が受け取れるんでしょうか?
たぶん私は、「ほとんど誰も知りたがっていないこと」を書こうとしています。
おそらく、世の中のほとんどの人は、私の言葉を「誇大妄想に取り憑かれた狂人の妄想」と見なして黙殺するでしょう。
なぜなら、そうでもしないと、自分たちが必死に守っている「自己欺瞞」が暴かれてしまうからです。
でも、世の中には「たとえどれほど『痛い想い』をすることになってもいいから、『真実』が知りたい」と切望する人々が、いつの時代にも一定数存在していました。
そして、私としては、そういう人に言葉が届けば、それでいいと思っています。
あなたはどっちですか?
「真実」から絶えず目を逸らし、「自分を騙す生き方」を死ぬまで続けられる自信があるなら、それでも別にいいと思います。
でも、生まれつき「そういうこと」ができない人がこの世には存在しています。
そのように生まれついてしまった人は、「社会にうまく溶け込めない」という意味で「ついていなかった」とも言えますが、「『真実』に対して目を閉じないだけの勇気を生まれ持っている」という意味では「神に愛されている」とも言えます。
そして、もしもあなたが「自分を騙すのが下手な人」であるのなら、本書を読んでみることは何かの役に立つかもしれません。
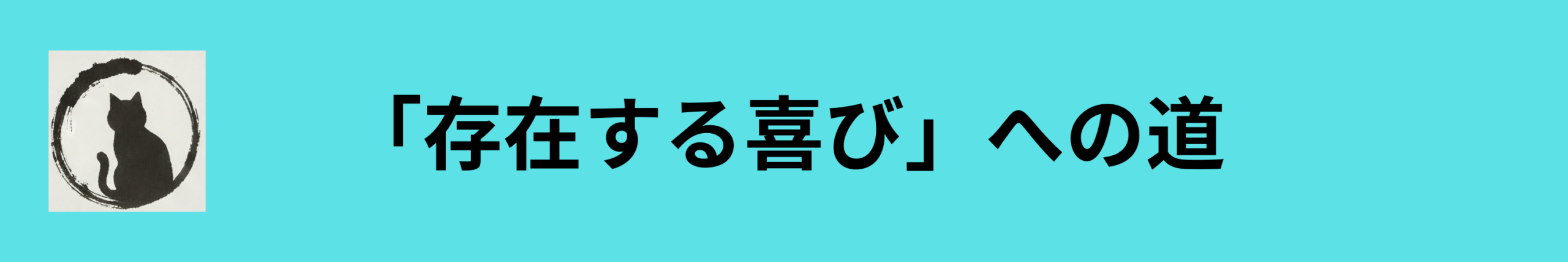
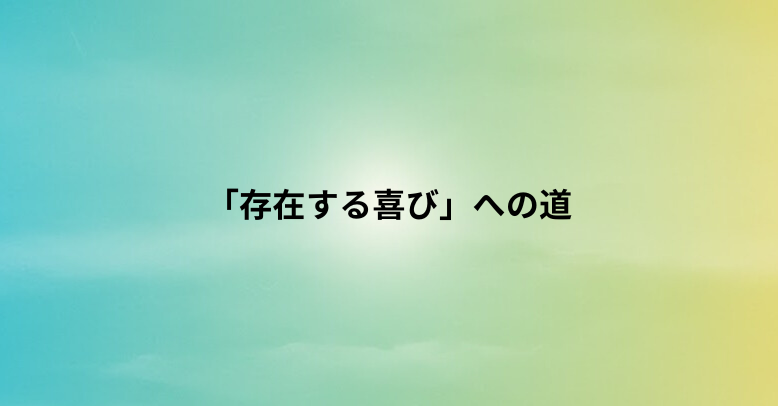
コメント