今回は、「実践の手引き」とか「探求のヒント」とかいったものではなく、ちょっとした「哲学的な考察」を書いてみたいと思います。
その考察とは、「他者にも『意識』はあるのだろうか?」というものです。
なお、私の中にも別に「明確な答え」があるわけではありません。
ただ、そういうことが気になる探求者がいるかもしれないので、とりあえず記事を書いておくというだけのことです。
探求そのものに直接かかわる事柄ではないので、興味のある人だけ読んでみてください。
では、始めていきましょう。
◎「心のないロボット」に関する思考実験
「他者にも『意識』は存在するのか?」
これは哲学の世界において「他我問題」として知られているものです。
人によっては、このことを子どもの頃に考えたことがあるかもしれません。
「他人の中にも、自分と同じように『意識』があるのかどうか?」
幼い頃、それが気になって仕方なかった人はいませんか?
ちなみに、私はあまり気になったことがありませんでした。
良くも悪くも、「自分に対する関心」が強い子どもだったためだと思います。
子どもの頃の私は他人の気持ちがよくわからなくて、コミュニケーションがうまくいかなかったことも多かったものです。
ただ、今回の問題は、「そもそも『他人の気持ち』というものが実在するのか?」という点にあります。
これについては、哲学的な思考実験をしてみると理解がしやすくなります。
たとえば、あるところに、非常によくできたロボットが存在したとします。
見た目は人間そっくりで、誰の目にも「ロボットだ」とはわかりません。
しかし、そのロボットには「心」と言えるようなものはなく、内側では何も感じていません。
痛みも味も、喜びも悲しみも、そのロボットはそれらがどんなものなのか、知らないのです。
ですが、そのロボットには人間のあらゆる行動パターンが登録されています。
もしもロボットが転んで膝をすりむくと、そこから血(のようなもの)が流れて、ロボットは「いかにも痛そうな身振り」をします。
時には「痛い!」と言って、涙(のようなもの)を流すことさえあるかもしれません。
また、同じように、他の人間だったら怒るような場面で、そのロボットは「いかにも怒っているかのような身振り」をし、他の人間だったら悲しむであろう場面では、「いかにも悲しそうな身振り」をするのです。
周りでそうした様子を見ている人からしたら、このロボットは人間にしか見えません。
しかし、当のロボットは内側では何も感じておらず、人間だったらするであろう言動を、登録されたパターン通りにおこなっているだけに過ぎないわけです。
◎「他者の意識の実在」を確かめる術は存在しない
以上のような場合にも、このロボットに「意識」があると言えるでしょうか?
たぶん、こういう話を聞いた人の多くは「そのロボットには『意識』なんてないんじゃないの?」と感じるのではないかと思います。
なぜならそのロボットは、私たちの中心に存在している「この自分」とは違って、自分自身で痛みや怒りや悲しみを感じているわけではないからです。
でも、以上のように考える時、私たちは知らないうちに「神の視点」に立っていることになります。
それはつまり、本来は決してそこから出ることができないはずの「この自分」から抜け出して、全ての人の内側を平等に見通すことができる存在(それが「神」です)からの視点を、当人は前提にしているわけです。
そういう意味では、世の中のほとんどすべての人は、「神の視点の存在」を信じているとも言えます。
なぜなら、この世の誰も「この自分」から抜け出すことはできないのに、それにもかかわらず、「他人にも意識はある」と当たり前のように考えているからです。
また、さっきのロボットの例で「そこに意識はない」と多くの人が思うのも、「他人の中を平等にのぞき込める」という「神」の能力を前提にしているからこそです。
そして、この「神」の視点からは当然、「意識がある他人」のことも識別できることになります。
「ロボットは何も感じていなかったから、そこに『意識』はない」と言うのと同時に、「他人はいろいろなことを実際に感じているはずだから、そこに『意識』はある」と言うことになるわけです。
ですが、本当にそうでしょうか?
実のところ、他人に「意識」があるかどうかを確かめる方法は、究極的には存在しません。
たとえば、さっきのロボットの例のように、あたかも痛みや怒りや悲しみを自分で感じているかのように振る舞うならば、何も知らない周りの人は、そこに「意識」の存在を確信するのではないかと思います。
でも、「神の視点」からは「意識」なんて存在しておらず、ただ前もって登録されたパターンの通りに振舞っているに過ぎません。
また、脳科学では「脳がこのような状態にある時、当人の『意識』においてはこういうことが起こっている」というような説明をよくしますが、「脳が怒りを示す状態に在る」ということと、「当人の『意識』の中に怒りが現に現れている」ということとの間には、埋めることのできない距離があります。
脳科学が語っていることは、あくまでも「脳がこういう状態になっている時に、当人は外から見ると怒りを感じているように見える」ということだけです。
たとえどれほど脳の状態が「怒り」の兆候を示していても、当人は、あのロボットのように、内側では何も感じていない可能性が常に残ります。
つまり、他人に本当に「意識」が存在するかどうかについては、どうやっても確かめることができないということなのです。
◎社会生活において、「他者の意識」を推定することが必要な理由
このように、他人に「意識」があることを確かめられる方法は、この世に存在しません。
私たちにできることは、「たぶん他人にも『意識』があるのだろう」と「推定」することだけです。
そして、この「推定」には、社会生活を円滑に営む上での妥当性があります。
つまり、たとえ相手がロボットであろうと、外見上、「意識を持った人間」のように見えるのであれば、「この人には意識がある」と前提することは、この社会で生きていく上で必要な「推定」であるということです。
実際、もしもこのことをいちいち疑うようになってしまうと、他者との共生が難しくなる可能性があります。
たとえば、もしも当人が子どもであれば、友達の感情を想像する習慣がつかなくなってしまうでしょうし、大人であれば家族や仕事仲間の気持ちや都合を尊重する態度が身に着かなくなってしまうでしょう。
そういう意味で、「他者にも『この自分』と同様に『意識』が在るはずだ」と考えることは、社会のマナーを学ぶ際にとても重要になるポイントと言えるかもしれません。
この前提をうまく呑み込めなかった子どもは、他人の気持ちを想像することをしなくなるでしょうし、他人の都合も考えなくなるでしょう。
つまり、「他者の内側にも『意識』があり、その上で『自我』も機能していて、みんなそれぞれが『自分の人生』を生きているのだ」という風に考える人だけが、「他人の都合」というものを尊重できるようになるわけです。
ですが、繰り返しますように、他者に「意識」があるのかどうかは、確かめる術がありません。
私たちに(というか「私」に)できることは、ただ「推定」することだけなのです。
◎「真理の探求」において、「世界」の実在性は崩壊する
逆に、「自分の意識」の存在ならば、いくらでも確かめることができます。
実のところ、「真理の探求」というのは、この「自分の意識」の実在性について、とことんまで確かめ尽くす旅でもあります。
そして、その旅の終点において、「存在するのは『自分』だけであり、『世界』というのは『虚構』に過ぎない」という理解が起こります。
【最終回】「世界の実在性」が崩壊する時|「世界」という最後の束縛からの自由について
「自分の意識」の実在性について、どこまでも確かめていった果てに、「世界の実在性」が否定されてしまうことになるわけです。
ですが、それは「世界は実在しない」ということを証明できたという話でもないのです。
そうではなくて、あくまでそれは「世界の実在性には『この自分』の実在性ほどの根拠がない」という理解です。
つまり、「世界は絶対に実在しない」ということが証明できたわけではなくて、あくまで「世界の実在性には根拠がない」とわかっただけなのです。
それゆえ、「悟り」が実現した後も、「世界の実在性」そのものが完全否定されるわけではありません。
「世界は絶対的に実在しない!」と言って閉じこもるわけではなく、覚者はごくごく普通に生きていきます。
つまり、「世界」というものがあたかも存在するかのように「推定」して、その後の人生を生きていくようになるわけです。
しかし、その認識においては、一般の人々と大きな違いがあります。
というのも、当人の中には「『世界』というのは『虚構』である」という理解が確固としてあり、「世界の実在性」についても別に確信はしていないからです。
そこにおいて当人は、とりあえずの生活上の便宜から、世界の存在を「推定」しているだけに過ぎません。
それは、表面的な見かけ上は、一般的な人とは全く変わりがないかもしれません。
ただ、他の多くの人たちが頭から信じているようには、彼/彼女は「世界の実在性」を信じていないのです。
◎「真理の探求」が持つ感覚的な性質と、「哲学的考察」の限界について
閑話休題。
「意識」について話していたのでした。
私たちはみんなだいたい「他人にも『意識』があるはずだ」という風に前提して生きています。
だからこそ、他人の気持ちを想像したり、他人の都合を尊重したりもするわけです。
ですが、「真理」を悟ると、このあたりの認識も微妙に変わってきます。
というのも、もしも「真理」を悟った場合、「世界の実在性」に根拠がないことを当人は理解すると同時に、他者の「意識」の実在性についても、究極的には根拠がないということが理解できるようになるからです。
もちろん、「神の視点」に立ってみることは可能です。
その場合、他人にも「意識」があるかのように感じることもあるでしょう。
でも、それはどこまで行っても想像に過ぎず、「この自分」から抜け出すことができない以上、確かめることができません。
もし仮に他人の身体に憑依することができたとしても、その時にはその他人の身体の内側にいるのが「この自分」になるだけであって、自分がそうして憑依する前にその他人に固有の「意識」が存在していたことの証明にはなりません。
結局、答えはないのです。
他人には「意識」が在るのかもしれませんし、無いのかもしれません。
でも、社会生活を送る際の便宜上、私はとりあえず「在る」という風に「推定」しています。
だからこそ、こうして他人が読む文章をせっせと書いているのでもあります。
そもそも他人に「意識」が無いと前提しているのであれば、他人が「真理」を悟るための手引について、こうしてブログで書いたりしません。
つまり、私は他人の「意識」の存在については、「確かめる方法は存在しないけど、完全に否定する根拠もないから、とりあえず『在る』という風に思っておく」というスタンスなわけです。
実際、私のようなスタンスを取る覚者は多いのではないかと思います。
なぜなら、多くの覚者は「真理」を理解した後に、弟子を取って教えを伝えようとするからです。
もしも「実在するのはただ『この自分』だけだ」と思っていたら、たぶんそういうことはしないのではないかと思います。
「他人の意識」の存在を確かめる方法はありませんけれど、積極的に否定する根拠もないので、「あなたの中にも『不変の意識』が在る」と言って弟子を導こうとするのでしょう。
そういう意味では、私は「独我論者」とも言えるかもしれません。
というのも、実在するのは「真我」のみであり、「世界の実在性」には根拠がないと私は思っているからです。
しかし、私は別に論理的に哲学的な考察を重ねた果てに、そのような理解に到達したわけではありません。
私はただ、ひたすら自分の内側に潜り続ける実践をおこない、その結果、「世界は実在しない」という「感覚的な理解」に至ったのです。
決して「世界は実在しない」ということについての「知的な理解」を、あれこれ考えて構築したわけではありません。
そして、だからこそ、私は実際に「世界」に振り回されることを避けられるようになりました。
その理解が自分自身の体験を通した「感覚的なもの」であったがゆえに、それは私自身を深く変容させることができたのです。
最後に、ある哲学者のエピソードを引いて終わろうと思います。
その哲学者は根っからの独我論者で「存在するのは『この自分』だけで、この世界は全て夢のようなものに過ぎない」と常々言っていました。
しかしある時、そんな彼の論説を聞いた一人の友人が、突然、その独我論者の足に石を叩きつけたそうです。
すると、独我論者は痛みのあまり気が動転して、大騒ぎを始めました。
そして、その様子を見ていた友人は、彼にこう言ったのだそうです。
「いったいどうした?この世界は全て夢に過ぎないんじゃなかったのか?」
「もしも世界の全てが夢なら、その痛みだって現実ではないはずじゃないか?」
「もし世界が全て夢なら、いったいこの後、君はどこへと帰るつもりだ?」
「君はきっと自分の家へと帰っていく。君は本当は自分の言葉を信じていない」
「『世界は夢だ』と言いながら、君はこの世界の実在を信じているのだ」
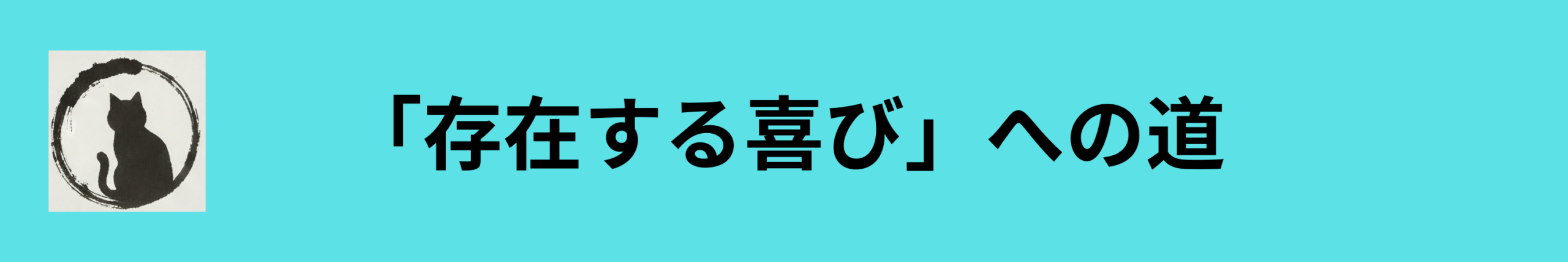
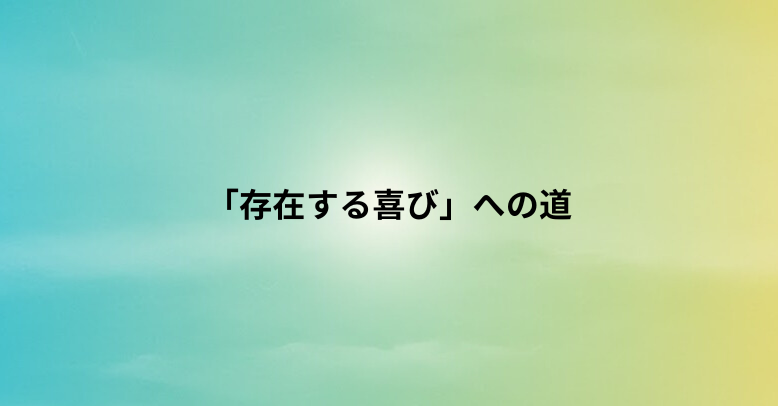
コメント