◎『老子』淳風第十七において語られている「君主像」について
私は昔、自分で教室を開いて、武道や瞑想について教えていたことがありました。
とはいえ、その頃はまだ真理の探求をしていなかったので、「自我」と完全に自己同一化していて、「エゴ」丸出しの教師だったと思います。
当時の私は、心の底では「もっと楽して生徒からチヤホヤされたい」と思っていたため、人を教え導くことに真剣だったとは言い難いでしょう。
ですが、そんな私も「理想の教師像」のようなものは持っていました。
「教師というのはこう在れたら理想的だろうな」という風にイメージするものがあったわけです。
その私のイメージの元になっていたのは、『老子』の淳風第十七に出てくる「君主」についての記述です。
それはこんな書き出しから始まっています。
太上は下之有るを知るのみ。
其の次は之に親しみ之を誉む。
其の次は之を畏れ、其の次は之を侮る。
『老子』、阿部吉雄・山本敏夫著/渡辺雅之編、明治書院
「太上」というのは「最も優れた君主」のことです。
つまり、「太上は下之有るを知るのみ」というのは、「本当に優れた君主というのは、民衆からその存在を知られているだけの者のことである」という意味になります。
そしてその後の「其の次は之に親しみ之を誉む」というのは、「太上」よりもちょっとだけ劣っている君主についての記述です。
つまり、「太上の次に優れた君主は、民衆から親しまれ、その功績を称賛される」ということですね。
あとはたぶんわかるのではないかと思います。
「其の次は之を畏れ」というのは、「三番目に位置する君主は民衆から恐れられている」ということであり、「其の次は之を侮る」というのは、「最も劣った君主は民衆から侮られているものである」ということになります。
「一番優れた君主」は「知られているだけの存在」であり、その次は「親しみを込めて称賛され」、その次は「民衆から恐れられ」、「最も劣った指導者」は「民衆から侮られている」ということですね。
◎職場における「理想の上司」とは?
これは「国を治める君主」について言われている言葉ですが、「人の上に立つ」ということについて、かなり汎用性の高い知見なのではないかと、個人的には思っています。
たとえば、職場の上司について。
『老子』によると、「一番ダメな上司」というのは、部下から侮られている上司です。
実際、「あの人、本当に仕事できないよね」などと裏で言われながら、全く信頼されていない上司を、あなたも一度は見たことがあるかもしれません。
こういった上司に関しては、部下は「ついていきたい!」とは思わないものですし、その上司が存在するだけで、チーム全体のモチベーションが下がってしまうこともあるでしょう。
また、いつも怒ってばかりで、理不尽に部下を追い詰める上司は、周りから恐れられているかもしれません。
こういった上司の場合、「侮られている上司」と違って、部下に命令を聞かせることはできると思います。
ですが、部下たちは内心ではその上司には従っておらず、不満を溜め込んでいる可能性が高いです。
表面上は、チームが一致団結して動いているように見えながら、実際には上司による「ワンマン」になっており、その体制はいつ瓦解するかわかりません。
それに対して、部下から深く慕われて、尊敬されている上司も存在します。
仕事ができて、思いやりもあって、部下の気持ちや都合を配慮してくれる上司。
多くの人にとって、まさに「理想の上司」ですね。
こういった上司に対しては、部下は「この人についていこう!」と主体的に思いますし、「この人のために頑張ろう!」というモチベーションも湧いてくるのではないかと思います。
ですが、『老子』においては、このような上司はまだ「太上」ではありません。
『老子』によると、「最も優れた指導者」というのは、「その存在が知られているだけの者」なのです。
◎「親しまれる教師」は生徒の自立心を挫いてしまう
しかし、「最も優れた指導者はただ存在を知られているだけだ」と言うと、「そんな人間、何の役にも立たないじゃないか!」と思う人もいるかもしれません。
確かに、「ただ存在しているだけ」というのでは、役に立たなそうに思えます。
ですが、そうして「ただ存在しているだけの人」が上に立つことによって、部下たちは自分たちで考えて、自分たちで決断するようになっていきます。
つまり、指導者の存在に依存することなく、自分自身の足で立とうとするようになるのです。
実際、先ほど引用した『老子』の淳風第十七はこんな風に続きます。
信足らざれば、不信有り。
猶として其れ言を貴べ。
功成り事遂げて、百姓 皆 我自ら然りと謂えり。
前掲書
「信足らざれば、不信有り」というのは、つまり「君主が民衆を信頼していないと、民衆も君主を信頼できない」ということです。
ただ存在しているだけの「太上」も、民衆を軽んじているわけではありません。
むしろ、「太上」は民衆自身が持っている力を、深く信頼しているのです。
「猶として其れ言を貴べ」というのは、「君主は何を言うべきかよく思慮を巡らせて、言葉を大事にしなければならない」ということです。
決して民衆をほったらかしにするわけではなく、あくまでも「君主は本当に民衆のためになる言葉をこそ考えるべきだ」ということでしょう。
そして、「功成り事遂げて、百姓 皆 我自ら然りと謂えり」というのは、「本当に優れた指導者(太上)の下では、実際に民衆(百姓)が功を立てて、何かを成し遂げた場合にも、彼らはそれを『自分たち自身で成し遂げたのだ』と主張するだろう」ということです。
これについては、少し極端な例を考えてみるとわかりやすいかもしれません。
たとえば、幼い子どもに人気の先生というのは、単に子どもに甘いだけの優柔不断な人である場合があります。
子どもはその先生がわがままを聞いてくれることを知っており、だからこそ、その先生のことを、「親しんで誉める」というわけです。
ですが、それは実際には子ども自身のためにはなっていません。
子どもたちはそうやって先生に甘やかされることで、むしろ成長の機会を逸しているとも言えます。
つまり、子どもたちはその先生に依存してしまって、自分の足で立つことができなくなっていってしまうわけなのです。
◎「本当の教師」は自分の存在意義がなくなる日を目指して教え続ける
このように、部下や生徒から親しまれている人が、「優れた指導者」であるとは限りません。
実のところ、そういった指導者は、単に「下の者たちにとって都合がいい存在」である場合も多いものです。
そして、そういった指導者が上に存在していることによって、下にいる人々は、自分自身の選択に責任を持たなくなっていきます。
なぜなら、上司や教師が自分たちに代わって選択をして、その責任を負ってくれるからです。
これは、生徒に教えるのが上手い教師がしばしば陥りがちなピット・フォールです。
というのも、教師の「教える能力」が高すぎると、生徒は「自分で理解しようとして格闘する」という試行錯誤をスキップできてしまうからです。
そして、その結果として、生徒たちは「自分自身で考える力」が伸びなくなってしまいます。
もちろん、教師自身には「悪意」があるわけではありません。
実際、そういった教師は純粋な「善意」でもって、「もっとわかりやすく教えよう」と真剣に考えているものです。
ですが、そうやってわかりやすく教えれば教えるほど、生徒は「わかった気分」になってしまい、そこで考えることをやめてしまいます。
その教師の説明があまりにもスッキリし過ぎているために、「どうもよくわからないな。一つ自分でも考えてみよう…」という次のアクションを、生徒は起こさなくなります。
そうして「わかりやすい説明」の中で生徒たちは安心しきってしまい、生徒たち自身が大きく成長することもなくなるわけです。
これが「親しみを込めて誉められる指導者」の問題点です。
こういった指導者はしばしば高く評価されますが、実際には部下や生徒の成長を阻害していることがあります。
もしも部下や生徒自身の成長を本当に望むなら、「親しみを込めて誉められること」から降りねばなりません。
「重要なのは、自分が親しみや敬意を得ることではなく、部下や生徒自身が成長することだ」
そのように考えることができて初めて、その人が「太上」になれる可能性が開けてきます。
部下や生徒の力を信じて、言葉を慎重に選んでは、ただ存在を知られているだけに留まる指導者。
それが「太上」です。
こうした指導者の元においてこそ、部下や生徒は自分から成長しようとするものなのです。
そしてこれは、「指導者自身の存在意義の否定」をも意味します。
なぜなら、その時、部下や生徒たちは指導者に寄りかからずに、自分の力で成長することができるようになるからです。
教師の仕事というのは本来的に矛盾しています。
というのも、教師の仕事は「自分の教えを生徒が必要としなくなるように導くこと」だからです。
生徒をいつまでも自分に依存させておく教師は、本来の役目を果たしていません。
「本当の教師」というのは、教えるべきことを教え終えたら、生徒が全てを悟って「お世話になりました」といって去っていくのを、むしろ大いに喜ぶものです。
つまり、「教える者」としての自分の存在意義が消えることを喜ぶのが、「真の教師」であるということです。
◎「わかった気」になって足を止めるなら、読まないほうがずっと良い
私が人に物を教える時は、だいたい以上のようなことを念頭に置いていることが多いです。
もちろん、「太上」を体現することはなかなか難しいものです。
たとえ私がどう考えていようと、私の教えることを全く受け付けない人がいるのと同様に、私の言葉に寄りかかろうとする人もいると思います。
でも、私としては、できるだけ私の言葉に寄りかかってほしくないと思っています。
私の文章を読んで「わかった気」になって歩みを止めてしまうくらいなら、むしろ読まれないほうがマシだとさえ思っているほどです。
でも、やっぱり私は「わかりやすく教えたい」という気持ちに、しばしば負けてしまいます。
それはきっと、私自身がわからなくて苦労した経験があるからであり、「苦労してわかった時の感動」を誰かと共有したいからなのではないかと思います。
「人を導く」というのは本当に難しいものだと思う、今日この頃です。
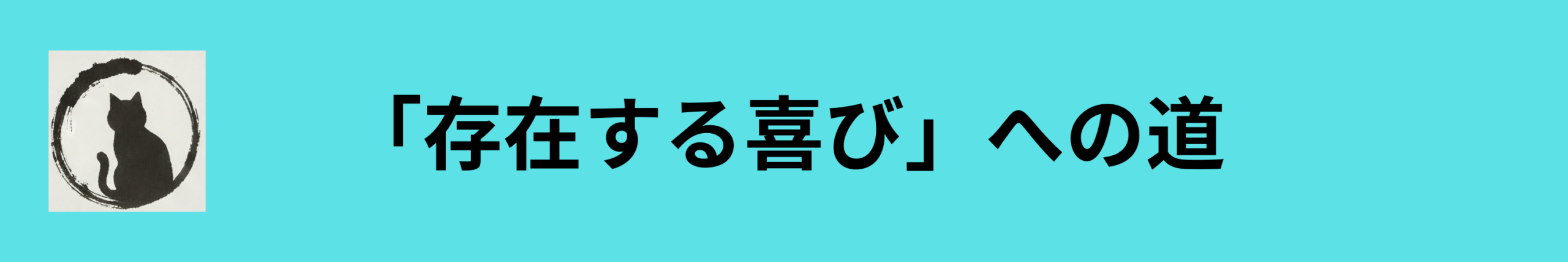
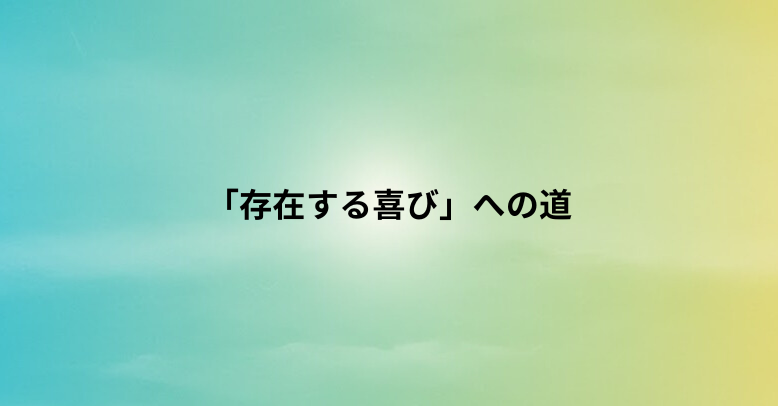
コメント